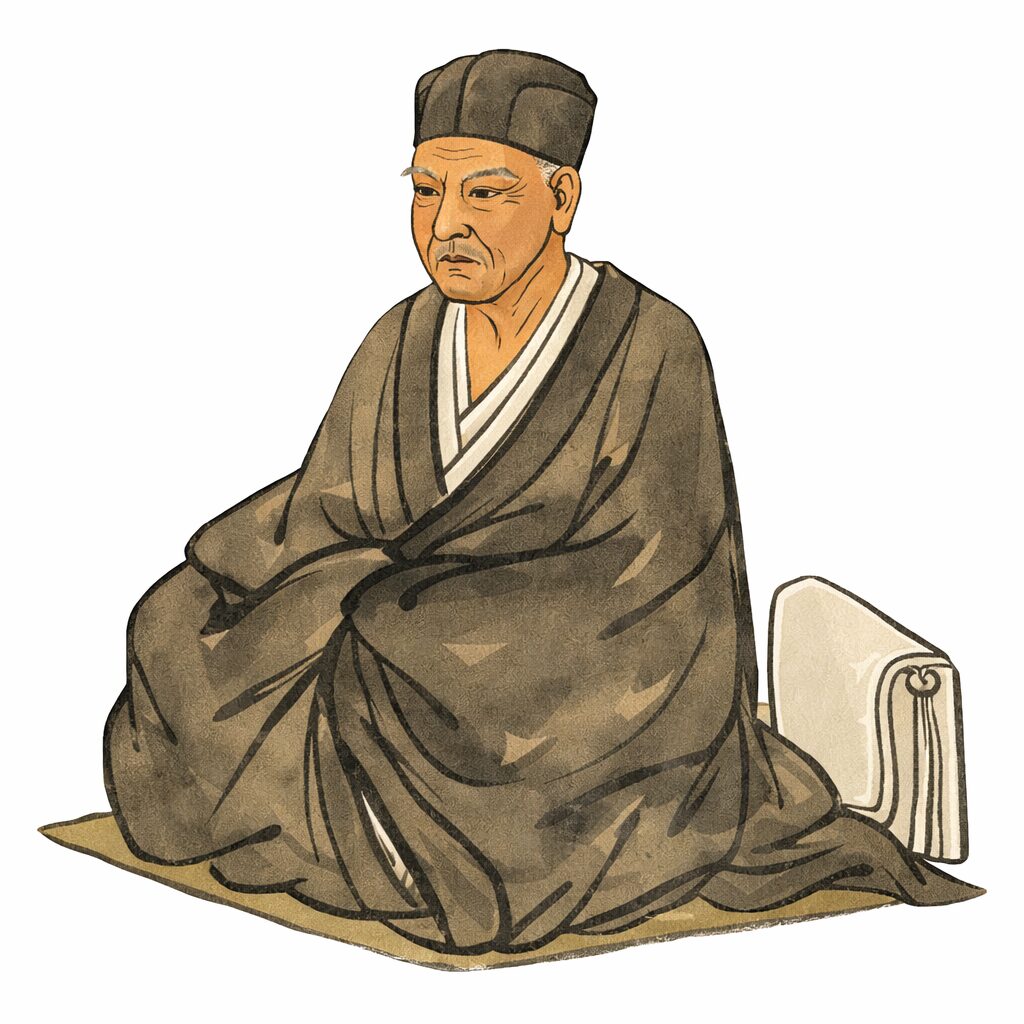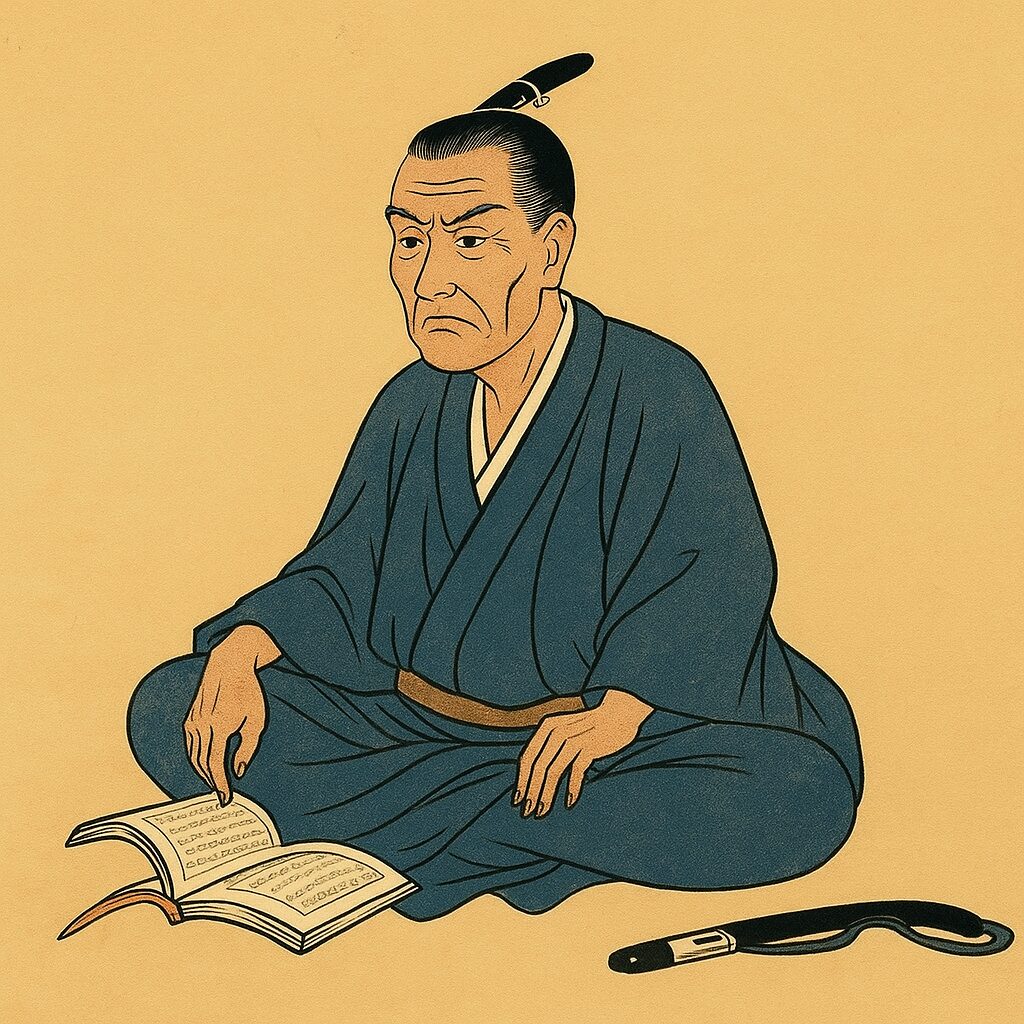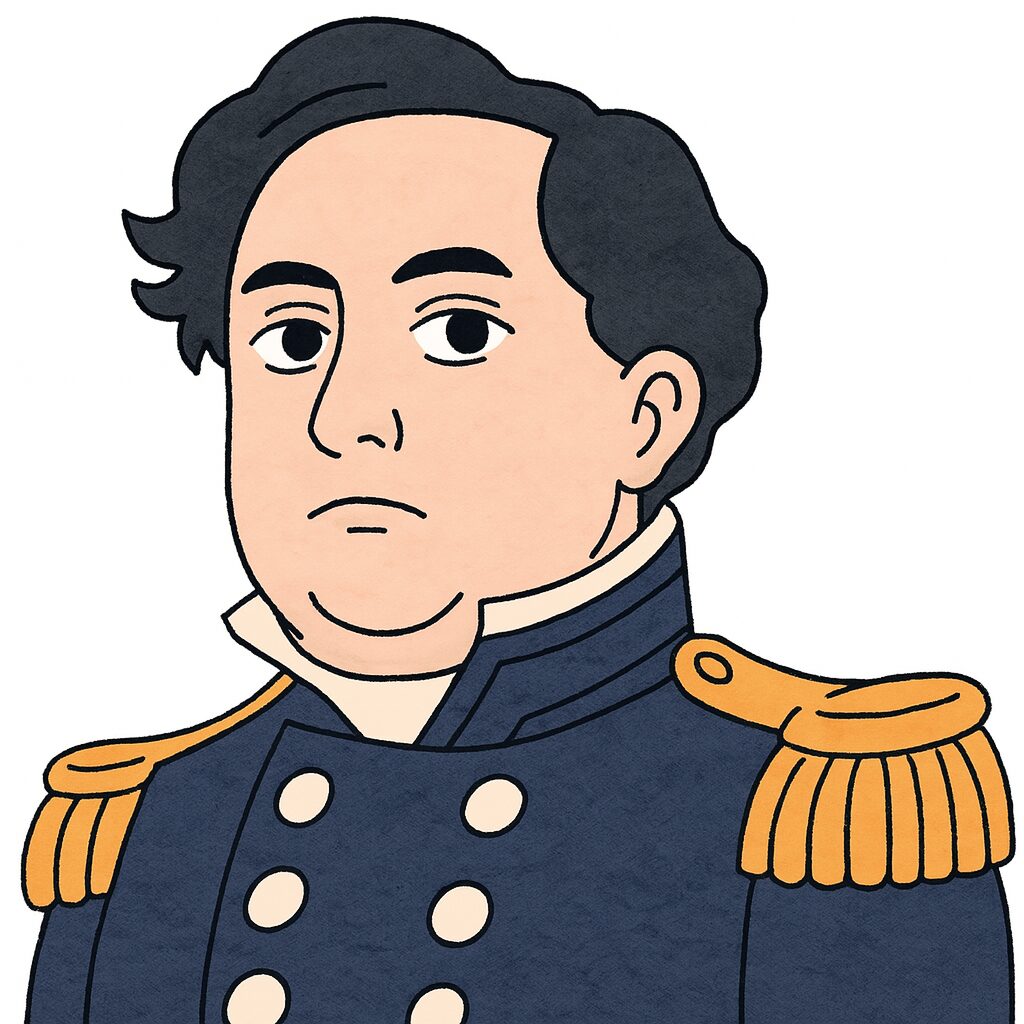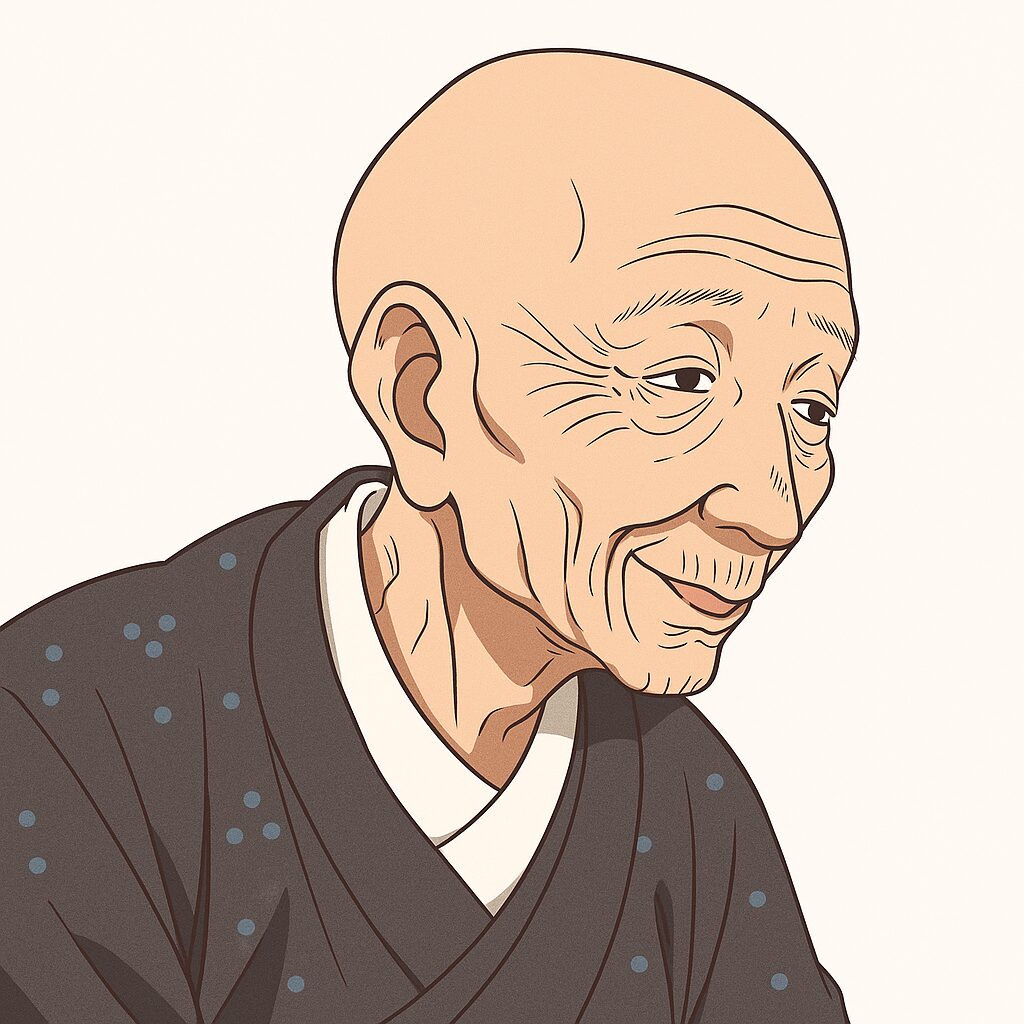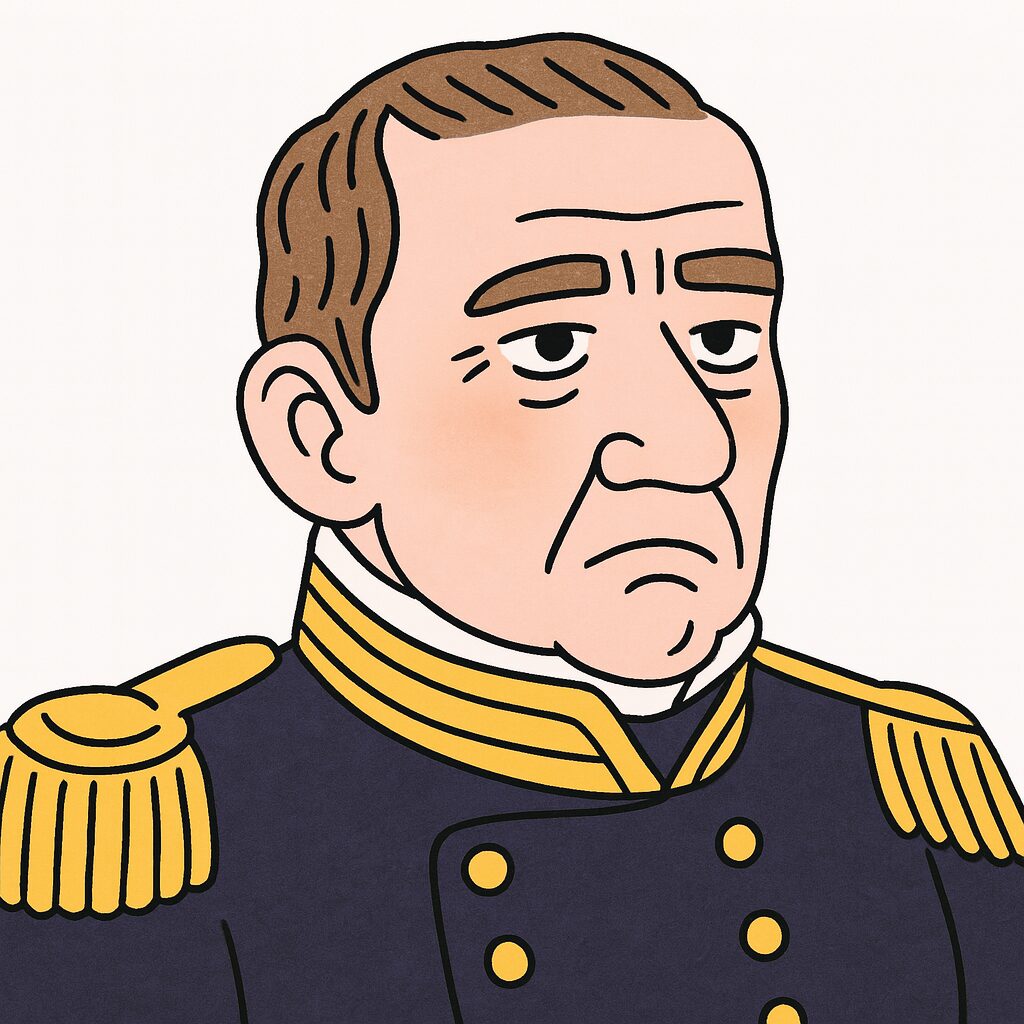
1853年、突然日本に現れたペリー来航の「黒船」。この出来事が、およそ200年間続いた日本の鎖国を終わらせ、近代国家への大きな一歩を踏み出すきっかけとなった。
この記事では、ペリーがどこに来航し、なぜ長崎ではなく浦賀を選んだのか、その背景にある国際情勢や、当時の日本社会に与えた衝撃、さらには今に残る「ペリーロード」や「語呂合わせ」といった記憶の形まで、わかりやすく深掘りしていく。歴史の大きな転換点となったペリー来航の多角的な側面を知り、今の日本につながるその影響を一緒に見ていこう。
- ペリー来航は、日本の鎖国を終わらせ、近代化を促すきっかけとなった。
- ペリーが長崎ではなく浦賀に来航したのは、江戸幕府に直接的な圧力をかけるためだった。
- 黒船の衝撃は、当時の日本社会に大きな混乱と好奇心、そして不安をもたらした。
- 開港地として選ばれた下田と函館は、アメリカの捕鯨産業と深く関連していた。
- 「ペリーロード」や年号の語呂合わせは、ペリー来航の歴史を現代に伝える重要な手がかりとなっている。
鎖国日本に迫る開国の波:なぜペリーはやってきたのか?
日本は江戸時代を通じて、外国との交流を厳しく制限する鎖国という政策を200年以上続けてきた。この鎖国は、キリスト教を広めないことと、国内の平和を保つことを主な目的としていた。外国との貿易は長崎で、中国(清)とオランダという限られた国とのみ行われていた。しかし、19世紀になると世界は大きく変わり、ヨーロッパやアメリカの国々(欧米列強)は、産業革命によって経済的にも軍事的にも力をつけ、アジアへの進出を活発にしていた。
鎖国日本の限界と欧米列強の圧力
アメリカ合衆国は、特に日本に対して開国を強く求めるようになった。その理由はいくつかある。まず、太平洋を横断する貿易ルートの安全を守りたいという目的があった。次に、嵐などで遭難したアメリカの船員が日本で保護された際、ひどい扱いを受けることがあったため、彼らを守るための取り決めが必要だった。そして、当時のアメリカは捕鯨が盛んで、捕鯨船が長い航海をするために必要な石炭や食料を補給できる場所を日本に求めていた。
たとえば、1849年にアメリカの捕鯨船ラゴダ号の船員が日本で厳しい扱いを受けた事件は、アメリカ国内で大きな問題となり、日本との条約を結ぶ必要性を高めることになった。この事件が、ペリーを日本に派遣する大きなきっかけの一つとなったのだ。
ペリー艦隊派遣の真のねらい:砲艦外交と太平洋戦略
ペリー提督が日本に送られたのは、単に話し合いをするためではなかった。彼は、軍事力を見せつけて相手を威嚇する、いわゆる「砲艦外交」という戦略をとった。これは、当時のアメリカがアジアに進出し、国際的な影響力を広げようとする大きな戦略の一部だった。
表面上は貿易や捕鯨船の保護が目的とされていたが、実はもっと深い理由があった。当時のアメリカは、中国(清)との貿易をさらに広げたいと考えており、そのための太平洋航路の安全確保と、航海中の船が燃料や食料を補給できる基地の確保がどうしても必要だったのだ。日本列島は、この太平洋航路にとって非常に重要な場所にあった。
ペリー来航:黒船が浦賀に現れた日
1853年7月8日の午後、マシュー・C・ペリー提督が率いる4隻の軍艦が、突然、浦賀の沖に現れ、停泊した。これらの船は、旗艦「サスケハナ号」をはじめとする、当時としては最新鋭の蒸気船を含んでおり、合計73門もの大砲を積んでいた。日本からの攻撃を警戒し、いつでも戦える態勢をとっていたと伝えられている。
黒船の衝撃:日本人の目に映った異様な光景
これらの軍艦は、これまで日本人が見たことのあるロシアやイギリスの帆船とは全く違うものだった。黒い船体、帆だけでなく、外輪と蒸気機関で進み、煙突からはモクモクと煙を上げるその姿は、当時の日本人にとって想像を絶するもので、「黒船」と呼ばれ、日本の社会に大きな衝撃を与えた。
この衝撃を、当時の人々はどのように感じたのだろうか。例えば、初めて空砲を撃たれたとき、江戸の町は一時的にパニックになったが、空砲だとわかると、まるで花火を楽しむかのように喜んだと伝えられている。しかし、やがて「本物の大砲が撃たれるかもしれない」といううわさが広まると、不安が広がっていった。
幕府の困惑と「無言の授受」
ペリーの来航の知らせを受けた幕府は、すぐに浦賀奉行所の役人を派遣したが、ペリーはアメリカ大統領からの手紙(親書)を、幕府のトップである将軍かそれに近い身分の者にしか渡さないと主張した。そして、「もし偉い役人が来なければ、江戸湾をさらに北上し、兵を連れて上陸して将軍に直接渡すことになる」と強く迫った。
幕府はペリーの強硬な態度に驚いたが、戦うことはできないと判断し、親書を受け取ることにした。そして1853年7月14日、現在の神奈川県横須賀市久里浜で、ペリーは幕府の代表者である戸田氏栄と井戸弘道に、大統領の親書などを受け取らせた。この時、外交上の話し合いは一切行われず、ただ手紙を受け取るだけという「無言の授受」が行われた。幕府は、将軍が病気であることを理由に、返事をするまでに1年間の猶予を求め、ペリーは1年後に再び来航することを告げて去っていった。
この「無言の授受」は、幕府が鎖国という長年のルールを形式上は守りつつも、ペリーの軍事的な圧力に対して、戦いを避けるために仕方なく対応した、という複雑な状況を示している。幕府は、アメリカとの衝突を避けながらも、これはあくまで例外的なことであり、正式な外交ではないという建前を保とうとしたのだ。
江戸市中の混乱と「上喜撰」の狂歌
ペリーの来航は、江戸の町にも大きな影響を与えた。空砲の音が響き渡ると、町民は一時的に混乱したが、やがて空砲だとわかると、花火のように楽しむ人もいたそうだ。翌日には、浦賀には見物人が集まり始め、江戸からも佐久間象山や吉田松陰といった有名な学者を含む多くの人々が押し寄せた。中には、幕府の命令を無視して、小さな船で黒船に近づこうとする人もいたほどだ。
この時の様子を風刺した狂歌が「泰平の眠りを覚ます上喜撰たつた四杯で夜も眠れず」だ。この歌には、緑茶の高級品「喜撰」と、たった4隻(船を数える時は「杯」と数えることがある)の蒸気船(上喜撰)によって、国中が大騒ぎになり、夜も眠れなくなるほどの衝撃を受けたという二つの意味が込められている。この歌は、当時の人々が感じた衝撃や動揺、そして社会の混乱をとてもうまく表現している。
開国の舞台:日米和親条約と開港地下田
ペリーは約束通り、1854年に7隻の軍艦を率いて再び日本に来航した。この再来航を受け、江戸幕府はアメリカの要求を受け入れ、「日米和親条約」を結ぶことになった。この条約によって、200年以上続いた日本の鎖国は、ついに終わりを告げることになる。
開港地が下田と函館だった理由
日米和親条約によって、日本が開くことになった港は、伊豆半島の南にある下田(静岡県)と、北海道の函館の2つだった。
函館が選ばれた理由としては、当時のアメリカの捕鯨船が津軽海峡を通って日本海まで進出していたため、捕鯨活動に必要な燃料や食料を補給したり、遭難した時に避難したりする場所として、函館が地理的に非常に良い場所だったことが挙げられる。この選択は、単に日本を開国させるだけでなく、当時のアメリカの捕鯨産業の戦略と深く結びついていたことを示している。
下田では、ペリー艦隊は入港後も熱心に測量活動を行った。浦賀や江戸湾での測量と同じように、下田湾内やその周りの海の測量が行われ、詳しい海図が作られたと考えられている。これらの測量活動は、単に地理的な情報を集めるだけでなく、将来、船が安全に航行したり、貿易活動を行ったりするための基礎を作る目的があった。
下田での異文化交流:日本初の洋楽コンサートも
日米和親条約が結ばれたことで、アメリカ人は下田の町を自由に歩けるようになった。これにより、黒船のアメリカ人と下田の町の人々の間で、様々な異文化交流が始まった。
具体的な交流の例として、了仙寺というお寺では、下田の町の人々を対象に、アメリカ海軍の軍楽隊によるコンサートが開催された。これは日本で初めての洋楽コンサートと言われており、日本の音楽の歴史にとって画期的な出来事だった。
また、初代アメリカ総領事のハリスが下田の玉泉寺に領事館を置いた際、混浴の風呂にいたお吉という女性を見て、彼女を自分の世話役にするよう要求したという話も残っている。お吉は婚約者がいたため断ったが、下田奉行所の役人に「国のために我慢してくれ」と言われ、ハリスのもとへ行くことになった。彼女は「ヤシャメン(アメリカ兵のこと)」「唐人(外国人)」などと罵倒されながら領事館に通い、その後の人生も苦労が多かったと言われている。このエピソードは、異文化間の摩擦や誤解、そして当時の日本の女性のつらい立場を浮き彫りにする話として語り継がれている。
「不平等条約」再考:為替レートと明治政府の思惑
日米和親条約は、一般的に「不平等条約」として認識されることが多い。しかし、その評価は様々な角度から考える必要がある。例えば、銀を使った日本とアメリカの為替レートは、実は日本側に圧倒的に有利だったという記録もある。これは、一般的に言われていることとは違う側面を示しており、条約の交渉において、日本側が必ずしも一方的に不利な立場だったわけではない可能性を示している。
このような「不平等条約」というイメージが広まった背景には、明治政府の政治的なねらいがあったと考えられている。明治政府は、江戸幕府の外交を批判し、自分たちの政府こそが正しいと主張するために、過去の条約を「不平等」だと位置づける必要があったのだ。このことは、歴史の記述や解釈が、常に客観的であるとは限らず、その時代の政治や社会の状況によって作られることがある、という大切な視点を与えてくれる。
なぜペリーは長崎を訪れなかったのか?:外交戦略の舞台裏
江戸時代の日本において、長崎は鎖国体制の中で、中国(清)とオランダとの貿易だけが許されていた特別な港だった。このため、長崎奉行所は外国との交渉を一手に引き受け、外国人との接触や情報管理を厳しく行っていた。長崎は、日本の対外的な窓口として機能していたが、その交流は幕府の厳しい管理下に置かれ、限られたものだった。
ペリーの狙い:江戸への直接的な威圧
ペリーが長崎を避け、浦賀(江戸湾の入り口)に直接来航した理由は、彼の周到な外交戦略にあった。その主なねらいは、幕府の中心である江戸に最も近い場所で威圧を加えることで、開国を迫る強い意志を直接的に示すことにあった。
ペリーは、長崎が長年オランダ人との交渉に慣れており、幕府の役人や民衆が外国人に対して「卑屈」になっていると判断し、アメリカ人にも同じような扱いを強制されるかもしれないと考えた。彼は、中国の広東のような古い習慣に縛られた港を避け、新しくて自由な上海に商人が集まったように、日本でも新しい交渉の場所を求めていた。
ペリーの目的は、これまでの枠組みにとらわれず、直接幕府に圧力をかけ、新しい関係を築くことだった。そのため、長崎を避けて、江戸へ最短ルートを選んだのだ。これにより、交渉が長引いたり、形だけになったりする可能性をなくし、早く開国を促すねらいがあった。
幕府の情報軽視と判断の遅れ
長崎奉行所からは、オランダ人から伝えられたペリー来航に関する情報を軽視するような報告があったという指摘もある。これは、幕府内部での情報収集や判断が遅れたこと、あるいは長崎という特別な場所の状況が、中央政府の危機感を十分に高められなかった可能性を示唆している。長崎は唯一の対外的な窓口だったにもかかわらず、そこから得られる情報が長崎奉行によって都合よくフィルタリングされ、中央に正確かつ緊急性を持って伝わらなかった可能性がある。
幕府は、欧米列強の軍事力や外交戦略に対する理解が不足しており、情報の軽視や判断の遅れが、ペリーの強硬な外交戦略に効果的に対応できない結果を招いた。鎖国体制が、外部からの脅威に関する情報を集めたり、早く決断したりすることを妨げる要因となったことは明らかだ。
ペリー来航を記憶するキーワード:年号と「ペリーロード」
ペリーが浦賀に来航した1853年を覚えるための語呂合わせは、日本の歴史の授業で広く使われてきた。
「日本の人は降参さ」:年号の語呂合わせに込められた意味
最もよく知られている語呂合わせは、「日本の人は(18)降参(53)さ」というものだ。この語呂合わせは、ペリーの軍事力を背景とした圧力に対して、日本が抵抗できずに開国を迫られた状況を象徴的に表現している。
他にも、「イヤでござんす、ペリーさん」という語呂合わせもある。これは、当時の日本がペリーの来航、ひいては開国を望んでいなかった心情を反映しており、外からの圧力による開国という側面を強調している。
これらの語呂合わせは、単に年号を覚えるための方法にとどまらず、当時の日本人がペリー来航という出来事をどのように感じ、どのような感情を抱いていたかを現代に伝える役割を果たしている。これらの言葉には、抵抗しきれなかった無念さや、望まない開国を強いられたことへの複雑な感情が込められている。
歴史を歩く「ペリーロード」:下田の観光名所
「ペリーロード」は、江戸時代の終わり頃に黒船で来航したペリー提督が、日米和親条約を結んだ後、下田の了仙寺へ向かう際に歩いたとされる小さな道だ。この歴史的な道は、静岡県下田市にある。
ペリーロードは、美しい柳並木と石畳が特徴的な景観を作り出しており、道の両側には明治時代や大正時代の洋風の建物や古い民家が立ち並び、異国情緒あふれる雰囲気を醸し出している。現在では、アンティークショップやカフェ、飲食店などが軒を連ね、人気の観光スポットとして多くの人々を惹きつけている。
この道には、黒船来航に関する歴史を感じさせる記念碑や看板があちこちにあり、訪れる人はペリー提督の像や当時の歴史を紹介するパネル展示などを通して、開国の歴史を学ぶことができる。ペリーロードは、散歩にぴったりの場所で、地元の特産品やお土産を買ったり、カフェで一休みしたりしながら、歴史の風を感じる静かな時間を過ごすことができる、下田市の重要な歴史的・観光的な遺産となっている。
FAQ:ペリー来航に関するよくある質問
Q1: ペリー来航は何年ですか?
A1: ペリーが初めて浦賀に来航したのは1853年だ。日米和親条約が結ばれたのは、その翌年の1854年だ。
Q2: ペリーはなぜ長崎ではなく浦賀に来航したのですか?
A2: ペリーが長崎を避け、浦賀に来航したのは、江戸幕府の中枢である江戸に直接的な圧力をかけ、迅速な開国を促すためだった。長崎での交渉では、これまでの慣例に縛られ、時間がかかったり、思うように交渉が進まなかったりする可能性を懸念したためだ。
Q3: 「黒船」とは何ですか?
A3: 「黒船」とは、ペリーが率いて来航した軍艦のことだ。蒸気機関で航行し、黒く塗られた船体は、当時の日本人にとって非常に珍しく、大きな衝撃を与えたため、そう呼ばれるようになった。
Q4: ペリー来航によって、日本はどのように変わりましたか?
A4: ペリー来航は、約200年間続いた日本の鎖国を終わらせ、日米和親条約の締結へとつながった。これにより、日本は国際社会への参加を余儀なくされ、その後の明治維新や近代化の大きなきっかけとなった。
Q5: 「ペリーロード」はどこにありますか?
A5: 「ペリーロード」は、静岡県下田市にある。ペリーが日米和親条約締結後、了仙寺に向かう際に歩いたとされる歴史的な小径で、現在は観光スポットとなっている。
結論:ペリー来航が切り開いた日本の近代化
ペリー来航とそれに続く開国は、日本の歴史において非常に大きな転換点だった。およそ200年間続いた鎖国が終わったことで、日本は否応なく国際社会へと参加することになり、その後の日本の政治、経済、社会、文化に計り知れないほど大きな影響を与えた。
開国後、幕府は西洋の技術や知識を取り入れることを加速させ、海を守る力を強くしたり(例えば品川台場の建設など)、軍隊の改革に着手したりした。これは、外国からの圧力によって日本の防衛意識が大きく変わったことを示している。また、開国は国内の政治的な対立を激しくさせ、最終的には江戸幕府が終わり、明治維新へとつながる大きな要因となった。
しかし、もしこの外国からの圧力がなければ、日本が自分たちの力だけで近代化の道を歩むことは、もっと難しかったかもしれない。ペリー来航は、日本が近代国家として生まれ変わるためのきっかけとなり、その後の急速な発展の原動力となった。この出来事は、日本が国際社会の一員として、自分たちの役割や立場をもう一度考え直す上で、なくてはならない経験だったと言えるだろう。
ペリー来航の歴史は、今の日本を理解する上で欠かせない出来事だ。この記事を通して、ペリー来航の背景、その後の変化、そして現代に続く歴史の記憶に触れることができたのではないだろうか。
ペリー来航や開国について、さらに深く知りたいなら、関連する書籍を読んでみたり、実際に浦賀や下田のペリーロードを訪れて、歴史の舞台を肌で感じてみることをおすすめする。歴史の息吹を感じながら、日本の大きな転換点について考えてみよう。