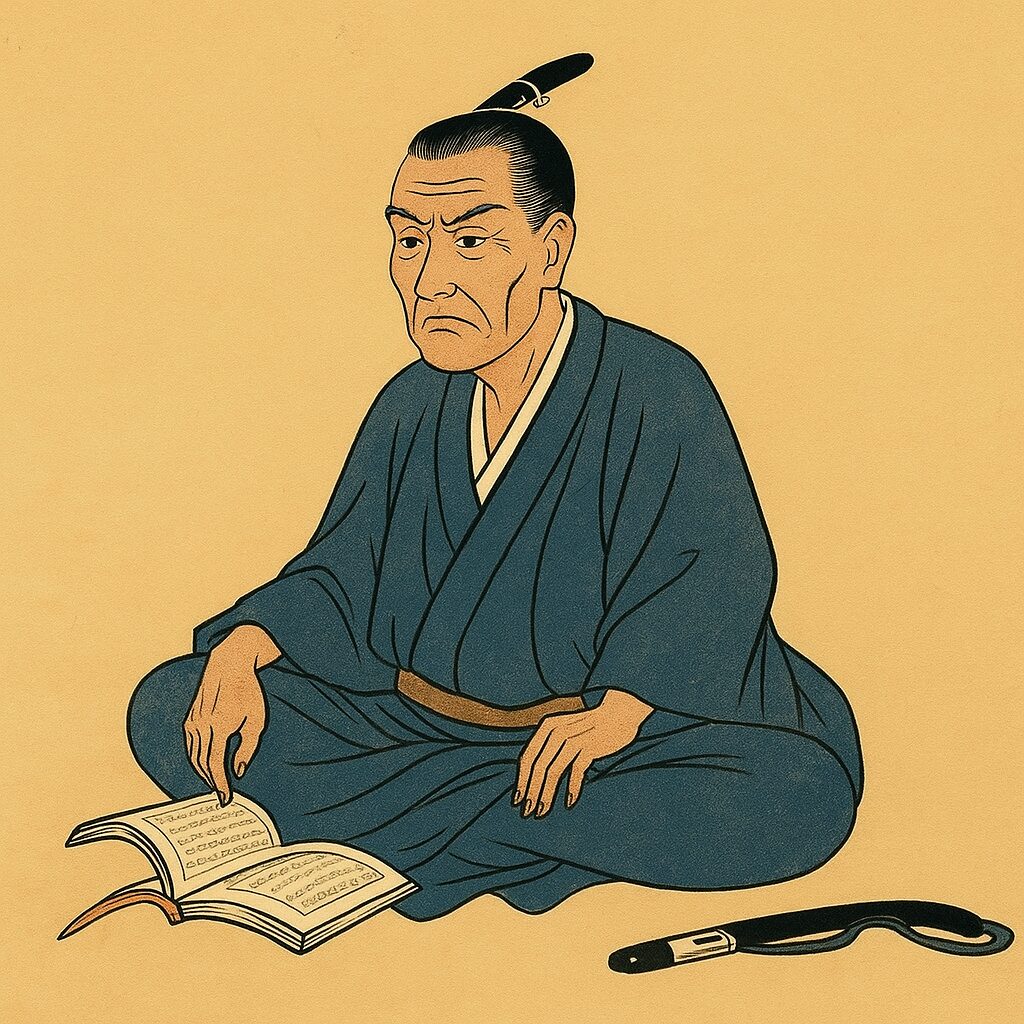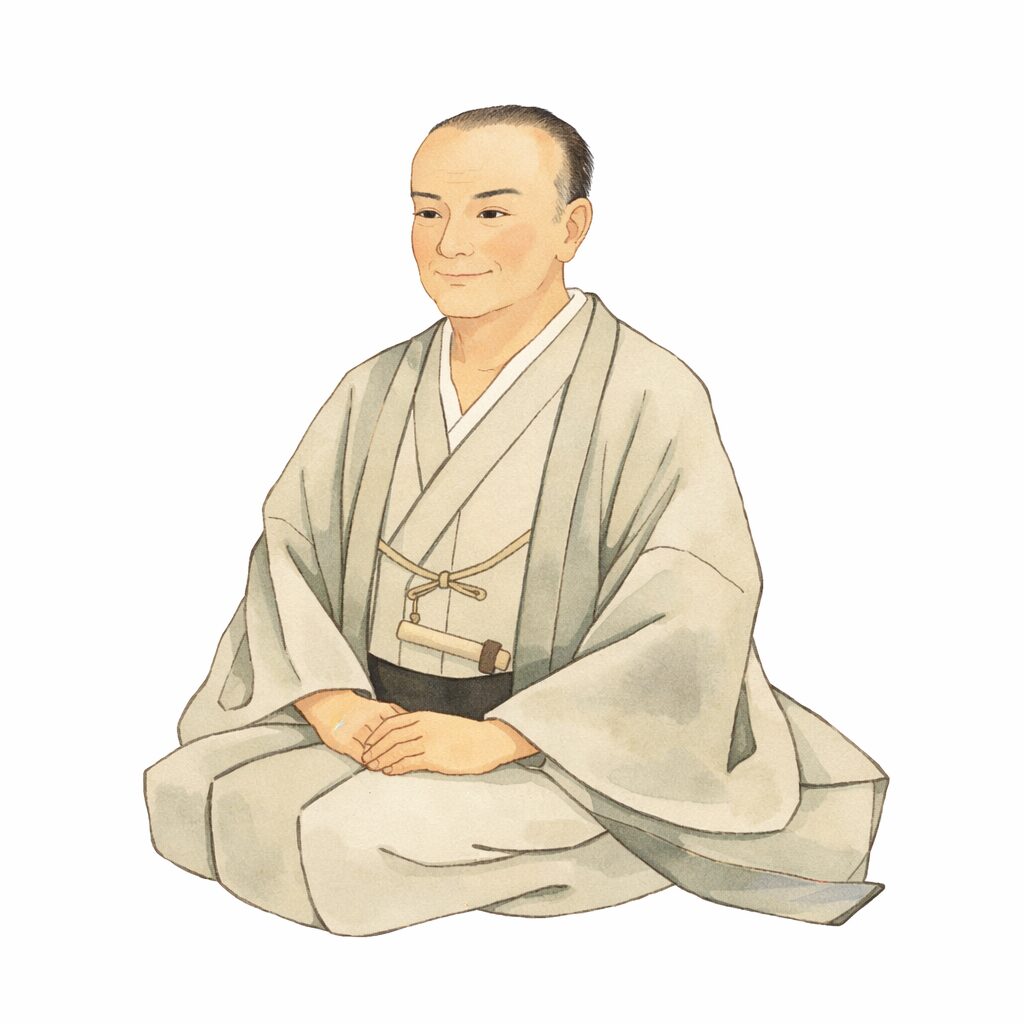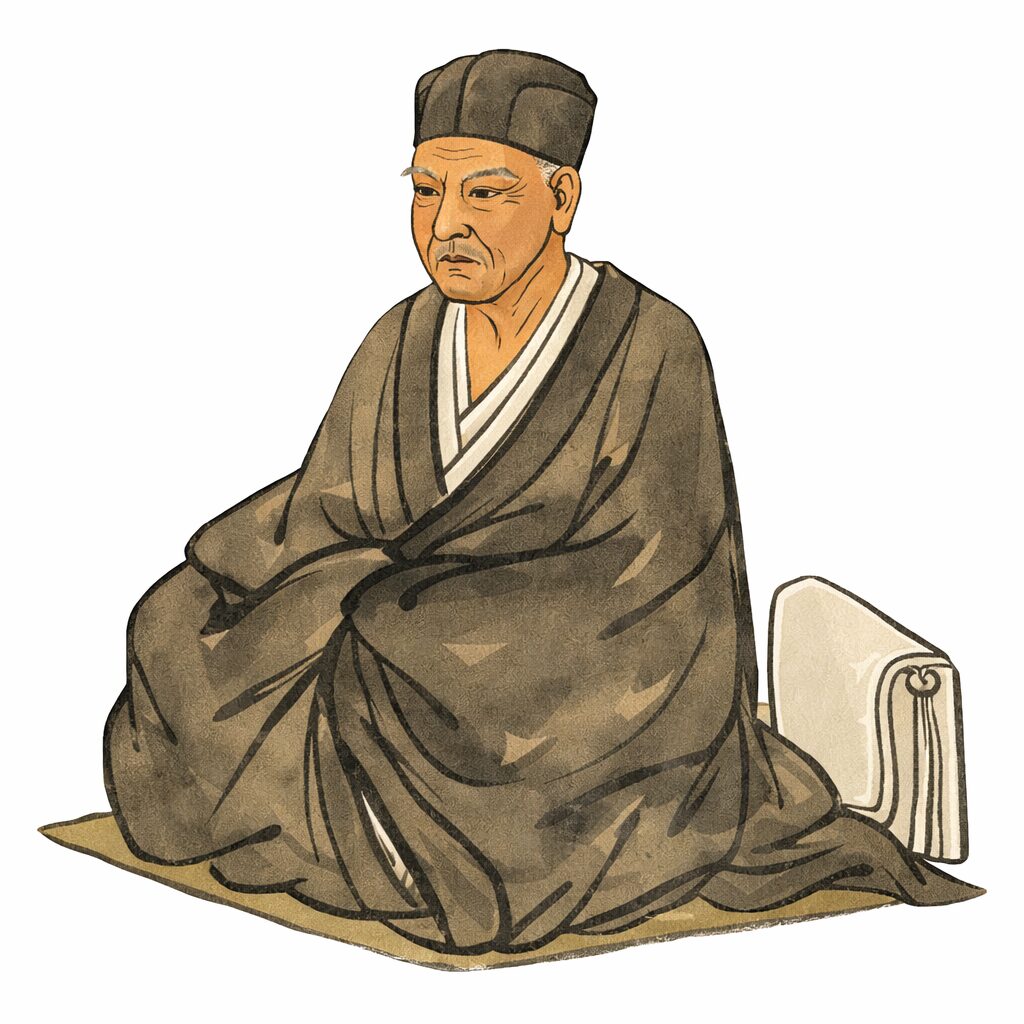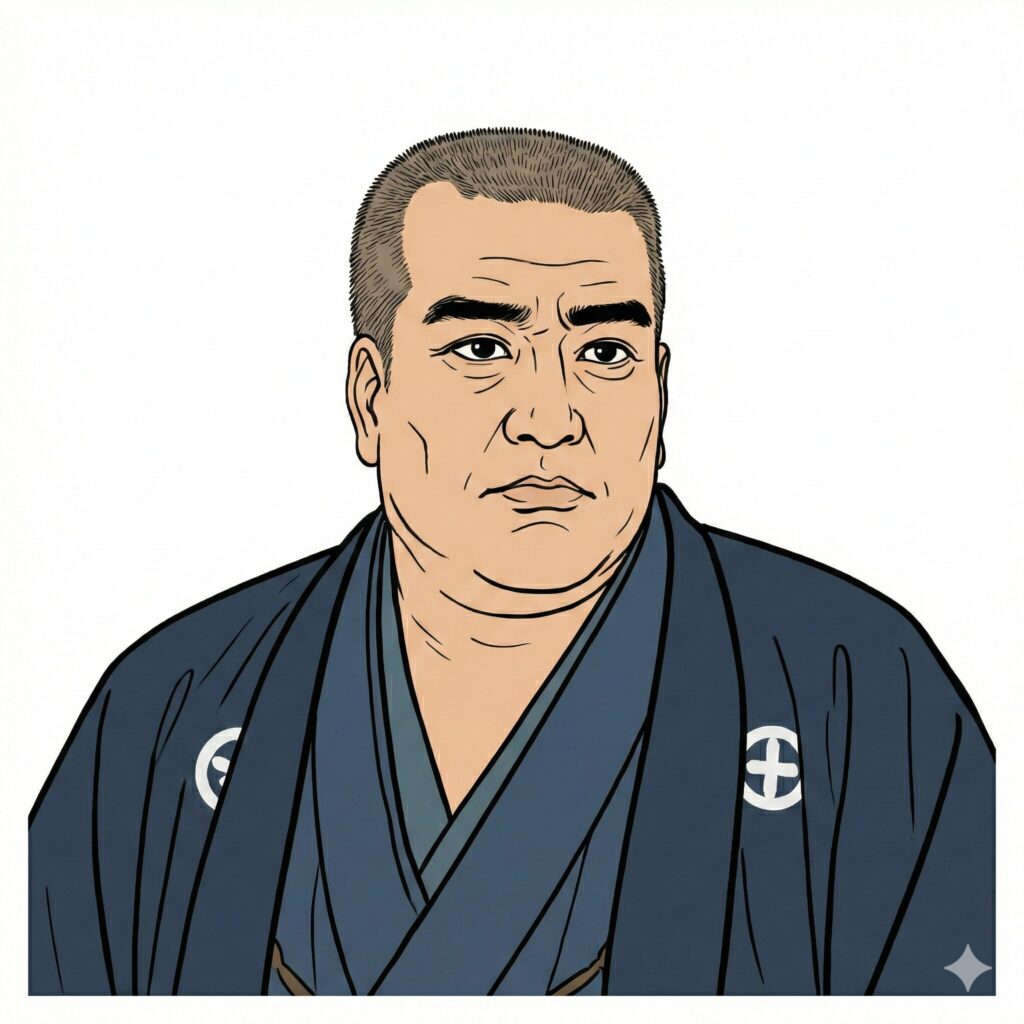「徳川家康のお墓」と聞いて、あなたはどこを思い浮かべるだろうか?静岡の久能山(くのうざん)なのか、それとも華やか絢爛(けんらん)な日光東照宮か。はたまた、愛知県岡崎市の大樹寺(だいじゅじ)周辺なのか。じつは徳川家康の墓所については、「三か所にある」という話を聞いたことがある人も多いのではないだろうか。
本記事では、この「徳川家康のお墓」に関する歴史的背景や、各地にある家康の霊廟(れいびょう)の由来、そして観光情報までを網羅的に紹介する。なぜ三か所に家康の墓があるといわれるのか?どこへ行けば家康に一番近づけるのか?そんな疑問にお答えする形で、この記事を読めば「徳川家康のお墓」の重要ポイントをすべて押さえられるように構成している。
さらに、記事の後半では現地へのアクセスや見どころ、知る人ぞ知るマニアックな逸話にも言及していくので、読み終えたら「家康の真の墓所」について人に語りたくなるはずだ。
では、壮大な徳川家康の歴史の締めくくりを飾る「お墓」の謎に迫っていこう。
徳川家康のお墓の概要
まず前提として、「徳川家康のお墓」と呼ばれる場所は大きく3つあるといわれる。久能山東照宮(静岡県静岡市)と、日光東照宮(栃木県日光市)、そして家康の菩提寺とされる大樹寺(愛知県岡崎市)だ。もっとも観光地として有名なのは豪華絢爛(ごうかけんらん)な日光東照宮だが、実は家康が最初に祀られたのは久能山東照宮である。
なぜこんなにも「徳川家康のお墓」が複数存在することになったのか? そこには家康が生前に示した遺言や、家康を神格化する「東照大権現(とうしょうだいごんげん)」としての扱い、また徳川幕府の権威付けといった複雑な事情が重なっている。
さらに大樹寺にも家康の墓碑があるため、どれが「本当の墓」なのかと混乱する方も多いだろう。しかし、それぞれに由緒正しい意味や役割があり、まさに徳川家康という人物の歴史が色濃く反映された「三か所説」になっているわけだ。いわば、家康にまつわる霊廟や墓所は、織田信長や豊臣秀吉のように一つに集約されていないというユニークさを持つ。
なぜお墓が三か所にあるとされるのか?
徳川家康は、江戸幕府の礎(いしずえ)を築いた人物として知られる。彼は征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)に任じられ、後に大御所(おおごしょ)政治を行い、さらには「東照大権現」として神格化された。家康が75歳で亡くなった際、最初に埋葬されたのは久能山であったが、後に江戸幕府の威光を示すために日光へと霊廟が移され、その後も大樹寺における法要などのために記念碑的な墓が存在することになる。
よく「亡骸(なきがら)は久能山に、魂は日光に、位牌は大樹寺に」といわれるが、諸説ある。実際には、遺骨を久能山から日光に移したともされているし、当初からどこに安置すべきかで家臣たちの間で意見が割れていたという話も伝わっている。それゆえに「三か所にお墓がある」と語られることが多いのだ。
ポイントは「神として祀る」ことを重視した結果、久能山と日光に二重に霊廟が整えられたという点。そして菩提寺としての役割を担う大樹寺にも家康の墓碑が設けられたという点。これが合わさり、「徳川家康のお墓は三か所にある」説が広まったというわけだ。
久能山東照宮:家康が最初に祀られた場所
久能山東照宮の歴史と特色
久能山東照宮は、静岡県静岡市駿河区(するがく)に位置する。駿河湾と富士山を見渡す絶景の地であり、何より徳川家康が「最初に」祀られた場所として知られる。家康が亡くなったのは元和2年(1616年)の4月17日(旧暦)で、遺命によって久能山に埋葬された。遺体を久能山に安置し、翌年には朝廷から家康に対して「東照大権現」の神号(しんごう)が贈られたのだ。
当初、徳川家康自身は生前に「遺体を久能山に葬り、そこから一年後に日光へ移す」と遺言したといわれる。この一連の流れを実行した結果、久能山は家康を祀る東照宮として最初に造営されることになった。現在でも久能山東照宮は国宝の社殿をはじめ、重要文化財が多く残っており、家康の墓所として最も古い歴史を持つ場所といえる。
久能山東照宮の魅力としては、石段の険しさと眺望の素晴らしさが挙げられる。参道は海岸沿いの麓から1,159段もの石段を上った先にあり、「ここを登りきれば家康の元へたどり着く」と思うと、不思議な達成感すら湧いてくる。もっとも、ロープウェイで山頂まで行くという現代的な手段もあるので、あえて石段を登るかどうかはあなたの体力と時間との相談だ。
なお、久能山はイチゴ狩りなどの観光スポットでも有名であり、参拝後に周辺を散策して楽しむ観光客も多い。
久能山へのアクセスと参拝ポイント
- アクセス
- 静岡駅からしずてつジャストラインバス「日本平ロープウェイ」行きに乗り、バス停「日本平ロープウェイ」で下車後、ロープウェイで久能山山頂へ。
- もしくは、車で東名高速道路「静岡IC」から約30分ほどで日本平ロープウェイ駅まで行き、そこからロープウェイを利用。
- 参拝ポイント
- 1,159段の石段:古来からの正攻法で参拝したいならこちら。体力に自信がある方はチャレンジしてみては。
- 社殿の美しさ:極彩色の社殿は国宝に指定されており、細部の彫刻や意匠が見事である。
- 家康のお墓(神廟):本殿の奥にある神廟で、家康が眠るとされる重要スポット。静かに手を合わせよう。
久能山東照宮公式サイトなども確認しておけば、拝観料や営業時間が最新の情報で分かるので、事前にチェックすることをおすすめする。
日光東照宮:徳川の威光を象徴する霊廟
日光東照宮の由来と造営の背景
次に紹介するのは、世界的にも有名な日光東照宮。栃木県日光市に位置し、徳川家康をはじめとする徳川家ゆかりの霊廟が存在する。日光という場所は、古くから山岳信仰の地として知られていたが、家康の遺言に基づき「一年後に日光へ祀る」という計画が実行され、元和3年(1617年)に家康を祀る社殿が造営されることになった。
その後、三代将軍の徳川家光(いえみつ)により大規模な改修が行われ、現在のきらびやかな社殿群が完成したという経緯がある。江戸幕府の権力を誇示するかのごとく絢爛豪華な社殿が立ち並んでいるのは、家光の意向が強く反映されているためだ。
「日光を見ずして結構(けっこう)と言うなかれ」という言葉があるが、これは日光の風光明媚(ふうこうめいび)さに加え、日光東照宮の圧倒的な豪華さを指しているともいわれる。単に「お墓」というよりは、「神として祀られた家康を讃える霊廟兼観光名所」という色合いが強い場所だ。
見どころと参拝時の注意点
- 陽明門(ようめいもん):日光東照宮を象徴する門。白と金のコントラストや繊細な彫刻が見応え抜群。国宝に指定されている。
- 眠り猫(ねむりねこ):左甚五郎(ひだりじんごろう)作と伝わる有名な彫刻。小さいながらも存在感があるのでお見逃しなく。
- 奥社(おくしゃ)の墓所:家康を祀る本質的な部分。奥社宝塔(ほうとう)と呼ばれる家康の墓所があり、こちらが家康の御霊(みたま)が最終的に鎮まる場所だとされる。
参拝の際には、混雑時期(秋の紅葉シーズンや大型連休など)を避けると、よりゆったりと見学できる。また、境内は思いのほか広く石段が多いので、歩きやすい靴で行くのがベターである。
大樹寺:家康と三河武士の精神的支柱
三河武士と大樹寺の深い関係
愛知県岡崎市にある**大樹寺(だいじゅじ)**は、もともと松平(まつだいら)家(=後の徳川家)の菩提寺であり、家康が「もし戦に敗れたら、ここで自害する」と決意していたほどの特別な場所だ。若き日の家康(当時は松平元信や家康など諸々改名している)が、戦に疲れたり、精神的に参ってしまいそうな時に何度も訪れた場所でもある。
家康が生まれ育った三河(みかわ)の地で信仰されていた寺ということもあり、ここには家康だけでなく歴代の松平・徳川家の墓所がある。家康が江戸幕府を開く以前からのゆかりの地なので、家康にとって大切な「心の支柱」であったとも言えるだろう。
大樹寺での徳川家康のお墓に関する逸話
大樹寺には、家康が祖先への感謝と自らの覚悟を示すためにつくった墓所がある。実際に訪れると「松平家廟所(びょうしょ)」と呼ばれる区画に歴代の当主の墓が並んでおり、その中に家康の墓碑も確認できる。これが「徳川家康のお墓」の三か所目だとされる所以(ゆえん)だ。
もっとも、こちらには家康の遺骨自体はないとされているが、菩提寺としての役割を果たす大樹寺において家康の名前を刻んだ墓碑が存在すること自体が重要なのだ。愛知県岡崎市は家康の誕生地であり、多くの家康ファンがここを巡礼スポットの一つとして訪れる。
徳川家康のお墓にまつわるその他の説や伝説
家康遺骨の移動説や隠し墓説
歴史のロマンか、それとも幕府の秘密主義か、徳川家康の遺骨の行方についてはさまざまな説がある。たとえば、久能山に埋葬したのちは、完全に日光へ移したとも言われる。一方で、一部の遺骨だけを日光へ移し、大半は久能山に残したという説、はたまた家康の最期を弔うために大樹寺にも分骨(ぶんこつ)がなされたのではないかと推測する声もある。
また、一部のマニアの間では「家康の真の墓は別の場所にひっそりと隠されている」という都市伝説めいた話もささやかれている。これは幕府が政治的事情から家康の実際の埋葬場所を隠したというストーリーだが、もちろん史料による明確な裏付けはなく、あくまで噂レベルである。
“最強”の風水説と江戸幕府の繁栄の謎
一方、徳川幕府の安定や繁栄が約260年も続いた背景には、家康が風水の力を利用したという説も根強く存在する。日光は古くから龍脈(りゅうみゃく)が通る霊山として知られ、そこに家康の墓を置くことで徳川家の繁栄を永続化したというのだ。
これは当時の学問や信仰(陰陽道や神道)などが複雑に絡み合った可能性も否定できない。たとえば、家康と密接に交流があった天海(てんかい)僧正が日光東照宮の造営に大きく関わり、風水的観点をもとに家康の神廟を設計したという説は、歴史ファンの間ではわりと有名な話である。真偽のほどはさておき、こうした風水伝説が「徳川家康のお墓」を一層ミステリアスな存在へと仕立て上げていることは間違いない。
徳川家康のお墓をめぐるよくある質問
ここでは、「徳川家康のお墓」を検索する人が抱きがちな質問をピックアップしてみよう。
- Q:本当に三か所のお墓すべて回る必要はあるのか?
A:観光目的であれば、日光東照宮だけでも見どころは十分だ。ただし、家康ファンや歴史好きなら、久能山と大樹寺もあわせて巡ると家康の人生観や徳川幕府成立のドラマがより深く体感できる。 - Q:御朱印(ごしゅいん)はもらえるのか?
A:久能山東照宮・日光東照宮ともに御朱印がある。また、大樹寺でも御朱印を受け付けているので、参拝記念に頂くのも楽しいだろう。 - Q:服装や参拝マナーは厳しいのか?
A:神社や寺院によっては服装規定が厳しい場合があるが、基本的には常識の範囲で清潔感のある服装なら問題ない。ただし、奥社などへ続く急な階段もあるため、動きやすい格好と靴を推奨する。
観光・参拝前に知っておきたい豆知識
服装やマナーに関する注意点
- 歩きやすい靴:久能山も日光東照宮も石段や坂道が多く、大樹寺も広い境内を移動するので、スニーカーなどの歩きやすい靴がベターである。
- 写真撮影:社殿内部での撮影が禁止されている場合もある。特に日光東照宮は一部撮影禁止エリアがあるため、現地の案内板に従おう。
- 静粛な態度:お墓参りや霊廟参拝であることを忘れず、周囲の雰囲気を尊重する。大声での会話やふざけた行動は厳禁だ。
周辺施設やグルメ情報
- 久能山周辺:イチゴ狩りや久能山下の石垣いちごの直売所、また駿河湾の海鮮が楽しめるスポットも点在している。
- 日光周辺:日光湯波(ゆば)や湯波懐石が名物。華厳の滝や中禅寺湖といった自然の絶景スポットと合わせて巡るのがおすすめだ。
- 大樹寺周辺:岡崎といえば八丁味噌が有名。味噌煮込みうどんや味噌カツなど、コク深い三河グルメを堪能できる。
いずれも年間を通じて観光客が多い地域なので、宿泊施設や飲食店は豊富だ。しかし人気シーズン(紅葉の時期や連休)は混雑が予想されるので、計画的な予約やスケジュール調整が欠かせない。
まとめ
「徳川家康のお墓」はなぜ三か所にあるのか。その答えは、家康自身の遺言や神として祀るための儀礼、そして徳川幕府の権威や風水に対するこだわりなど、さまざまな要因が重なった結果だといえる。久能山東照宮は家康が最初に安置された由緒ある場所、日光東照宮は幕府の威光を誇る豪華絢爛な霊廟、そして大樹寺は家康の菩提寺として三河武士の精神的支柱となっている。
どの場所もそれぞれが徳川家康という人物の一面を映し出しており、歴史に興味がある人はもちろん、ちょっとした観光感覚でも十分に楽しめるスポットだ。「徳川家康のお墓」 で検索する方の多くは、歴史的知識や観光情報、アクセス方法、そして謎や伝説を知りたいと考えているだろう。本記事ではそれらを総合的に解説したが、一度現地を訪れてみると、より一層家康の偉大さや当時の世界観を体感できるはずだ。
もしまだ「家康の人生そのものをよく知らない…」という方は、弊社サイト内の『徳川家康の生涯をまとめた記事』もあわせて参照していただきたい。家康の生い立ちから関ヶ原の戦いや大坂の陣、さらには将軍職の譲位(じょうい)と大御所政治の実態まで、詳細を知ることで彼の最期やお墓への理解がより深まるだろう。
最後に、もしこの記事が面白かったり、役に立ったと思ったら、ぜひSNSなどでシェアしていただきたい。歴史好きの仲間と「家康の墓はどこにあるのか」を語り合うと、意外な新発見があるかもしれない。江戸幕府を265年も支えた男の眠る地——一度は訪れておきたい日本史ロマンの聖地だ。