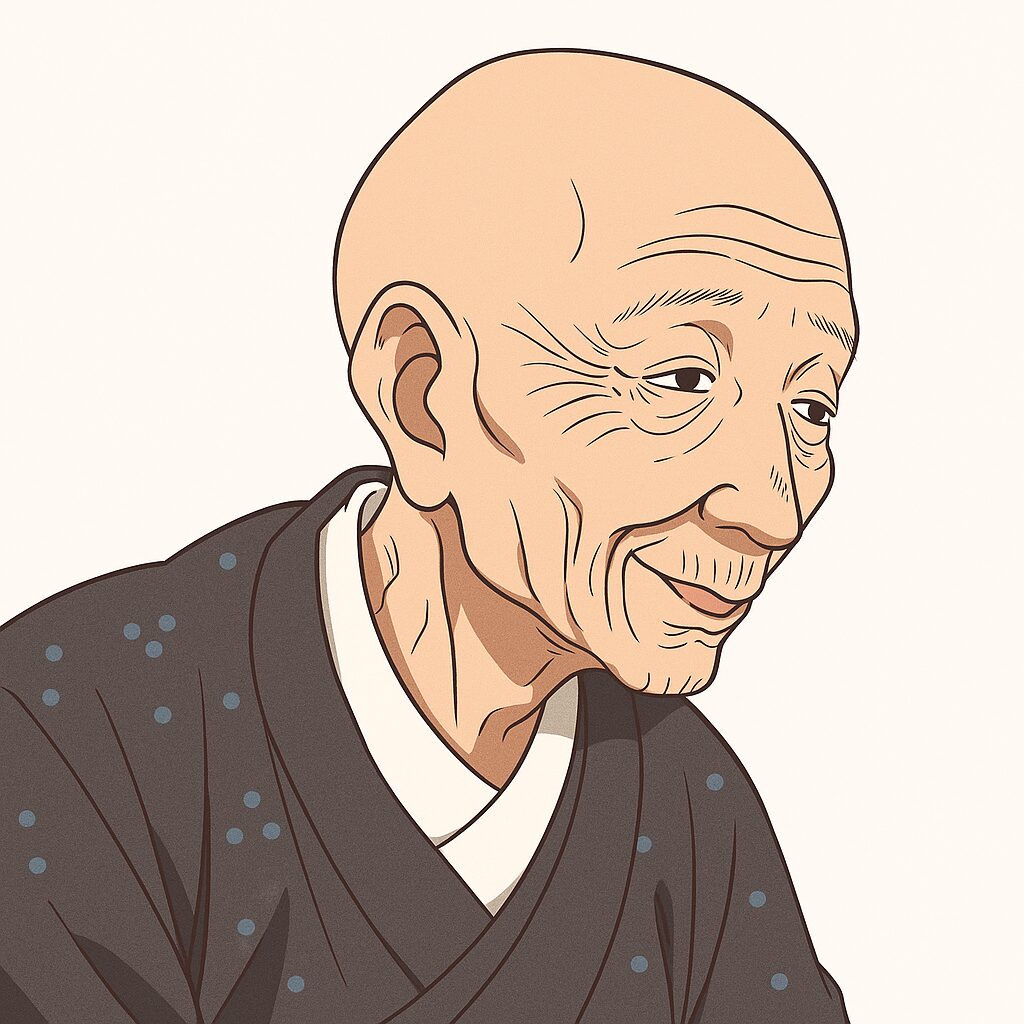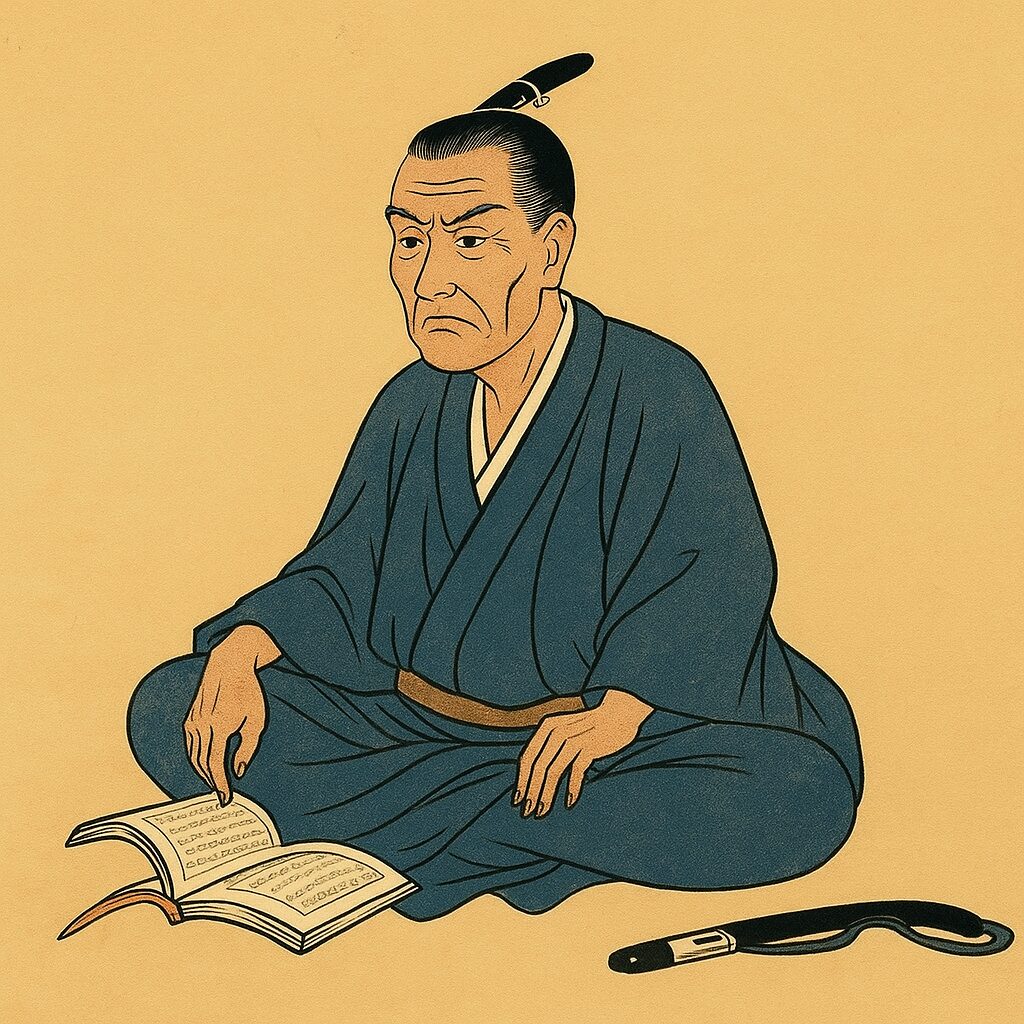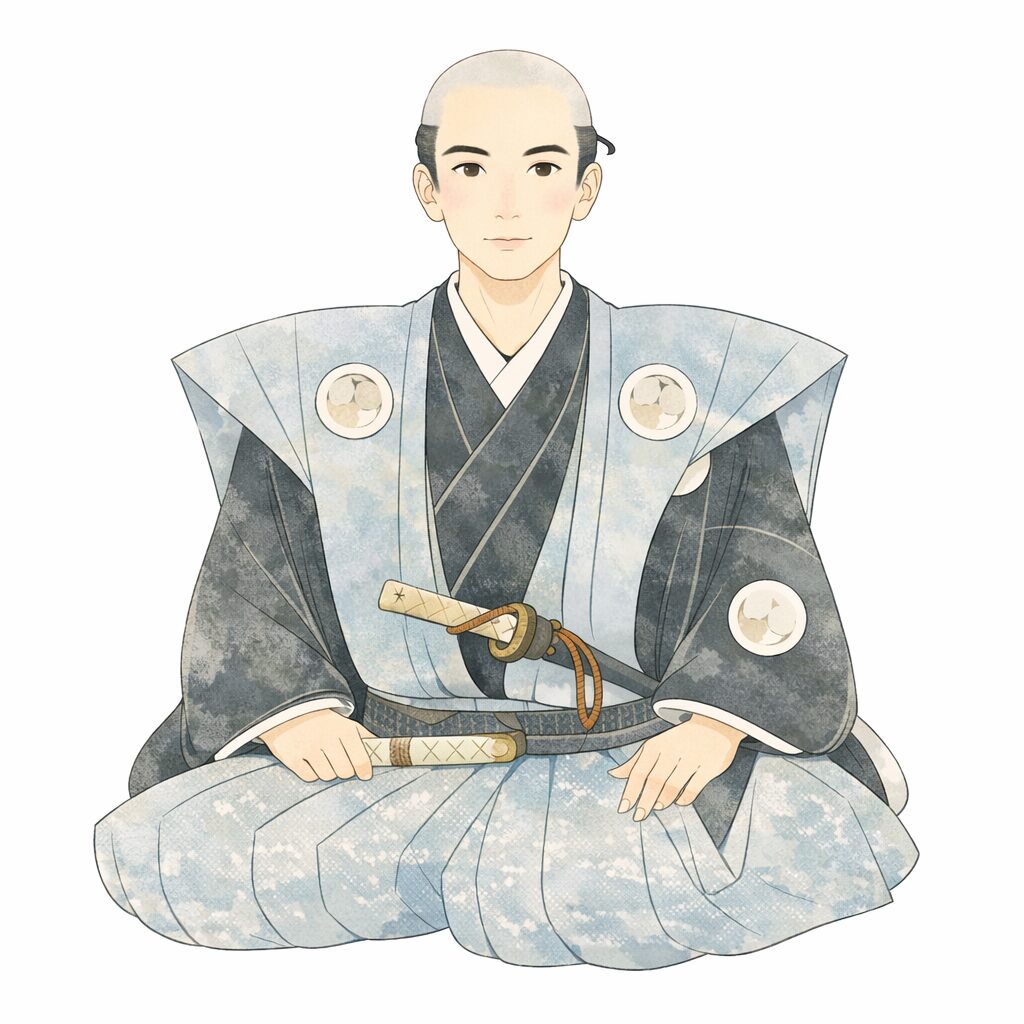『水戸黄門』として、お供の助さん・格さんと共に諸国を漫遊し、悪を懲らしめる正義の味方――。多くの人が徳川光圀にそんなイメージを抱いているだろう。しかし、その素顔は、物語の姿とは大きく異なる、複雑で人間味あふれるものだった。
若い頃は派手な身なりを好む「かぶき者」として、常識はずれの行動を繰り返す破天荒な青年。それが一冊の歴史書との出会いをきっかけに、学問の道に目覚め、生涯をかけた大事業『大日本史』の編纂に着手する。この事業は、日本の歴史学に大きな足跡を残しただけでなく、約200年後の日本の歴史そのものを動かす思想的な源流ともなった。
藩主としては領民の暮らしを思う合理的な改革を進める一方、日本で初めてラーメンを食べたと言われるほどの旺盛な好奇心も持ち合わせていた。
この記事では、そんな伝説のベールに包まれた徳川光圀の、知られざる実像に迫っていく。
徳川光圀とはどのような人物だった?
水戸徳川家に生まれた生涯と「黄門さま」の由来
徳川光圀は、1628年6月10日、水戸藩の初代藩主である徳川頼房の三男として生まれた
その生涯は、藩主としての政治から、学者としての探究、そして静かな隠居生活まで、いくつかの時期に分けられる。
| 年 | できごと |
| 1628年 | 水戸藩初代藩主・徳川頼房の三男として生まれる |
| 1633年 | 兄がいたが、世子(跡継ぎ)に決まる |
| 1657年 | 歴史書『大日本史』の編纂を始める |
| 1661年 | 水戸藩の第2代藩主となる |
| 1690年 | 藩主の座を養子の綱條に譲り、隠居する |
| 1691年 | 西山荘(せいざんそう)に移り住み、静かな生活を送る |
| 1700年 | 73歳で生涯を終える |
多くの人が彼を「水戸黄門」や「黄門さま」と呼ぶ。この「黄門」とは、彼が就いていた役職名に由来する
しかし、実は「水戸黄門」は光圀一人だけではなかった。水戸藩の歴代藩主の中で、光圀を含めて7人が中納言の位に就いている
若き日は破天荒?「かぶき者」としての一面
今では賢者のイメージが強い光圀だが、若い頃は全くの別人だった。派手な服装や常識はずれの行動を好む「かぶき者」として知られ、その行動はかなり破天荒だった
家臣の忠告に耳を貸さずわがままに振る舞い、父である頼房を心配させたという記録が残っている
そんな光圀が生まれ変わるきっかけとなったのが、18歳の時に読んだ一冊の本、中国の歴史家・司馬遷が書いた『史記』だった
「伯夷伝」には、伯夷と叔斉という兄弟の物語が記されている。父である王は弟の叔斉に跡を継がせたいと考えていた。父の死後、叔斉は兄の伯夷に王位を譲ろうとするが、伯夷は父の遺志を尊重してこれを拒否する。結局、兄弟は二人とも王位を辞退して国を去ってしまうという話だ
この物語は、光圀自身の境遇と深く重なった。光圀は三男でありながら、病弱な兄を差し置いて跡継ぎに選ばれていた
家族構成と子孫について
光圀の家族関係、特に兄との関係は、彼の人生を理解する上で非常に重要だ。父は初代水戸藩主の徳川頼房、母は側室の久子
本来であれば長男である頼重が水戸藩を継ぐはずだった。しかし、頼重が生まれた当時、頼房の兄である尾張徳川家と紀伊徳川家にまだ跡継ぎがおらず、頼房はそれに遠慮して頼重の存在を公にしなかった
兄を差し置いて家督を継ぐことになった罪悪感は、光圀の心に生涯重くのしかかっていた
この光圀の決断により、水戸徳川家は兄の血筋によって受け継がれていくことになった。その家系は現代まで続いており、現在の第15代当主・徳川斉正(なりまさ)氏は、徳川ミュージアムの理事長などを務めている
光圀の人柄がわかる有名な逸話
学問によって生まれ変わった光圀の人柄は、数々の逸話からうかがい知ることができる。彼の判断基準は、法律や慣習に盲目的に従うのではなく、人間性や理性を重んじる独自の倫理観に基づいていた。
ある時、領内で親を殺した男が捕まった。男は反省の色を見せず、「自分の親を殺しただけだ」と開き直った。これを聞いた光圀は、彼をすぐに処刑せず、「道徳を教えなかった為政者である自分の責任だ」と考えた。そして、男に3年間『論語』の講義を受けさせた。やがて男は自らの罪の重さを悟り、自ら死刑を願い出たという
また、光圀が大切に飼っていた鶴を殺してしまった農民・長作がいた。光圀は激怒したが、いざ斬り捨てようという瞬間に刀を収め、「この者を殺しても鶴は生き返らない。獣一匹のために人を殺すわけにはいかない」と言って彼を許した。さらに、「無一文で放り出せば、またどこかで悪事を働くだろう」と考え、彼に米と銭を与えて立ち直る機会を与えた
一方で、彼は時の将軍・徳川綱吉が出した「生類憐れみの令」には公然と反対した。特に犬を過剰に保護するこの法律を非合理的だと考え、幕府の役人に対して批判的な言葉を述べた記録が残っている
これらの逸話は、光圀が状況に応じて、人間性と理性を天秤にかける、非常に人間味あふれる為政者であったことを物語っている。
質素倹約を旨とした食生活
光圀は藩の財政のために倹約令を出すなど、質素倹約を奨励したことで知られる
特に鮭が好物で、カマやハラス、皮の部分を好んで食べたという
藩の財政を預かる為政者として倹約を推進する一方で、個人の生活では食文化の探求を楽しむ。この二面性は、彼が公的な責任と私的な興味を明確に区別できる、洗練された人物であったことを示している。藩の財政を引き締めることは、自らの知的好奇心や探求心を抑圧することと同じではないと考えていたのだろう。
歴史に名を刻んだ徳川光圀とは?その偉大な功績と意外な一面
生涯を捧げた一大事業『大日本史』の編纂
徳川光圀の最大の功績は、日本の歴史書『大日本史』の編纂事業を始めたことだ。1657年に着手されたこの事業は、光圀の死後も続けられ、最終的に完成したのは1906年(明治39年)、実に250年もの歳月を要した壮大なプロジェクトだった
この歴史書は、初代・神武天皇から南北朝時代を統一した後小松天皇までの歴史を、中国の『史記』に倣った「紀伝体」という形式で記述している
『大日本史』は、その内容において、当時の常識を覆す三つの大きな特徴(三大特筆)で知られている
- 神功皇后を天皇ではなく、天皇の后として扱ったこと。
- それまで天皇と認められていなかった大友皇子を、弘文天皇として正式な天皇としたこと。
- そして最も重要なのが、皇室が二つに分かれて争った南北朝時代において、南朝こそが正統な皇室であると結論付けたこと。
この事業は、単なる歴史書の編纂にとどまらなかった。光圀は江戸の藩邸に「彰考館」という研究機関を設立し、全国から優れた学者たちを招聘した
そして歴史の皮肉とも言うべきことに、この水戸学が、幕末の日本に大きな影響を与えることになる。特に、天皇の絶対的な正統性を強調する「尊王論」は、徳川幕府を倒して天皇中心の新しい国を作ろうとする思想(尊王攘夷運動)の強力な理論的支柱となった
名君として行った藩政改革
光圀は藩主として、領民の生活を豊かにするための様々な改革を行った。その根底には、若き日に学んだ「民を愛する」という思想と、物事を合理的・実践的に捉える姿勢があった。
代表的な功績の一つが、1663年に完成させた「笠原水道」だ
社会の慣習にもメスを入れた。藩主となった1661年、彼は家臣が主君の死を追って殉死する「殉死」を厳しく禁じた
また、宗教制度の改革にも着手した。領内の寺社を調査し、不正や堕落が見られた寺院を約1,000カ寺も整理・廃止する一方で、由緒正しい寺社は手厚く保護した
日本で初めてラーメンやチーズを食べた?旺盛な好奇心
光圀の功績は政治や学問だけではない。彼は未知の文化に対しても非常に強い好奇心を持っていた。その象徴が、日本で初めてラーメンを食べた人物という逸話だ
きっかけは、彼が師として招いた中国の儒学者・朱舜水(しゅしゅんすい)との交流だった
彼の食への探求はそれだけにとどまらず、朱舜水から牛乳を加工して作る「白牛酪(はくぎゅうらく)」というチーズのような乳製品や、餃子の作り方も教わったと言われている
光圀にとって、これらの食体験は単なる珍しいものを味わう以上の意味を持っていた。それは、尊敬する師である朱舜水の文化そのものを受け入れ、学ぶという行為だった。食を通じて異文化への理解を深め、知識を実践する。これは、彼の学問に対する姿勢、すなわち書物の上だけでなく、実体験を重んじる「実学」の精神そのものを表している。
全国の優れた学者や文化人との交流
光圀の周りには、常に優れた学者や文化人が集まっていた。『大日本史』編纂のために設立した彰考館には、彼の学識を慕って全国から才能ある人々が集結した
その中でも最も重要な人物が、明(当時の中国)の滅亡にともない日本へ亡命してきた儒学者・朱舜水だ
また、『水戸黄門』の物語でおなじみの「助さん」と「格さん」にも、実在のモデルがいた。助さんのモデルは佐々宗淳(さっさむねきよ)、格さんのモデルは安積澹泊(あさかたんぱく)という、いずれも彰考館の中心的な学者だった
この事実は、歴史上の人物が伝説の中でいかに姿を変えるかをよく示している。実際の光圀とその家臣たちの功績は、地道な学問的探求の積み重ねにあった。しかし、物語はそれを、より大衆に受け入れられやすい、勧善懲悪の冒険活劇へと作り変えた。歴史上の光圀と、伝説の「水戸黄門さま」との間には、こうした大きな隔たりが存在するのである。
独特の死生観と「瑞龍山」の寿陵
晩年の光圀は、自らの死と向き合い、生前に自身の墓「瑞龍山寿陵(ずいりゅうさんじゅりょう)」を造営した。生きているうちに建てる墓を「寿陵」といい、これは彼の独特な死生観の表れだった。
墓の様式は、仏教式ではなく、彼が生涯を通じて探求した儒教の教えに厳格に基づいている
さらに彼は、自らの葬儀において仏教的な儀式を一切行わないよう、そして墓所には僧侶を立ち入らせないよう遺言した
瑞龍山の墓は、光圀にとって単なる終の棲家ではなかった。それは、彼の人生を懸けた知的探求の最終的な結論であり、自らの哲学を形にした記念碑だった。当時の主流であった仏教の死生観に頼るのではなく、自らが信じる儒教の倫理観と理性の力によって、人生を締めくくろうとしたのだ。この墓は、彼の生き様そのものを象徴する、最後の、そして最も雄弁なメッセージと言えるだろう。
まとめ:徳川光圀とは?
- 徳川光圀は徳川家康の孫で、水戸藩の第2代藩主だった。
- 「水戸黄門」の「黄門」とは、彼が就いていた権中納言という役職の中国風の呼び名に由来する。
- 若い頃は「かぶき者」として知られる破天荒な人物だったが、18歳で『史記』「伯夷伝」を読んで感銘を受け、学問に目覚めた。
- 兄を差し置いて跡継ぎになったことを生涯気にかけ、兄の息子を養子に迎えて水戸藩を継がせた。
- 生涯をかけた事業として、日本の歴史書『大日本史』の編纂を始め、これが後の「水戸学」の基礎となった。
- 『大日本史』が掲げた天皇を尊ぶ思想は、約200年後に徳川幕府を倒す運動の理論的支柱の一つとなった。
- 藩主として、上水道「笠原水道」の建設や、家臣の殉死の禁止など、合理的で民を思う改革を行った。
- 好奇心旺盛で、日本で初めてラーメンやチーズ、餃子を食べた人物の一人と言われている。
- 物語の「助さん・格さん」のモデルは、武士ではなく、歴史資料収集のために全国を旅した一流の学者だった。
- 自らの墓を生前に儒教の様式で作り、仏教的な儀式を拒否するなど、独自の死生観を貫いた。