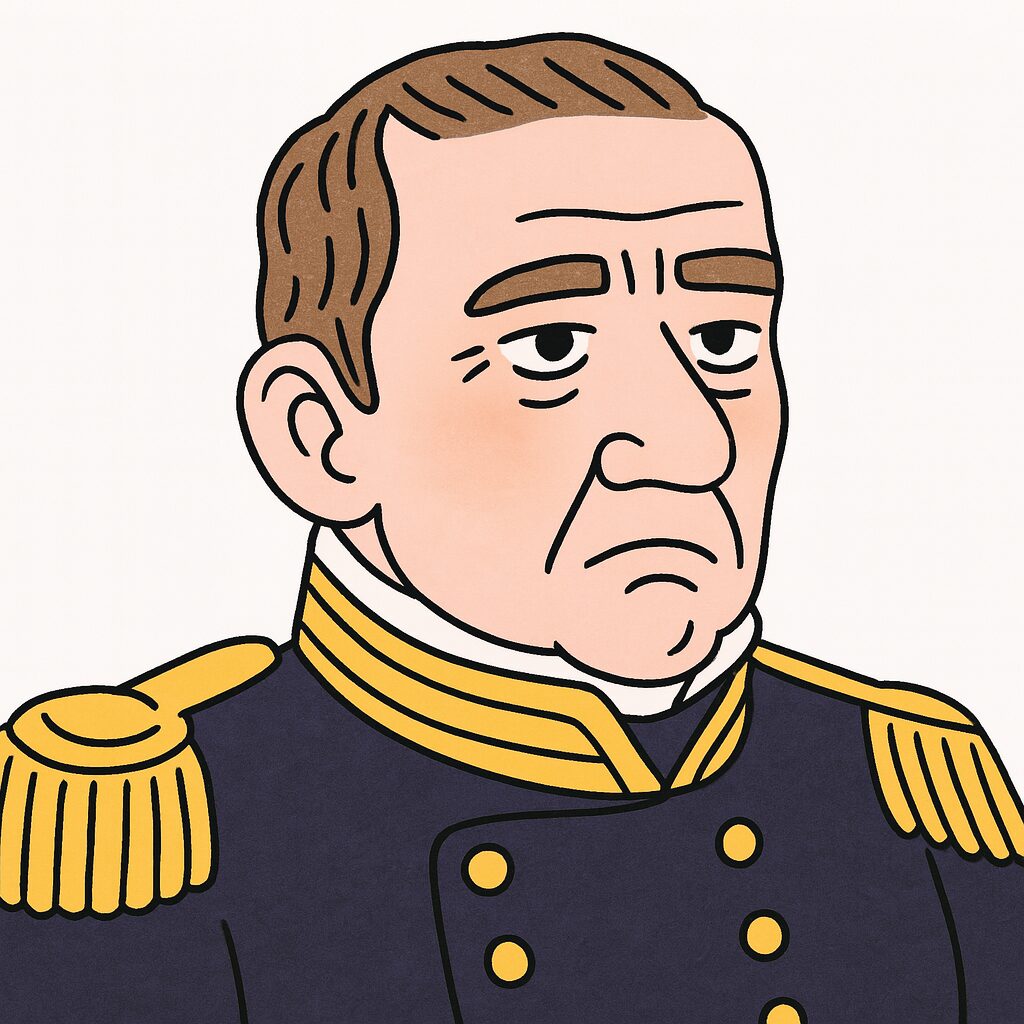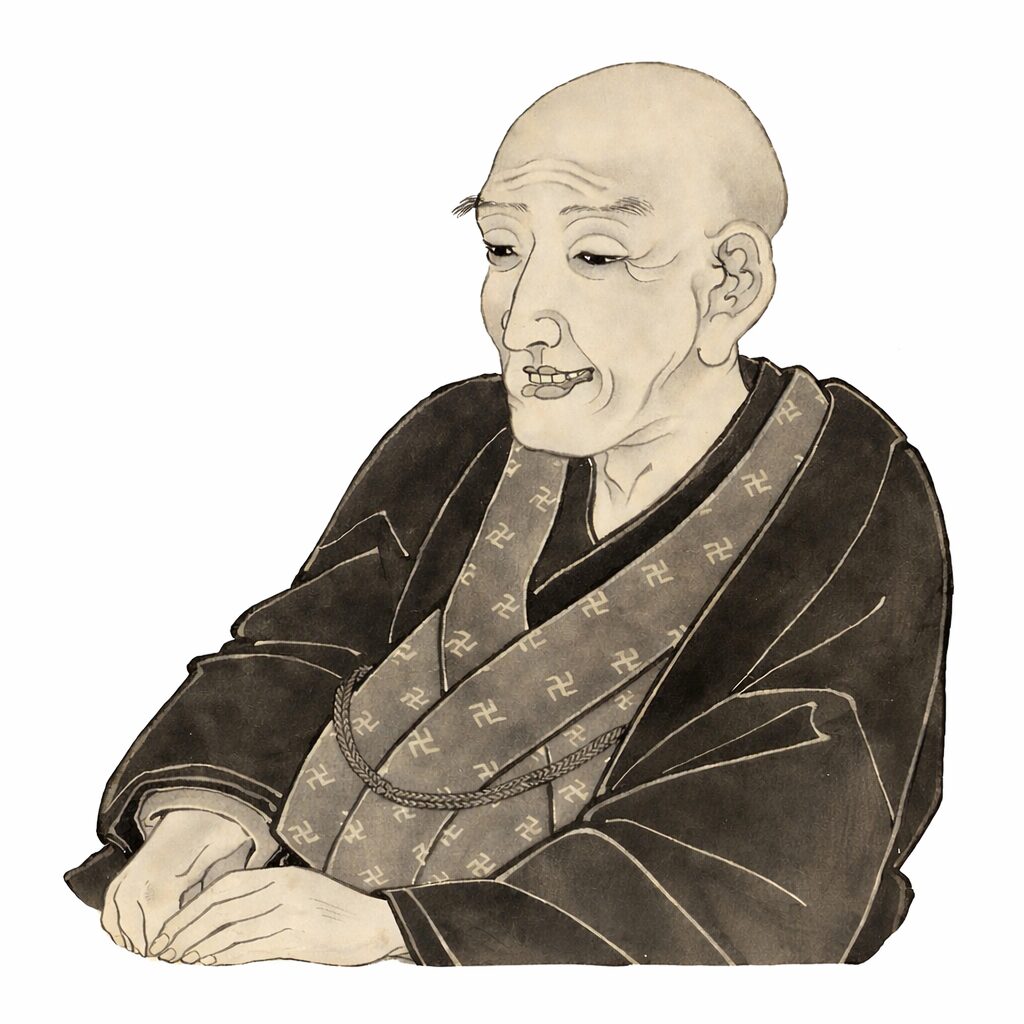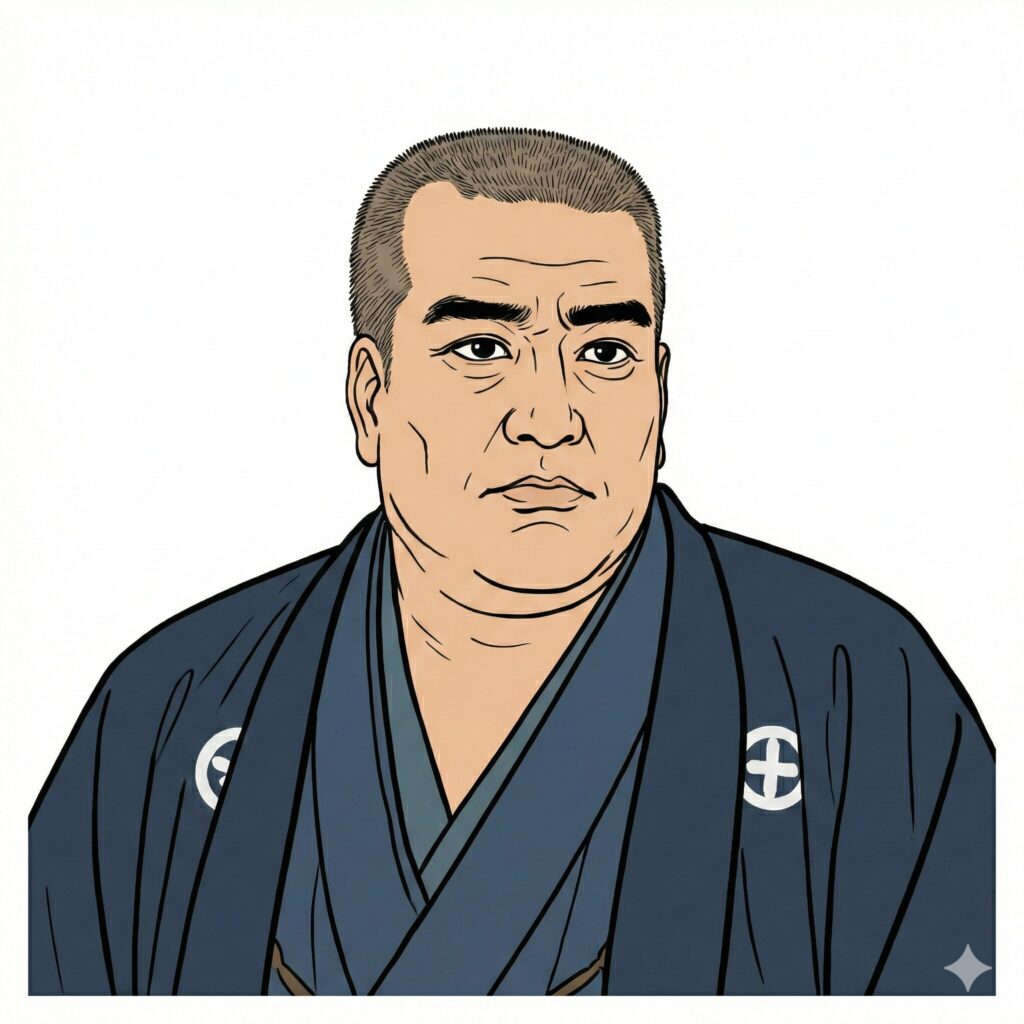「徳川家康の家系図における側室」と聞くと、なんだか強い女性たちのイメージや、あっちもこっちもキラめくお殿様の華麗なる女性遍歴を連想してしまうかもしれない。だが実際は、「戦国の世」で自らの一族や領土を守るべく、親族関係の構築や同盟強化のために重要な役割を担った女性たちでもあるのだ。
今回の記事では、徳川家康とその側室の関係を歴史的背景や家系図の観点から丁寧に解説していく。「徳川家康の家系図における側室」がなぜ注目されるのか、その魅力をしっかり把握することで、あなたの戦国史観がさらに奥深くなること間違いなしである。
本記事は、徳川家康の家系図における側室たちの生い立ちや役割、子どもたちへの影響までを網羅的に紹介する。読めば読むほど「おや、こんなエピソードもあったのか!」と驚かされるはずだ。ぜひ最後まで読んで、戦国屈指の“モテ男”徳川家康の裏側をのぞいていただきたい。
1. 「徳川家康の家系図における側室」が重要な理由
「徳川家康の家系図における側室」とは、家康にとって単なる愛人や女性的な楽しみだけではなかった。いやいや、確かに家康は大変な女性好きとしても有名だが、そこには戦国を生き抜く強かな“政治的意図”もあったのである。
例えば、当時は婚姻関係を通じて大名同士が同盟を組むのが当たり前。側室を迎えることで血縁関係を増やし、敵対勢力を味方につけたり、離反しないよう安定を図ったりすることが常套手段だった。
結果、徳川家康は2人の正室(築山殿、朝日姫)のほか、10人を優に超える側室を抱え、多くの子女をもうけている。これらの子女が全国各藩へ縁組され、“徳川”という大家が天下に広がっていったわけだ。
つまり「徳川家康の家系図における側室」を学ぶことは、江戸幕府成立前後の政治・社会的背景を理解するうえで不可欠。戦国最強とも言われる家康の権力基盤がどう築かれたか、その一端を見つけるカギでもあるのだ。
2. 徳川家康の正室と側室の人数と目的
さて、そもそも徳川家康にはどれくらいの正室と側室がいたのか。よく言われるのが正室が2人、側室が約20人という数字だ。もちろん、時代が時代だけに「この人、実はただの愛妾だった」「いや、正室級の扱いだったのでは」と史料がはっきりしないケースも多い。
とりあえず、歴史ファンや研究者のあいだでは「2人の正室+約20人の側室」という説が現在有力。しかも家康の場合は、最晩年の66歳で五女が誕生するなど、非常に“精力”が衰えなかったことでも知られている。
家康が側室をこれだけ抱えた目的は主に2つ。
- 同盟・縁組による政治的安定
- 家督を継ぐ子女の確保
戦国時代は早世のリスクも高かった。たくさんの後継者候補を確保しておかないと、家が途絶えてしまう可能性もある。家康に限らず、多くの戦国大名が複数の正室や側室を抱えていた背景には、そうした“世知辛い”事情が存在したわけだ。
もちろん「家康公の浮気グセ」という話で盛り上がるのもアリだが、一方で生存競争の激しい時代を乗り越えるための“打算”と“戦略”がそこにあったことは覚えておきたい。
3. 「徳川家康の家系図における側室」総一覧
ここでは、「徳川家康の家系図における側室」としてよく挙げられる女性たちをざっと紹介する。名前の表記や呼び名が複数あったり、同一人物かどうか判別が難しいケースもあるが、大まかなラインナップは下記のとおりである。
| 正室 | 側室 |
|---|---|
| 築山殿 | 西郡の方(蓮葉院)於万の方(小督の局、長勝院)於愛の方(西郷の局、宝台院)於都摩の方(下山殿、長慶院)於茶阿の方(朝覚院)於亀の方(相応院)間宮氏女於万の方(蔭山殿、養珠院)於梶(勝)の方(英勝院)阿茶の局(雲光院)阿牟須の方(正栄院)於仙の方(泰栄院)於梅の方(蓮華院)於竹の方(良雲院)於六の方(養儼院)於夏の方(清雲院) |
| 朝日姫(南明院) |
この他にも名前が挙がる女性はいるが、文献によっては「同一人物を別名で呼んでいるだけ」といった混同が起こりがちである。以下では、特に有名もしくは史料で比較的情報がはっきりしている側室について、時代背景やエピソードを交えながら解説していく。
4. 主要側室の人生とエピソード
ここから先は、比較的よく知られる・あるいはドラマや書籍でも扱われることが多い側室を中心に、生涯やエピソードを深堀りしてみよう。読むほどに「えっ、こんなドラマチックな人生!?」となるはずだ。
西郡の方(蓮葉院)
通称:西郡局(にしのこおりのつぼね)
出自は柏原城の加藤氏といわれ、鵜殿長忠の養子となった後、家康に見初められて側室となった。1565年(永禄8年)には徳川家康の次女「督姫」を出産。
西郡の方は政治面でも貢献度が高い。督姫が北条氏直に嫁ぐことで、徳川家と北条家の緊張関係が緩和され、結果的に和睦が成立した。
その後も家康が江戸城に入城するとともに行動を共にし、菩提寺の復興など信仰面でも活動したとされる。1606年(慶長11年)に伏見城で急死したというから、なかなか波瀾万丈な人生だ。
於万の方(小督の局、長勝院)
「於万の方」は、後の結城秀康(家康の次男)を産んだ女性として知られる。もともとは築山殿の奥女中だったが、家康の目に止まり、最終的に側室へ。
当時、正室である築山殿の嫉妬もすさまじく、於万の方はかなりの迫害を受けたらしい。寒空の下で身ぐるみ剥がされ、木にくくりつけられた…なんて凄絶な伝説も残っている。こうしたエピソードは戦国時代特有の女性同士の激しい権力闘争を感じさせる。
結城秀康は城の外で産まれたため、当初は家康の子どもとして認められなかったが、後に越前国(現在の福井県)を与えられて正式な大名に。於万の方も秀康に従って越前へ移り、1619年(元和5年)に72歳で亡くなった。
於愛の方(西郷の局、宝台院)
家康の数多い側室の中でも、特に最愛の側室と言われるのが「於愛の方」だ。その魅力は“美貌”だけでなく“性格が温和で誠実”だったことにある。
1579年(天正7年)には後の2代将軍・徳川秀忠を出産し、翌年には松平忠吉を産んでいる。正室並みの扱いを受けていた節もあり、「西郷殿」という“殿”の敬称で呼ばれる記録も残っている。
しかし1589年(天正17年)に28歳(もしくは30歳)で早世。家康は相当にショックを受けたと言われるが、天下取り真っ只中ということもあり、その悲しみに浸る暇もなかったのかもしれない。
於都摩の方(下山殿、長慶院)
1564年(永禄7年)、甲斐武田氏の家臣・秋山虎康の長女として生まれ、その後穴山信君の養女となった女性である。武田家滅亡後に家康の側室となり、1583年(天正11年)に五男・福松丸(後の武田信吉)を出産する。
しかし1591年(天正19年)、わずか24歳で亡くなった。そのため「家康の寵愛を一身に受けた期間は決して長くなかった」とも推測されるが、その短さゆえに神秘的なイメージを持つファンも多い。
於茶阿の方(朝覚院)
1550年(天文19年)頃に生まれたとされ、もともとは遠江国金谷村の鋳物師の後妻だったが、夫を闇討ちした代官を訴え出るために家康のもとへ直訴。その正義感の強さと美貌を家康に気に入られ、浜松城へ引き入れられたという逸話がある。
最初は身分が低かったものの、次第に信頼を得ていき、1589年(天正17年)に於愛の方が亡くなると、その遺児である秀忠と忠吉を養育する役目を担う。さらに1592年(天正20年)には六男・松平忠輝、1593年(文禄2年)には七男・松平松千代を出産。
大坂の陣でも交渉役を務めたとされ、1621年(元和7年)に72歳で病死した。現代の大河ドラマなどで描かれる人となりは「芯の強い女性」だが、実際もその通りであった可能性が高い。
於亀の方(相応院)
石清水八幡宮の社務・志水宗清の娘として生まれ、1594年(文禄3年)に22歳で家康の側室となる。翌1595年(文禄4年)には「仙千代」を産むが、この子は1600年(慶長5年)に夭折した。
仙千代を失った悲しみから寺を建立したり(名古屋市の高岳院)、供養を続けていた於亀の方だが、同年1600年に九男を出産。これが尾張徳川家の祖・徳川義直である。以降、於亀の方は義直とともに名古屋城で暮らし、1642年(寛永19年)に70歳で亡くなった。
間宮氏女(まみやしむすめ)
後北条氏の旧臣・間宮康俊の娘とされ、1595年(文禄4年)に四女・松姫を産んだ。しかし1598年(慶長3年)に松姫は4歳で夭折。さらに家康の死後(1616年の翌年)、1617年(元和3年)にこの世を去ったと伝わる。
ほとんど史料が残っておらず、謎の多い側室のひとりだが、娘が早世してしまった不運もあり、家康の家系図では影が薄めかもしれない。
於万の方(蔭山殿、養珠院)
こちらは先述の「於万の方(小督の局)」とは別人物なので注意が必要。伊豆国出身とされ、1593年(文禄2年)頃、16~17歳で家康の側室となった。
1602年(慶長7年)に十男の徳川頼宣(紀州藩初代藩主)、翌1603年(慶長8年)には十一男の徳川頼房(水戸藩初代藩主)を産んでいる。いわゆる“紀州家”と“水戸家”の母として非常に重要な人物。
こうして徳川家が尾張・紀州・水戸の御三家を形成する土台ともなったわけで、家康の家系図における影響力は相当に大きい。
於梶(勝)の方(英勝院)
家康最後の子どもとされる「市姫」の母として知られる。娘の市姫は4歳で早世してしまったが、その後、家康の心配りにより於梶の方は結城康秀の次男・松平忠昌や池田輝政の娘・振姫の養母になるなど、家中で大切に扱われた。
家康の死後は出家し「英勝院」を名乗り、1642年(寛永19年)に65歳で没した。
阿茶の局(雲光院)
武田家の血を引く神尾忠重に嫁いだが、夫と死別後の1579年(天正7年)に家康のもとへ。実子を産むことはなかったが、家康の信頼は厚かった。
特に家政管理や秀忠・忠吉の養育など、“内政”面で力を発揮した。家康の死後は江戸竹橋の屋敷で悠々自適の生活を送り、1637年(寛永14年)に83歳で他界。なお「阿茶局」という呼び名で、大河ドラマなどでも登場することがある。
阿牟須の方(正栄院)
出自ははっきりしないが、1584年(天正12年)に夫が戦死し、家康の側室になったとされる。於茶阿の方、阿茶の局と並んで家康のお気に入り三人衆として名を馳せた。
しかし1592年(文禄元年)に家康が名護屋城(肥前国)へ向かった際に同行し、出産時の難産によって母子ともに亡くなったという。激動の戦国を象徴するかのような儚い生涯である。
於仙の方(泰栄院)
武田家旧臣・宮崎泰景の娘とされ、家康に仕え始めた正確な時期は不明だが天正年間(1573~1592年)と推測される。子どもは産んでおらず、1619年(元和5年)に駿府で他界。資料が少ないため、その詳細はベールに包まれている。
於梅の方(蓮華院)
1586年(天正14年)生まれ。父は豊臣家臣の青木一矩とされる。1600年(慶長5年)、15歳で家康に仕えるようになり、ほどなくして家康の側室となった。
のちに家康の重臣・本多正信の息子、本多正純の継室となるが、本多家改易後に出家。伊勢の梅香寺などに隠棲し、1647年(正保4年)に62歳で亡くなった。
於竹の方(良雲院)
詳しい出自は不明で、武田信玄の娘説まであるほど謎が多い。家康の三女・振姫の生母とも、あるいは別の側室との混同かもしれないなど、史料の確証が得られないケースの代表例である。
1637年(寛永14年)に亡くなったとされるが、それ以外の情報がはっきりしないため、研究者泣かせの側室の一人でもある。
於六の方(養儼院)
今川家臣・黒田直陣を父にもち、1597年(慶長2年)生まれ。於梶の方の部屋子をしていたところ、家康に見初められたという。
1625年(寛永2年)に日光東照宮へ家康の法事に向かう途上で急死。享年29という若さであった。
於夏の方(清雲院)
1581年(天正9年)、北畠家旧臣・長谷川藤直の娘として生まれ、17歳で家康の側室に。大坂冬の陣にも家康に随行していた。
1616年(元和2年)の家康死後は出家。4代将軍・家綱の時代に至る1660年(万治3年)まで存命し、享年80。存命する家康の側室としては最後の一人であったため、江戸幕府からも特に手厚い待遇を受けたという。
ここまで生き抜いた“戦国の女傑”という感じである。
5. 徳川家康の家系図における側室たちが築いた“絆”と同盟戦略
ここまで見てきたように、徳川家康の側室たちは一人ひとりがただ“美人であった”だけではなく、各地の有力武家の血筋や武田・北条などの旧敵家臣との縁結びの要となり、家康自身の政治基盤を強固にする役割を担っていた。
特に、甲斐武田や駿河今川、遠江や伊豆など、家康の領国や隣国の武将との“つながり”を作る手段として側室が活躍していることが分かる。
戦国時代は「結婚は政治」である。そこにドラマやロマンを感じるのもまた歴史探究の醍醐味だが、当人たちからするとまさに生存競争そのもの。家康の側室たちが駿府や江戸に入った後も、実家の旧臣との連絡役を務めたり、幼い子女を通じて有力大名との関係維持に貢献したことだろう。
こうした結び付きがあったからこそ、家康は勢力を拡大し、最終的に江戸幕府を開くに至ったとも言える。まさに大奥の原型のような“女性のネットワーク”が家康を支えたのだ。
6. 徳川家康の子女と将軍家の繁栄
徳川家康は合計で男児11人、女児5人(さらに諸説あり)をもうけており、そのうち何人かは戦国の世で夭折したものの、少なくとも8人以上の子が成長し各地へ嫁いだり、藩主になったりしている。
- 徳川秀忠(母:於愛の方)は江戸幕府2代将軍
- 結城秀康(母:於万の方)は越前藩主
- 徳川義直(母:於亀の方)は尾張徳川家祖
- 徳川頼宣(母:於万の方[蔭山殿])は紀州徳川家祖
- 徳川頼房(母:於万の方[蔭山殿])は水戸徳川家祖
つまり、御三家(尾張・紀州・水戸)を含む強力な支流ができあがり、江戸幕府を300年弱も支える礎となったわけである。
そして、そこには正室・側室を問わず、多くの女性たちの血筋と“働き”がしっかりと刻まれている。家康一人の力だけでは決して成し得なかった“徳川繁栄”の裏には、こうした数多の側室たちの存在があったのだ。
7. まとめ:史料をたどり、家康像を再発見しよう
「徳川家康の家系図における側室」と聞くと、「へぇ、愛人がいっぱいいたんだね」程度に思われがちかもしれない。しかし、彼女たちの存在意義は、戦国の生存競争と政略結婚が渦巻く時代においては極めて重大であった。
現代の感覚ではなかなか理解しづらいが、当時は領地拡大や家名存続のために複数の正室・側室を持つのが普通。誰を側室として迎えるか、誰との間に子をもうけ、どこに嫁がせるか――そうした一つひとつの判断が、家康の天下取りを左右していたといっても過言ではない。
もし、あなたが「家康の人物像」にさらに興味を持ったのなら、下記のような信頼性の高い史料も参考にしてみてほしい。ネットや図書館、博物館で調べると思わぬ新発見があるはずだ。
- 『家忠日記』
- 『徳川実紀』
- 国立公文書館・江戸東京博物館などの史料
そして、彼女たちが残したエピソードの中には「いや、それドラマの脚本でも盛り込みすぎでは!?」と思うような突飛な話もある。しかし、そこにはやはり当時ならではの“リアル”が確かに刻まれているのだ。
気になる方はぜひ、さらに深く史料をあさってみてほしい。家康がどんな想いで側室を迎えていたのか。女性たちはどのように戦国を生きたのか。新たな気づきが得られたとき、あなたの中の戦国史がますます楽しく豊かになるに違いない。