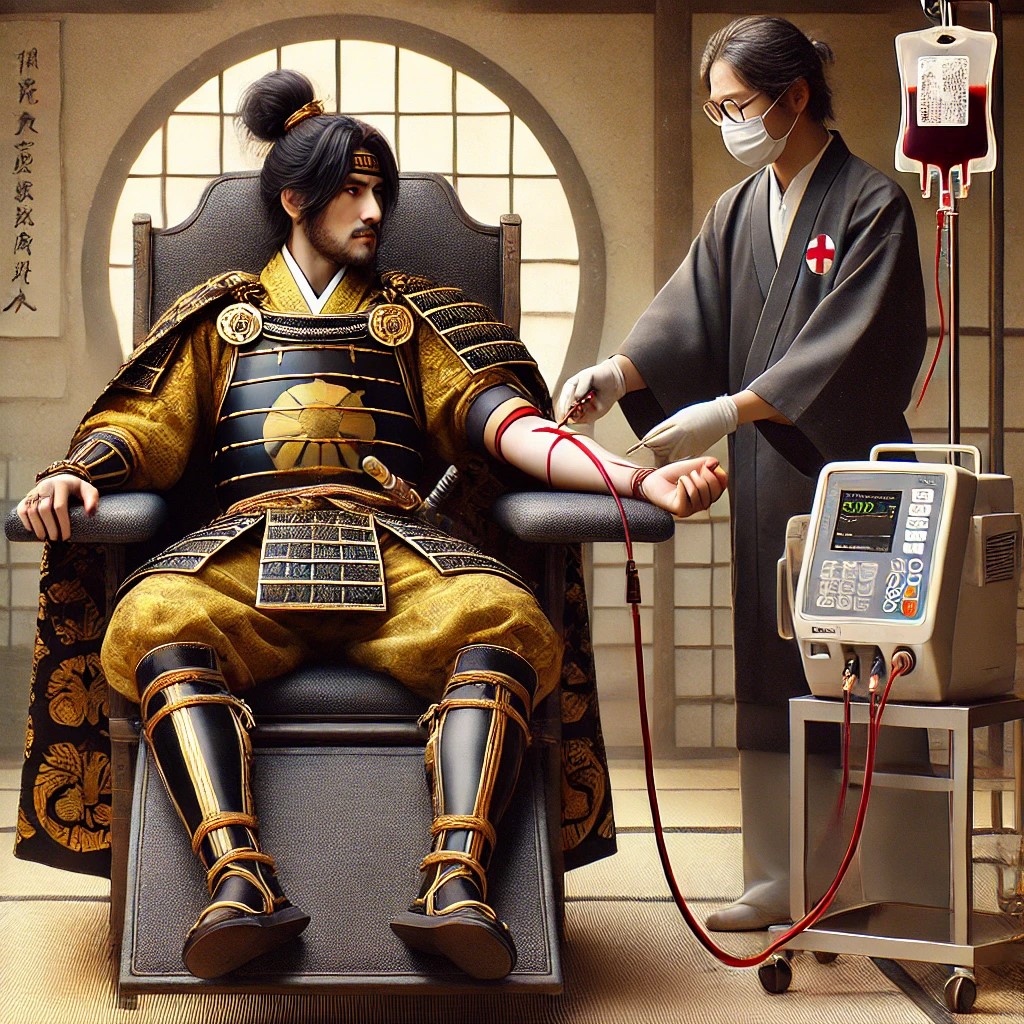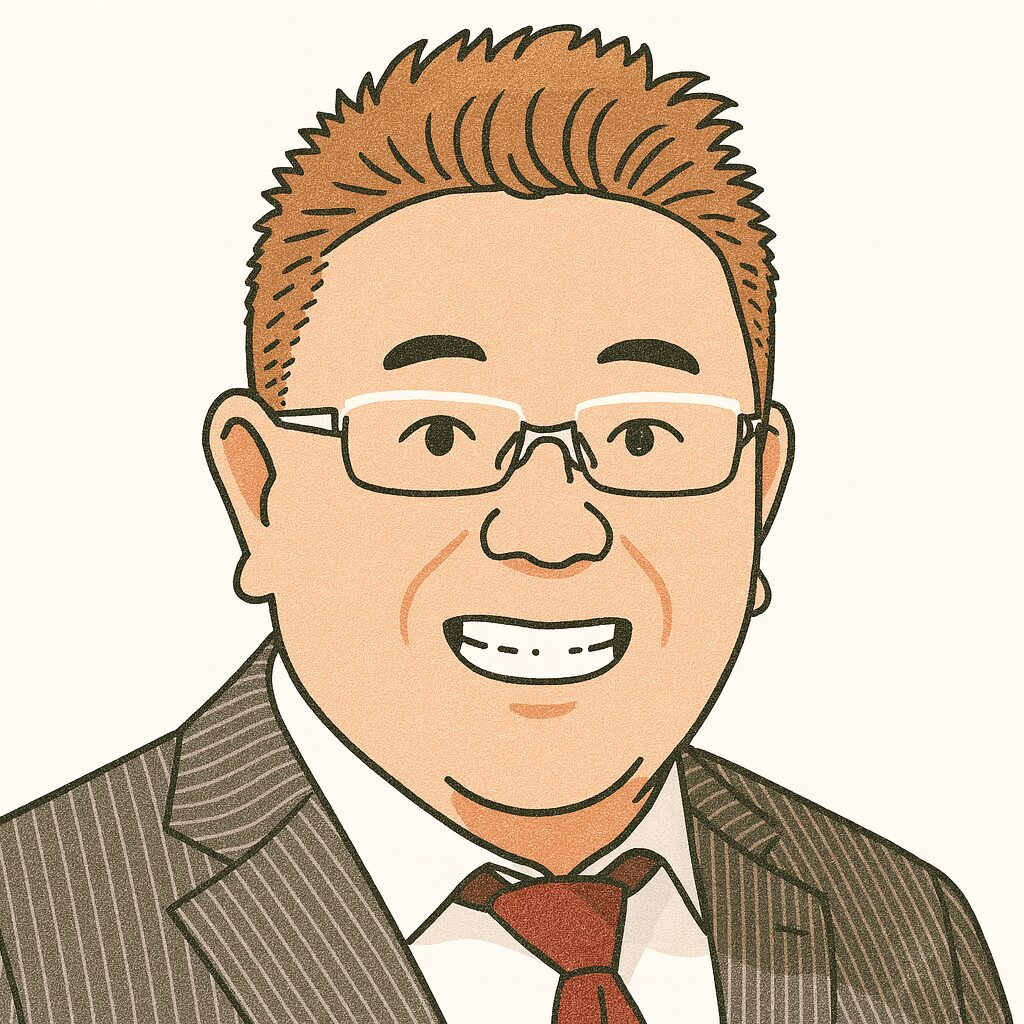
伊達政宗という名前を聞いて、多くの人が思い浮かべるのは、黒い眼帯をつけた勇ましい戦国武将の姿だろう。奥州の覇者として知られ、仙台藩62万石の礎を築いた「独眼竜政宗」。その活躍は、今もなお多くの物語やドラマで語り継がれている。しかし、そんな政宗の死後、彼が築いた伊達家がどうなったのか、その子孫たちがどのような歴史を歩んだのかについては、意外と知られていないかもしれない。実は、政宗の血筋は途絶えることなく、400年以上経った現代まで脈々と受け継がれている。しかも、その子孫は仙台だけでなく、遠く四国の地にも広がり、それぞれの場所で歴史を刻んできた。本家を継いだ者、新たな地で大名となった者、そして現代社会で活躍する意外な有名人まで。この記事では、伊達政宗の子孫たちがたどった壮大な物語を、分かりやすく解説していく。0
伊達政宗の子孫は「仙台」と「宇和島」の2つの家系に分かれた
政宗はどんなお父さんだった?娘たちへの手紙
戦国武将としての勇ましいイメージとは裏腹に、伊達政宗は家族を深く愛する父親としての一面を持っていた。彼には正室や側室との間に10男4女、合計14人の子どもがいたことが記録されている。特に、42歳の時に生まれた次女の牟宇姫(むうひめ)のことは大変可愛がったようだ。牟宇姫が嫁いだ後、政宗が彼女に送った手紙は、なんと329通も残されている。その手紙は、娘が読みやすいようにと、わざわざ仮名文字で書かれていた。ある手紙では、成人した牟宇姫と初めて親子三人でお酒を飲んだ喜びを「お父さんも思いのほか酔ってしまい、詳しく書けないほどです」と、楽しげに綴っている。
一方で、正室・愛姫(めごひめ)との間に15年目にしてようやく生まれた待望の第一子、五郎八姫(いろはひめ)の人生は波乱に満ちていた。彼女は徳川家康の息子・松平忠輝と政略結婚したが、夫が幕府から罰せられたことで離縁を余儀なくされ、仙台へ戻った。その後、五郎八姫は再婚することなく生涯を終えたが、その背景にはキリスト教の教えがあったのではないかと考えられている。政宗は、娘たちを政治の道具としてだけでなく、一人の人間として深く気にかけていた。彼が娘たちに送った数々の手紙は、厳しい時代の中で家族の絆を保ち続けようとした、戦略家でありながら愛情深い父親の姿を今に伝えている。
跡継ぎ問題!長男・秀宗と次男・忠宗
伊達家の未来を左右する大きな出来事が、政宗の跡継ぎ問題だった。政宗には、側室の飯坂氏(新造の方)との間に生まれた長男・秀宗と、正室・愛姫との間に生まれた次男・忠宗がいた。通常であれば長男が家を継ぐのが当たり前の時代だったが、伊達家の家督は次男の忠宗が継ぐことになった。
この決断の裏には、当時の日本の大きな政治状況の変化があった。長男の秀宗は幼い頃、天下人であった豊臣秀吉のもとへ人質として送られ、そこで育った。一方、豊臣氏が滅び徳川家康が天下を統一すると、政宗は新しい時代を生き抜くために、徳川幕府との関係を強化する必要があった。そこで政宗は、次男の忠宗を徳川家と深く結びつける。忠宗は二代将軍・徳川秀忠から名前の一字をもらい、家康の孫娘と結婚した。こうして、徳川幕府から正式な後継者として認められた忠宗が、仙台藩を継ぐことになったのだ。これは、単なる家族の問題ではなく、伊達家が徳川の世で生き残るための、政宗の計算し尽くされた政治的な決断だったのである。
仙台藩を継いだ伊達政宗の子孫「仙台伊達家」
伊達家の本家(宗家)と仙台藩62万石を継いだのは、次男の伊達忠宗だ。彼は伊達家18代当主、そして仙台藩の2代藩主となった。派手好きで「伊達者」の語源にもなった父・政宗とは対照的に、忠宗は真面目で堅実な性格だったと言われている。その政治手腕は高く評価され、「守成の名君」、つまり創業者(父・政宗)が築いたものをしっかりと守り、発展させた優れた君主と称された。
忠宗は、藩の法律を整備し、正確な土地調査(検地)を行って税の仕組みを安定させるなど、仙台藩の基礎を固めるための重要な政策を次々と実行した。また、仙台東照宮などの寺社を建立し、文化の発展にも力を注いだ。父・政宗がカリスマ的なリーダーシップで仙台藩という巨大な組織を「創業」したとすれば、忠宗はその組織が長く安定して続くための「経営システム」を構築したと言える。この父と子の見事な連携があったからこそ、仙台藩は江戸時代を通じて繁栄を続けることができたのだ。仙台伊達家は、その後も時には分家から養子を迎えながら血筋をつなぎ、幕末まで仙台を治め続けた。
もう一つの伊達家、愛媛の「宇和島伊達家」
跡継ぎになれなかった長男・秀宗は、どうなったのだろうか。政宗は秀宗のために、幕府に働きかけ、四国の伊予宇和島(現在の愛媛県宇和島市)に10万石の新しい領地を与えてもらった。こうして、仙台の伊達家とは別に、もう一つの「宇和島伊達家」が誕生した。これは仙台藩の支店(支藩)という位置づけではなく、幕府から直接認められた独立した大名家であり、「東の仙台伊達、西の宇和島伊達」として並び立つことを期待された。
しかし、宇和島藩の船出は困難を極めた。藩を始めるための資金は父・政宗からの借金であり、大きな負担となった。さらに、秀宗と共に宇和島へ行った家臣団は、政宗が選んだ者たちだったため、彼らの忠誠心は宇和島の秀宗よりも仙台の政宗に向いていた。このため、藩の運営をめぐって家臣同士が対立し、ついには秀宗の家臣が別の家臣を暗殺するという「和霊騒動」と呼ばれる事件が起きてしまう。この事件に激怒した政宗は、秀宗を勘当し、幕府に領地を取り上げるよう願い出るほどだった。父の大きな影響力の下で、自らの国を治めようとする秀宗の苦悩がうかがえる。
本家と分家、二つの伊達家の関係
仙台の「本家」と宇和島の「分家」。この二つの伊達家の関係は、複雑なものだった。宇和島藩は幕府からは独立した大名とされていたが、仙台藩は宇和島藩を格下の支藩と見なすことが多かった。特に藩の設立当初、秀宗が政宗から借りた資金を返すため、18年間にわたって宇和島藩の領地の一部を仙台藩が管理するという取り決めがあり、宇和島藩は経済的に仙台藩に従属する形となっていた。
時が経つにつれて、宇和島藩は仙台藩からの独立性を高めようと努力した。しかし、両家の間にはライバル意識と同時に、同じ「伊達」の名を背負う者としての強い絆も存在した。その証拠に、後に両家で跡継ぎが途絶えそうになった際には、お互いの家から養子を迎え入れている。特に宇和島伊達家は、仙台藩主・忠宗の子孫を養子に迎えたことで血筋を繋いだため、現代の宇和島伊達家の当主は、血筋をたどると仙台伊達家の忠宗に行き着く。明治時代には、宇和島伊達家が政治的な功績で本家の仙台伊達家よりも高い爵位を与えられるという逆転現象も起きた。対立と協力を繰り返しながら、二つの伊達家はそれぞれの歴史を歩んでいったのだ。
現代に続く伊達政宗の子孫たち!意外な有名人も
仙台伊達家18代当主・伊達泰宗さんとは?
伊達政宗から続く仙台伊達家の本家を、現代に受け継いでいるのが第18代当主の伊達泰宗(だて やすむね)さんだ。泰宗さんは1959年に東京で生まれた。明治維新後、伊達家の当主は東京で暮らすのが通例だったが、泰宗さんは明治以降で初めて仙台に移り住んだ当主である。
その決意のきっかけは、15歳の時に立ち会った政宗公のお墓の発掘調査だった。焼け跡で初代藩主の遺骨と対面した泰宗さんは、「成人したら必ず仙台に戻り、近くでお守りさせていただきます」と心に誓ったという。その誓いの通り、泰宗さんは学芸員の資格を取得し、仙台市博物館や政宗公が眠る瑞鳳殿の資料館に勤務した。現在は瑞鳳殿の名誉館長などを務め、伊達家の歴史や文化を後世に伝える活動に尽力している。1987年に大ヒットしたNHK大河ドラマ『独眼竜政宗』では、歴史監修を担当したことでも知られる。泰宗さんは、かつての領主としてではなく、歴史と文化の専門家として、祖先の遺産を守り続けるという新しい当主の姿を示している。
宇和島伊達家を継ぐ当主の今
一方、四国に渡った宇和島伊達家の血筋も現代に続いている。現在の当主は、第13代の伊達宗信(だて むねのぶ)さんだ。1971年に東京で生まれた宗信さんは、大学卒業後、大手小売企業の丸井に就職し、会社員として働いていた。
しかし2010年、父である12代当主が亡くなったことを機に、会社を退職。400年続く宇和島伊達家の当主としての責任を引き継ぐことを決意した。現在は、宇和島伊達家の文化財を保存する団体の理事長などを務め、東京と宇わ島を往復しながら、先祖から受け継いだ文化遺産を守る活動をしている。また、地域の活性化にも関心が高く、2016年に公開された宇和島が舞台の映画「海すずめ」は、宗信さんのアイデアがきっかけで制作された。現代的なビジネスの世界から、歴史と伝統を守る世界へ。宗信さんの経歴は、歴史的な家系に生まれた者が、現代においてどのようにその役割と向き合うかという一つの答えを示している。
お笑い芸人サンドウィッチマンの伊達みきおさんも子孫?
人気お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきおさん。彼もまた、伊達家の血を引く子孫の一人だ。ただし、伊達政宗の直接の子孫というわけではない。彼の家系をさかのぼると、「大條(おおえだ)氏」という伊達一族の分家にたどり着く。
この大條氏は、あの有名な「独眼竜政宗」(17代当主)の名前の由来にもなった、伊達家「中興の祖」と称される9代当主・伊達政宗の弟が興した家系だ。つまり、非常に由緒正しい伊達一族の一員なのである。大條氏は江戸時代、仙台藩の家臣として仕え、明治時代になってから「伊達」の姓に戻すことを許された。伊達みきおさんの存在は、伊達家という大きな一族が、藩主となった本家だけでなく、それを支えた多くの分家によって構成されていたことを教えてくれる。芸人になる際、父から「伊達の名を使うな」と言われたというエピソードは、分家であってもその名前に大きな誇りと重みを感じていたことの表れだろう。
明治時代の爵位、なぜ宇和島伊達家は「侯爵」?
江戸時代が終わり、明治時代になると、武士の世は終わりを告げた。新政府は、元大名などを「華族」とし、公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵という5つのランクの爵位を与えた。この時、伊達家の本家である仙台伊達家は「伯爵」に、分家である宇和島伊達家は、それより格上の「侯爵」に叙せられた。
なぜ、石高も歴史も上である本家より、分家の方が高い地位を与えられたのだろうか。その理由は、幕末の動乱期における両家の政治的な選択の違いにある。仙台藩は、戊辰戦争で旧幕府軍の中心となり、新政府軍と最後まで戦った「奥羽越列藩同盟」の盟主だった。つまり、新政府から見れば「敵」だったのだ。一方、宇和島藩8代藩主の伊達宗城(むねなり)は、「幕末の四賢侯」の一人と呼ばれる優れた人物で、早くから新政府側について活躍した。明治維新への貢献が評価された結果、宇和島伊達家は侯爵という高い爵位を与えられたのだ。これは、250年以上続いた家の序列が、時代の大きな変化点での行動によって一夜にして覆された、歴史の面白さを示す出来事である。
政宗公が眠る場所「瑞鳳殿」に行ってみよう
伊達政宗の歴史を感じるために、ぜひ訪れたい場所が仙台市にある「瑞鳳殿(ずいほうでん)」だ。ここは、政宗が自らの遺言によって眠る霊屋(おたまや)、つまりお墓である。1637年に完成した初代の瑞鳳殿は、桃山文化の粋を集めた豪華絢爛な建築で、「東北の日光」とも呼ばれ、国宝に指定されていた。
しかし、その美しい建物は1945年の仙台空襲で焼失してしまった。現在の瑞鳳殿は、1979年に焼失前と全く同じ姿で再建されたものである。敷地内には、2代藩主・忠宗の「感仙殿」、3代藩主・綱宗の「善応殿」もあり、伊達家三代の歴史に触れることができる。また、再建前の発掘調査で見つかった副葬品などを展示する資料館も見どころだ。ここでは、政宗の遺骨から身長が159.4cm、血液型がB型であったことなどが科学的に判明し、その頭蓋骨から復元されたリアルな顔も見ることができる。瑞鳳殿は、政宗の遺産が戦争という悲劇を乗り越え、仙台の人々の手によって大切に守り伝えられていることを示す象徴的な場所なのだ。
全国に広がる伊達の血筋とゆかりの地
伊達一族の歴史は、仙台や宇和島だけにとどまらない。そもそも伊達氏が発祥したのは、現在の福島県伊達市周辺であり、高子岡城跡など、その初期の歴史を物語る史跡が今も残っている。仙台藩の時代には、藩内の重要な地域を治めるために、政宗の息子たちが藩祖となった分家(一門)がいくつも作られた。例えば、四男・宗泰が初代の「岩出山伊達家」や、七男・宗高の「村田伊達家」などだ。これらの城下町には、今も伊達家ゆかりの史跡が点在している。
明治維新後、武士の時代が終わると、新たな挑戦を始めた者たちもいた。岩出山伊達家の当主・伊達邦直は、家臣たちを率いて北海道へ集団移住し、未開の地を開拓して当別町を築いた。この功績により、当別伊達家は男爵の位を授かっている。福島での誕生から、宮城での繁栄、愛媛での分立、そして北海道での再出発へ。伊達一族の足跡をたどることは、日本の歴史そのものを旅するような壮大な物語なのである。
- 伊達政宗には10男4女の子供がおり、その血筋は現代まで続いている。
- 政宗は特に娘たちを可愛がり、次女・牟宇姫には300通以上の手紙を送るなど、愛情深い父親としての一面があった。
- 跡継ぎは、長男・秀宗ではなく、徳川幕府との関係を重視して次男・忠宗が選ばれた。
- 忠宗が継いだ仙台伊達家は、藩の基礎を固め、江戸時代を通じて仙台を治めた本家となった。
- 秀宗が初代となった宇和島伊達家は、愛媛県に作られたもう一つの伊達家で、設立当初は多くの困難があった。
- 現代の仙台伊達家当主は伊達泰宗さんで、歴史家として祖先の遺産を守る活動をしている。
- 現代の宇和島伊達家当主は伊達宗信さんで、会社員から転身し、文化財の保存活動を行っている。
- お笑い芸人のサンドウィッチマン・伊達みきおさんは、伊達政宗の直接の子孫ではなく、分家である大條氏の末裔である。
- 明治時代、宇和島伊達家は幕末の功績で「侯爵」、仙台伊達家は戊辰戦争で新政府と戦ったため「伯爵」と、分家が本家より高い爵位を得た。
- 政宗が眠る瑞鳳殿は、仙台にある重要な史跡であり、伊達家の歴史と文化を体感できる場所である。