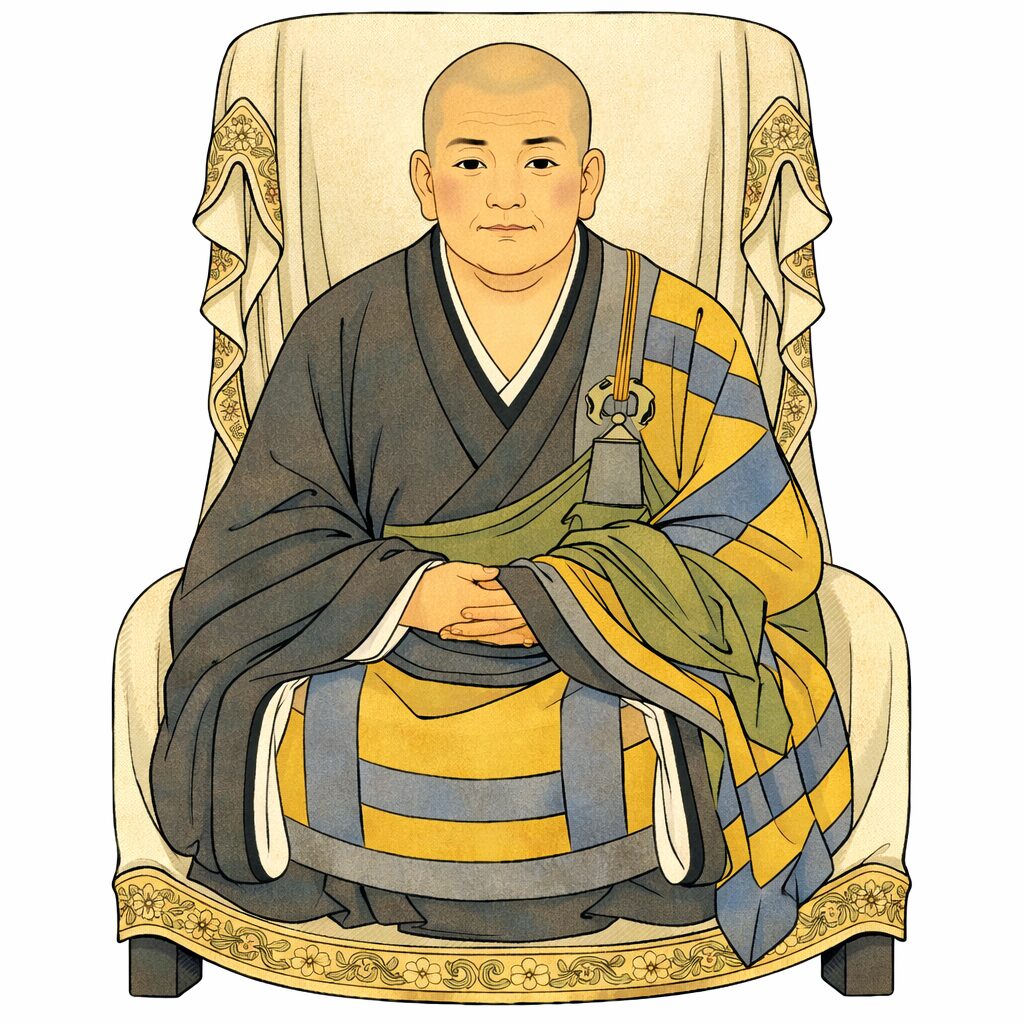鎌倉幕府の初代将軍・源頼朝の妻であり、夫の死後は「尼将軍」として幕府の政治を力強く動かした北条政子。日本の歴史上、最も有名な女性の一人である彼女だが、その最期の眠りの地がどこにあるかを知っているだろうか。
実は、鎌倉には「ここが北条政子の墓だ」と伝えられる場所が二つ存在する。一つは、夫・頼朝への想いが込められた「安養院」。もう一つは、愛する息子と共に眠るとされる「寿福寺」。なぜ二つも存在するのか?どちらが本当なのか?
この記事では、二つの伝承地を巡りながら、その歴史的な謎に迫っていく。アクセスや見どころ、関連史跡までを網羅した、鎌倉の歴史散策が何倍も面白くなる完全ガイドだ。
鎌倉・安養院にある北条政子の墓へのアクセスと歴史
まずはここ!北条政子の墓(安養院)の場所と拝観情報
北条政子の墓所として、まず名前が挙がるのが安養院だ。鎌倉駅から比較的歩きやすく、静かな住宅街の中にひっそりとたたずんでいる。訪れる前に、まずは基本的な情報を確認しておこう。
| 項目 | 詳細 |
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市大町3-1-22 |
| アクセス | ・JR鎌倉駅東口から徒歩約9分~15分 ・JR鎌倉駅東口バス乗り場から京急バス(名越方面行きなど)で約3~4分、「名越」または「大町四ツ角」バス停下車、徒歩約1~3分 |
| 拝観時間 | 8:00~16:30 (最終受付は15:45や16:00など資料により異なる) |
| 拝観料 | 200円 (一部資料では100円とあるが、200円がより一般的) |
| 拝観休止日 | 12月29日~31日。その他、7月8日、8月10日など寺の行事により休止の場合あり |
| 電話番号 | 0467-22-0806 |
複数の情報源で拝観料や時間に少し違いが見られるのは、情報が更新されるタイミングが異なるためだ。旅行の計画を立てる際は、最新の情報を確認するのが確実だ。
なぜ安養院に?源頼朝の菩提を弔うために建立した長楽寺が前身
では、なぜこの安養院が北条政子の墓所とされているのだろうか。その答えは、この寺の複雑な歴史の中にある。
現在の安養院は、もともと北条政子が建立した寺そのものではない。その始まりは、1225年(嘉禄元年)にさかのぼる。政子は、亡き夫・源頼朝の魂を弔うため、笹目ガ谷(ささめがやつ)という場所に「長楽寺」という壮大なお寺を建てた。この長楽寺があった場所は、現在の「鎌倉文学館」の敷地にあたり、今もその入口には「長楽寺跡」と記された石碑が立っている。
しかし、この長楽寺は1333年、新田義貞の鎌倉攻めの際に戦火で焼失してしまう。その後、長楽寺は現在の安養院がある場所へと移された。この場所にはもともと「善導寺」というお寺があったが、こちらも焼失していたため、その跡地が使われたのだ。そして、政子の死後、彼女の仏教上の名前(法名)である「安養院」という名前がつけられ、寺の名前となった。
話はさらに続く。この安養院も江戸時代の1680年に再び全焼してしまう。その再建の際に、別の場所にあった「田代寺」というお寺の観音堂を移してきた。このような経緯から、安養院は「長楽寺」「善導寺」「田代寺」という三つのお寺の歴史が重なり合ってできた、非常にユニークな寺院なのである。政子が頼朝のために建てた想い、そして彼女自身の名前が、幾度もの火災を乗り越えて今に受け継がれているのだ。
見どころは苔むした宝篋印塔(ほうきょういんとう)
安養院の本堂裏手にある墓地に進むと、大小二つの古い石塔が並んでいる。これが北条政子の墓と伝えられる場所だ。この石塔は「宝篋印塔(ほうきょういんとう)」と呼ばれる形式のものである。
宝篋印塔とは、もともとは「宝篋印陀羅尼」というお経を納めるために作られた仏塔の一種だ。鎌倉時代中期以降に多く造られるようになり、故人を供養するための供養塔や墓石として使われた。四角い基礎の上に、仏様や梵字が刻まれた塔身(とうしん)、特徴的な屋根(笠)、そして一番上に飾りがついた相輪(そうりん)という部分から構成されている。
安養院にある二つの宝篋印塔のうち、向かって左側の小さい方が北条政子の供養塔とされている。そして、右側の大きな塔は、国の重要文化財にも指定されており、安養院がこの地に移る前からあった善導寺の開山・尊観(そんかん)の墓と伝えられている。この尊観の塔には1308年の銘があり、鎌倉に現存する宝篋印塔としては最古のものだ。
政子の想いを受け継ぐ「長楽寺」と、もともとこの地にあった「善導寺」。その二つの寺の創設者である政子と尊観の墓が、こうして並んで立っている様子は、まさに安養院が持つ二重の歴史を物語っているかのようだ。苔むした静かな石塔を前にすると、鎌倉の激動の時代を生き抜いた人々の歴史の重みが感じられるだろう。
源頼朝の墓との位置関係と合わせて巡るモデルコース
北条政子の墓を訪れるなら、ぜひ夫である源頼朝の墓もあわせて巡りたい。二人の墓は少し離れた場所にあるが、鎌倉の歴史を感じながら歩くにはちょうど良い距離だ。
モデルコース案
- JR鎌倉駅を出発
まずは東口からスタートする。
- 源頼朝の墓へ
鶴岡八幡宮の横を通り、北へ向かって約20分ほど歩くと、源頼朝の墓(法華堂跡)に到着する。バスを利用する場合は、鎌倉駅東口からバスに乗り「岐れ道」で下車、徒歩約5分だ。静かな丘の上に立つ頼朝の墓に手を合わせ、鎌倉幕府の始まりに思いを馳せよう。
- 安養院へ
頼朝の墓から南へ、鎌倉の古い町並みが残るエリアを歩いて安養院へ向かう。徒歩で約20分ほどの道のりだ。夫の墓を参った後に、妻が夫のために建てた寺の跡を継ぐ安養院を訪れることで、二人の物語をより深く感じることができる。
- 安養院で北条政子の墓を参拝
安養院に到着したら、本堂裏の宝篋印塔を訪れ、尼将軍として生きた政子の生涯に心を寄せる。
このコースを歩けば、単に史跡を点で見るのではなく、夫婦の物語として線で捉えることができ、より記憶に残る歴史散策になるだろう。
尼将軍・北条政子とはどんな人物だったのか?
ここで改めて、北条政子がどのような人物だったのかを振り返っておこう。彼女はただの「将軍の妻」ではなかった。
政子は伊豆の豪族・北条時政の娘として生まれた。当時、伊豆に流されていた源頼朝と恋に落ち、親の反対を押し切って結婚した。頼朝が平家を倒し、鎌倉に幕府を開くと、政子は「御台所(みだいどころ)」として、頼朝を支えた。
頼朝の死後、彼女の人生は大きく動く。政子は髪をそり落として尼となったが、政治の世界から引退はしなかった。息子の頼家、実朝が次々と2代、3代将軍となるが、二人とも暗殺されるという悲劇に見舞われる。源氏の将軍が途絶えるという幕府最大の危機に、政子は京都から幼い公家の子(藤原頼経)を次の将軍として迎え、自らはその後見人として政治の実権を握った。このため、彼女は「尼将軍」と呼ばれるようになったのだ。
彼女のリーダーシップが最も発揮されたのが、1221年の「承久の乱」である。後鳥羽上皇が幕府を倒そうと兵を挙げた際、朝廷と戦うことにためらう御家人たちを前に、政子は涙ながらに演説した。「亡き頼朝公から受けた御恩は、山よりも高く、海よりも深い。今こそその恩に報いる時です」と。この言葉に心を動かされた御家人たちは奮い立ち、一致団結して上皇軍に勝利した。
夫とすべての子を失うという深い悲しみを乗り越え、その悲しみを力に変えて幕府を守り抜いた北条政子。彼女は、日本の歴史において、女性でありながら国を動かした、類まれな強さを持つ人物だったのである。
もう一つの伝承地から探る北条政子の墓の謎と周辺の見どころ
寿福寺にもある?北条政子の墓とされる五輪塔の謎
安養院のほかに、もう一つ、北条政子の墓と伝えられる場所がある。それが、鎌倉五山の第三位に数えられる格式高い禅寺「寿福寺」だ。
寿福寺は鎌倉駅西口から徒歩10分ほどの場所にある。この寺の最大の特徴は、普段は境内が一般公開されていないことだ。山門から中門へと続く美しい石畳の参道と、本堂裏手にある墓地のみが参拝可能となっている(正月やゴールデンウィークなど、年に数回特別公開されることもある)。
政子の墓とされるものは、この公開されている墓地の最も奥、崖をくり抜いて作られた「やぐら」と呼ばれる横穴式のお墓の中にある。やぐらの中には、二つの石塔が並んでおり、手前が北条政子、奥が彼女の息子であり3代将軍の源実朝の墓と伝えられている。
ここの墓は、安養院の宝篋印塔とは違う「五輪塔(ごりんとう)」という形式だ。五輪塔は、仏教の宇宙観を表す5つの要素「地(四角)・水(丸)・火(三角)・風(半月)・空(宝珠)」をかたどった石を積み重ねたもので、平安時代後期から故人を供養するための墓として広く使われた。
夫を弔うために建てた寺の系譜を引く安養院の墓とは対照的に、寿福寺では悲劇的な最期を遂げた息子・実朝と寄り添うように眠っている。暗く静かなやぐらの中にたたずむ五輪塔は、尼将軍という公の顔ではなく、息子を亡くした母としての政子の、より私的な一面を物語っているように感じられる。
| 項目 | 詳細 |
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市扇ガ谷1-17-7 |
| アクセス | JR鎌倉駅西口から徒歩約8分~10分 |
| 拝観範囲 | ・山門から中門までの参道と、本堂裏の墓地は自由に参拝可能 ・中門から先の境内は通常非公開(正月・GWなどに特別公開あり) |
| 拝観料 | 無料(志納) |
| 備考 | 北条政子・源実朝の墓は、公開されている墓地の奥にあるやぐらの中にあり、いつでも参拝できる。 |
なぜ北条政子の墓は複数存在するのか?その理由を考察
安養院と寿福寺。なぜ北条政子の墓は二つも存在するのだろうか。これは、当時の人々の「お墓」に対する考え方を知ることで謎が解ける。
現代の我々が考える「お墓」は、遺骨が埋葬されている場所を指すことが多い。しかし、鎌倉時代などの昔は、遺体を埋葬した場所と、その魂を供養するための場所が別々にあることは珍しくなかった。
今日、私たちが「北条政子の墓」や「源頼朝の墓」として訪れている場所は、実際に遺骨がそこにある「埋葬地」ではなく、彼女たちの魂を慰め、後世の人々がその功績を偲ぶために建てられた「供養塔(くようとう)」である可能性が非常に高い。実際、現在の頼朝の墓とされているものは、江戸時代に薩摩藩主の島津重豪によって建て直された供養塔である。
供養塔は、故人にゆかりのある場所や、故人を敬う人々によって、複数の場所に建てられることがあった。つまり、安養院と寿福寺の墓は「どちらが本物か」を競い合っているわけではないのだ。
安養院の墓は、夫・頼朝を弔うために寺を建てた「尼将軍」としての公的な顔を象徴する供養塔。一方、寿福寺の墓は、自らが創建し、愛する息子・実朝と共に眠る「母」としての私的な顔を象徴する供養塔。
二つの墓は、北条政子という一人の女性が持っていた、異なる側面をそれぞれ今に伝える、補い合う関係にある記念碑なのである。
北条政子と源頼朝の墓が別々の場所にある理由
夫婦である北条政子と源頼朝の墓が、なぜ隣り合っていないのか、という疑問も湧くかもしれない。これもまた、彼らが単なる夫婦ではなく、それぞれが独立した偉大な歴史上の人物として記憶されていることの表れだ。
彼らの墓は、現代の「〇〇家の墓」というような家族単位の墓所とは意味合いが異なる。それぞれの墓は、その人物の生涯において最も象徴的な場所に建てられている。
源頼朝の墓は、彼が幕府の政治を執り行った中心地「法華堂」の跡地にある。これは、鎌倉幕府の創設者としての彼の功績を記念する場所だ。
一方、北条政子の墓は、彼女自身の行動に深く関わる場所にある。安養院は彼女が夫のために建てた寺の後継であり、寿福寺は彼女自身が創建した寺である。
つまり、頼朝は「政治家・将軍」としてその権力の中心地で、政子は「信仰者・母」として彼女自身の想いが込められた場所で、それぞれが独立した存在として供養されているのだ。二人の墓が別々の場所にあることは、彼らが歴史の中でいかに大きな個々の存在であったかを示していると言えるだろう。
北条政子の墓とあわせて訪れたい鎌倉の関連史跡
北条政子の生涯をより深く理解するために、彼女の墓所とあわせて訪れたい鎌倉の史跡をいくつか紹介する。
- 鶴岡八幡宮
鎌倉幕府の精神的な中心地であり、政子の人生の重要な舞台となった場所だ。政子はここで頼朝の戦勝を祈願し、頼朝は政子の安産を願って参道の「段葛(だんかずら)」を造営した。また、息子・実朝が暗殺された悲劇の現場でもある。境内にある旗上弁財天社の「政子石」は、子宝や夫婦円満にご利益があるとされ、今も多くの人が訪れる。
- 鎌倉文学館
前述の通り、ここは政子が頼朝のために建立した最初の寺「長楽寺」があった場所だ。現在の洋館の入口脇に立つ石碑が、その歴史を静かに伝えている。ここを訪れることで、安養院の物語の原点に触れることができる。
- 源氏山公園
園内には、頼朝の鎌倉入り800年を記念して1980年に建てられた源頼朝像がある。この像は、政子が愛し、支え、そしてその死後に幕府を継いで守り抜いた夫の姿を思い描くのに最適な場所だ。公園は桜や紅葉の名所でもあり、鎌倉の自然と共に歴史に浸ることができる。
これらの場所を巡ることで、北条政子の物語が点から線へ、そして立体的な歴史絵巻として心に刻まれるはずだ。
御朱印はもらえる?参拝の記念に
参拝の記念となる御朱印。安養院と寿福寺では、どちらも御朱印をいただくことができるが、その方法や雰囲気は大きく異なる。
- 安養院の御朱印
安養院では、複数の種類の御朱印をいただくことができる。ご本尊である「阿弥陀如来」、坂東三十三観音霊場および鎌倉三十三観音霊場の札所である「千手観音」、そして「日限地蔵尊」などだ。山門を入って右側にある受付(授与所)でお願いすることができ、比較的スムーズにいただける。参拝の記念に、政子ゆかりの寺の御朱印をいただいてみてはいかがだろうか。
- 寿福寺の御朱印
一方、寿福寺の御朱印は少し特殊で、事前の心構えが必要かもしれない。通常非公開の寺であるため、御朱印をいただくには、中門の右手にある「関係者以外立入禁止」の看板の先へ進み、お寺の方の住居と思われる場所の受付窓口へ行く必要がある。
近年は住職の体調などから、直接書いていただくのではなく、あらかじめ紙に書かれた「書き置き」での対応が基本となっている。また、「一回の参拝につき御朱印は一種類まで」というルールがあるとも言われており、複数の御朱印(ご本尊、鎌倉三十三観音など)をいただくには、日を改めて複数回訪れる必要があるかもしれない。
この少し緊張感のある手続きも、普段は静寂に包まれている禅寺の雰囲気を体験する一部と考えると、また違った趣がある。
この二つの寺の御朱印のいただき方の違いは、それぞれの寺の性格そのものを表しているかのようだ。開かれた安養院と、静寂を守る寿福寺。どちらも北条政子の歴史を伝える上で欠かせない場所である。
まとめ:北条政子の墓
- 北条政子の墓と伝わる場所は鎌倉に二つあり、安養院と寿福寺がその伝承地である。
- 安養院の墓は「宝篋印塔」という形式で、本堂裏の墓地にある。
- 安養院は、政子が夫・源頼朝の供養のために建てた「長楽寺」が前身である。
- 寿福寺の墓は「五輪塔」という形式で、崖のやぐら(洞窟墓)の中にある。
- 寿福寺では、政子の墓は息子・源実朝の墓と並んで安置されている。
- 墓が複数あるのは、これらが遺骨を埋めた場所ではなく、魂を供養するための「供養塔」だからである。
- 安養院は「尼将軍」としての公的な政子を、寿福寺は「母」としての私的な政子を象徴している。
- 夫である源頼朝の墓とは別の場所にあるのは、それぞれが独立した偉人として祀られているためである。
- 歴史を深く知るには、鶴岡八幡宮や鎌倉文学館(旧長楽寺跡)などもあわせて訪れるのがおすすめである。
- 安養院、寿福寺ともに御朱印はいただけるが、特に寿福寺は書き置き対応や「一回一枚」など独自のルールがあるため注意が必要である。