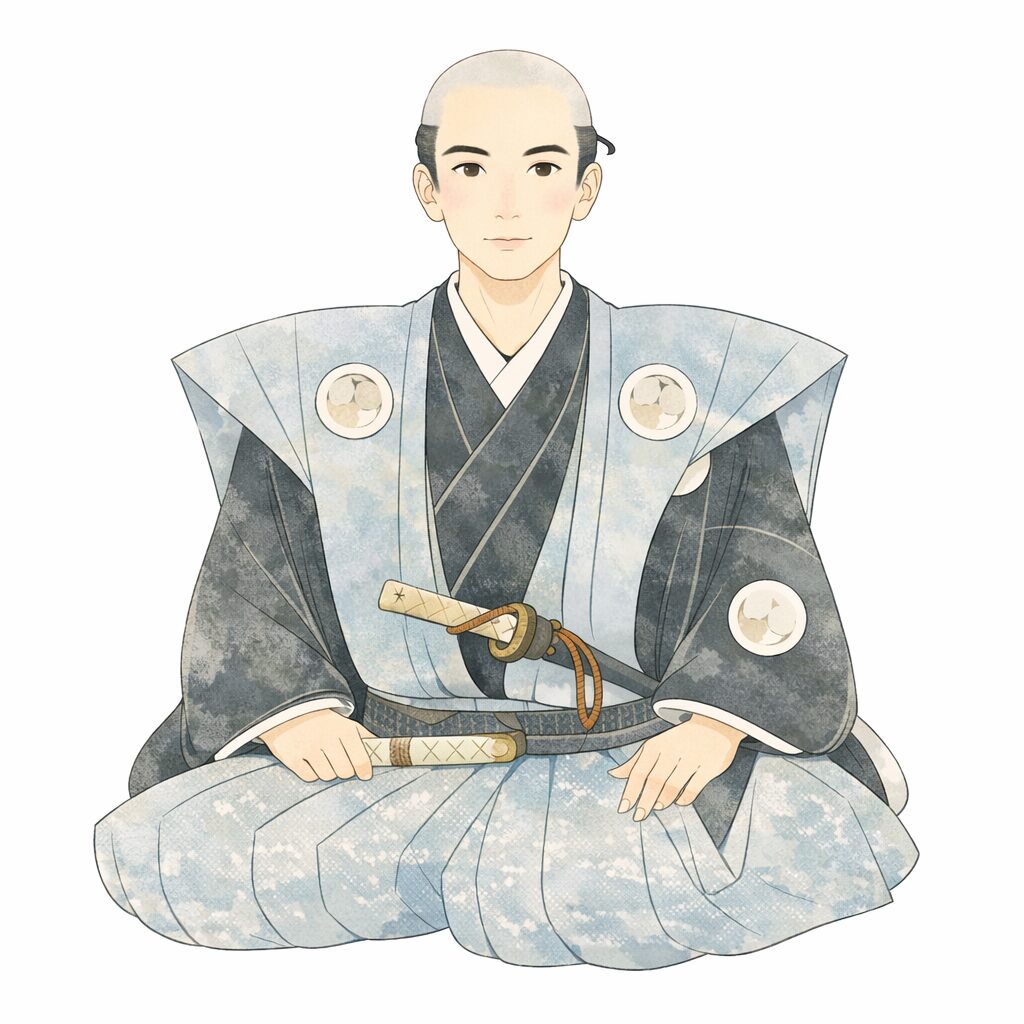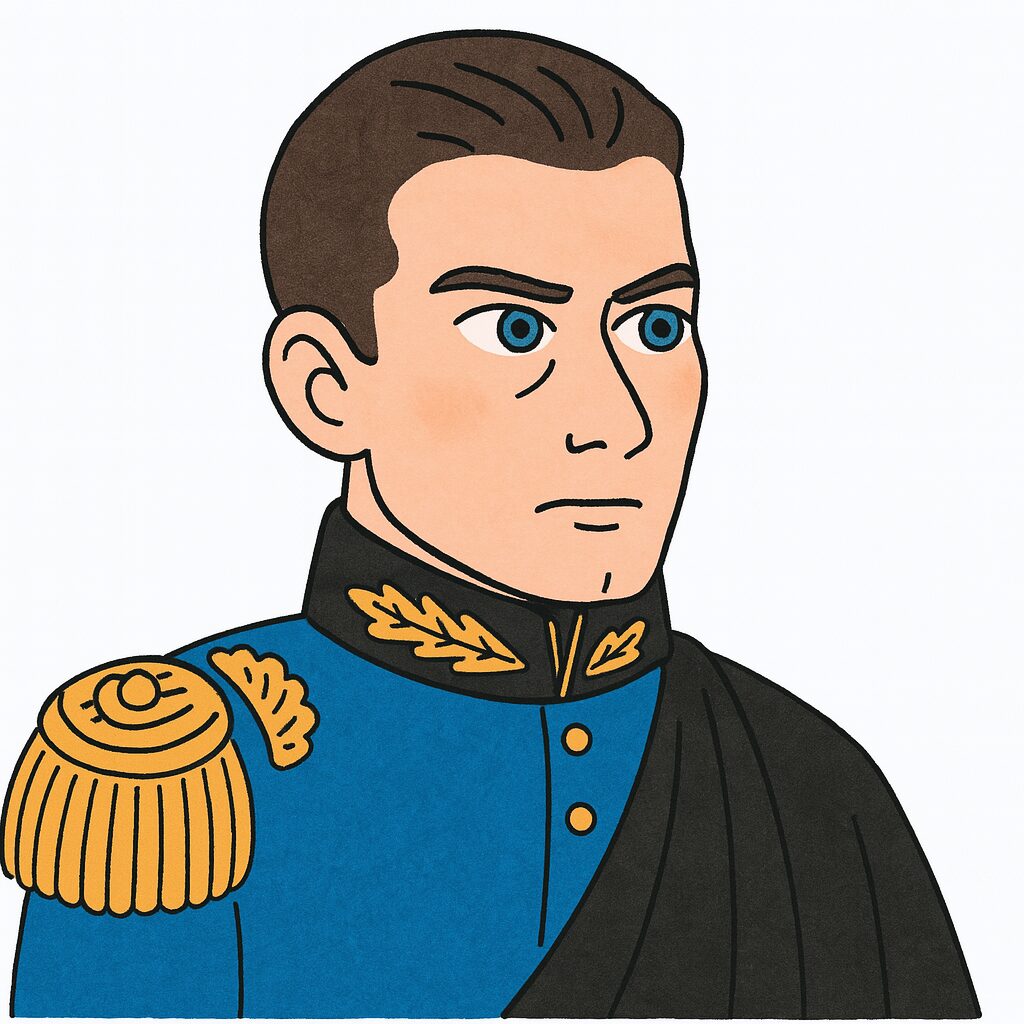
フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト(1796-1866)は、今からおよそ200年前、日本が外国との交流を厳しく制限していた「鎖国」の時代に、ドイツから日本へやってきた医者であり、たくさんの生き物や文化を調べた学者でもある。彼はただ病気を治すだけでなく、当時の日本でほとんど知られていなかった西洋の医学を伝え、逆に日本の珍しい動植物や地理、文化について詳しく調べてヨーロッパに紹介した。まるで、日本と世界の間に橋をかけたような人物だったのだ。
彼の人生は、学問に対する強い探求心と、どんな困難にも立ち向かうたくましい精神、そして当時の世界の状況が複雑に絡み合っていた。このブログ記事では、シーボルトという人物をもっと深く知るために、彼の意外な一面がわかる「決闘」の話、日本での活動が大きく変わるきっかけとなった「シーボルト事件」、そして彼がどれほど自然を愛していたかを示す「シーボルトミミズ」という三つのキーワードに注目して、彼のすごい功績はもちろん、その人柄や、当時の日本と世界の動きの中で彼がどんな役割を果たしたのかを、わかりやすく話していく。
- シーボルトは単なる学者ではなく、33回も決闘をしたほどの豪胆な人物だった。
- 鎖国中の日本に入国する際、彼は「ヤマホランダ」と称し、その機転で危機を乗り切った。
- シーボルト事件は、彼の日本での情報収集が原因で起こり、多くの日本人が処罰された大きな出来事だった。
- この事件後も、彼は日本で集めた膨大な資料をもとに、ヨーロッパで「日本学」を築き上げた。
- 彼の名前がつけられた「シーボルトミミズ」は、彼が日本の生物多様性にどれほど情熱を注いだかを物語っている。
シーボルトの意外な一面! 33回もの決闘に勝った豪胆な男
シーボルトというと、研究室で本を読んでいる真面目な学者というイメージがあるかもしれない。しかし実は、とても大胆で行動力のある一面を持っていた。そのたくましい精神と体は、鎖国中の日本という厳しい環境で活動する上で、とても大切な力になったのだ。
若き日のシーボルトと決闘の文化
シーボルトは1796年、ドイツのヴュルツブルクという学問が盛んな町で生まれた。彼の家系は代々医者や大学の先生をたくさん輩出する、医学界の名門だった。彼自身もヴュルツブルク大学で医学を学びながら、動物、植物、民族の文化など、色々な自然科学の知識を身につけた。学問に対する彼の深い興味は、小さい頃からずっと持っていたものだった。
大学にいた頃のシーボルトは、貴族の家柄としての強い誇りを持っていたと伝えられている。当時のヨーロッパ、特にドイツの大学では、学生同士の「決闘」が社会的に認められた慣習だった。名誉やプライドを守るための手段として、広く行われていたのだ。そんな時代の中で、シーボルトは学問に夢中になる一方で、かなり「やんちゃ」な一面も見せていたと記録に残っている。
なんと彼は、大学生活の間に実に33回もの決闘を行い、そのほとんどに勝ったという驚くべき話が残っている。この話は、彼がただ勉強ばかりしている「本の虫」ではなかったこと、体も心もとても強く、どんな相手にも負けない「絶対的な強者」という一面を持っていたことを示唆している。彼の顔には、その時の切り傷が残っていたとも伝えられていて、これが彼のたくましい性格を物語る証拠ともいえる。このような経験は、後に日本で難しい調査活動をする時や、予期せぬ出来事に対応する時、彼の揺るぎない自信と行動力の源になったと考えられる。
日本でのシーボルトの豪快なバイタリティ
シーボルトの豪胆さは、外国との交流が厳しく制限されていた日本という、とても特別な場所での活動でも存分に発揮された。1823年の8月、彼は今のインドネシアのジャカルタから45日かけて長い船旅をして、日本の長崎に到着した。当時の日本は、オランダ人以外の西洋人の入国を厳しく禁止していた。しかし、ドイツ人であるシーボルトは、オランダ領東インド陸軍病院の外科少佐という身分を利用し、オランダ人になりすまして入国を試みた。
入国審査の際、彼の不自然なオランダ語に役人が不審に思った。するとシーボルトはとっさに、「自分は『ヤマホランダ』、つまり山に住むオランダ人だから、なまりがあるんだ」と説明し、このピンチを切り抜けたという。実際にはオランダは山のない平らな国なので、この巧妙な嘘は、彼の機転の速さと大胆さ、そして目的達成のためには手段を選ばない強い意志を示すものだ。
彼の豪胆な性格は、1826年に江戸(今の東京)へ向かう際にも現れた。学術調査に協力してくれないオランダ商館長ステュルレルに対し、シーボルトは決闘を申し入れたと伝えられている。この行動は、彼が学問の探求にどれほど強い情熱を持っていたか、そしてそれを邪魔する相手にはひるむことなく立ち向かう強い意志を示している。
このように、「真面目な学者というイメージからは想像もつかない、シーボルトの豪快な行動力」は、見知らぬ異国の地で「大冒険」を成功させ、膨大な資料を集める上で、彼の重要な原動力となったと考えられる。彼の学術的な知識と、大胆な行動力という二つの側面が融合することで、鎖国という困難な状況下においても、彼は誰も成し遂げたことのない偉業を成し遂げることができたのだ。
シーボルト事件:鎖国時代の情報管理と学問の衝突
シーボルト事件は、シーボルトの日本での活動の中で最も大きな転機となった出来事である。これは、鎖国体制だった日本の情報管理の厳しさと、西洋の学問への探求心がぶつかり合った、象徴的な事件と言える。この事件は、彼の日本での功績に暗い影を落とす一方で、その後の彼の学術活動や「日本学」が発展するきっかけにも深く関係している。
事件の背景と発生
シーボルトは1823年8月に日本に来日した。彼は表向きはオランダ商館のお医者さんで、動植物を調べる学者として活動していた。しかし、実は単なる医者や研究者ではなかった。彼はオランダ領東インド政庁の総督から「国の計画に基づく特別な命令のもとに行動する特別な任務」を与えられて日本に来ていて、日本の政治や軍事の情報を集めるスパイのような役割も担っていたと考えられている。彼の日本への来日自体が、学問と情報収集という二つの目的を持っていたのだ。
日本に滞在して3年後の1826年1月、シーボルトはオランダ商館長(カピタン)が江戸へ将軍に挨拶に行く「江戸参府」に同行する機会を得た。この江戸での37日間の滞在中、彼は国で禁じられていると知りながらも、様々な方法で日本の大切な情報を集めた。特に問題となったのは、幕府の天文方(天文学や暦を扱う役職)で外国の書物の翻訳を担当していた高橋作左衛門景保(たかはし さくざえもん かげやす)から手に入れた樺太(今のサハリン)の詳しい地図の写しだった。この他にも、江戸城の本丸の詳しい図面や、武器・武具の説明図、将軍家の家紋(葵の紋)が入った着物など、軍事や政治に関する資料も集めていた。
高橋景保は、伊能忠敬(いのう ただたか)たちが作った日本地図の北の海岸線にわからない部分があったため、シーボルトが持っていたクルーゼンシュテルンの『世界一周記』という本で確認したいと考えた。その見返りとして、禁制品である日本地図の写しをシーボルトに渡したとされている。高橋は、この行為が「わが国に利益を与える」と強く信じていて、まるで「悪いことだとわかっていながらも、良いことだと信じてやった」という状態だった。また、北方を探検した間宮林蔵(まみや りんぞう)の上司であった最上徳内(もがみ とくない)からも樺太の地図を借りたという記述もある。これは、当時の日本側にも西洋の知識、特に地理情報に対する強い興味があったことを示唆している。
シーボルト事件は1828年(文政11年)に起こった。シーボルトが日本での5年間の滞在を終え、集めたたくさんの資料と一緒にオランダ領東インド(今のインドネシア)へ出発しようとした際、彼が乗っていた商船「コルネリウス・ハウトマン号」が嵐で長崎湾の中で座礁してしまった。積んであった荷物の多くが海に流れ出てしまい、その一部が日本の浜辺に打ち上げられた。その中から、外国へ持ち出すことが禁じられていた日本地図や江戸城の見取り図、樺太の測量図の写しなどが見つかったことで、事件が発覚したのだ。
事件の展開と関係者への処分
事件が発覚した後、幕府は高橋景保に疑いの目を向け、彼を逮捕した。高橋はシーボルトに禁制品を渡したことを自白した。シーボルトはスパイ容疑を否定したものの、1年間も軟禁状態に置かれて厳しい尋問を受け、持っていたものは全て押収された。その結果、翌年の1829年(文政12年)12月30日、彼は国外追放と二度と日本へ来ないという処分を受け、日本を去ることになった。彼が日本で集めたコレクションも没収された。
シーボルト事件は、日本側にとても大きな影響を与えた。地図を提供した幕府の書物奉行(しょもつぶぎょう)で天文方のトップだった高橋作左衛門景保は、厳しい取り調べの末に牢屋で病気で亡くなった。その後、彼の遺体は塩漬けにされ、死刑判決(斬首)という異例の処分が下された。これは当時の幕府の情報統制がどれほど厳しかったかを示すものだ。他にも、目の病気を治す幕府の医者である土生玄碩(はぶ げんせき)が役職を解かれるなど、高橋の部下やオランダ語の通訳、そしてシーボルトが開いた私塾「鳴滝塾(なるたきじゅく)」で教えを受けた高野長英(たかの ちょうえい)、二宮敬作(にのみや けいさく)、伊東玄朴(いとう げんぼく)、小関三英(こぜき さんえい)、伊藤圭介(いとう けいすけ)、桂川甫賢(かつらがわ ほけん)、高良斎(こう りょうさい)といった有名な蘭学者(西洋の学問を学ぶ学者)を含む、多くの幕府関係者や洋学者が罰せられた。この事件は、後に「蛮社の獄(ばんしゃのごく)」という蘭学者への弾圧事件の前に起こったものとして位置づけられている。
事件の歴史的意義とシーボルトの学術的遺産
シーボルト事件は、当時の江戸幕府が外国から情報が入ってくること、特に軍事や地理の情報に対して、とても厳しい管理体制を敷いていたことをはっきりと浮き彫りにした。これは、鎖国政策の根幹に関わる問題であり、幕府が国の安全をどれほど大切に考えていたかを示すものだった。この出来事は、学問を深く探求することが、時として国の情報戦略と複雑に絡み合う可能性があることを示している。シーボルトの日本での活動は、純粋な学術研究と、当時の国際社会での国と国との情報収集の競争という二つの側面が、切り離せない形で結びついていたのだ。彼の学問的な大きな功績の裏には、ある種の「スパイ活動」が伴っていたという複雑な事実が存在した。
シーボルトは国外追放となったが、日本で集めた膨大な資料(文学や民族に関するコレクション5000点以上、哺乳動物の標本200点、植物の押し葉標本12,000点など)をもとに、オランダに帰国した後も精力的に本を書き続けた。彼は1832年にライデンで自分のコレクションを展示する「日本博物館」を開設し、これが世界で初めての日本博物館と言われている。彼が日本での研究の集大成として書いた全7巻の**『日本』、ヨーゼフ・ゲアハルト・ツッカリーニとの共著である『日本植物誌』、そして『日本動物誌』は、ヨーロッパに日本を体系的に紹介した画期的な本であり、彼を「日本学の大先生」にした。これらの本は、日本の地理、歴史、言葉、宗教、美術、政治、経済など、とても広い分野をカバーしていて、高野長英をはじめとする門人たちが提出したオランダ語の論文も活用された。特に『日本植物誌』では、12,000点の押し葉標本をもとに2300種類の植物を記録し、今でも彼の名前が学名に残っている植物がたくさんある。『日本動物誌』**では、スズキ、マダイ、イセエビなど、日本でよく見かける生き物の学名が初めて確定された。
シーボルトの活動は、西洋に「日本学」を誕生させ、日本に関する知識を世界に広く紹介する先駆的な役割を果たした。彼が収集した植物標本は後の研究にも活用され、日本の植物に関する知識の基礎を築いた。また、日本茶の種をインドネシアのジャワ島に送り、そこで茶栽培が始まるきっかけを作るなど、実用的な貢献も行った。彼のコレクションは、世界で初めての民族学博物館が作られるきっかけにもなり、浮世絵師・葛飾北斎の『北斎漫画』に最初に注目したヨーロッパ人でもあった。
シーボルトは国外追放から30年後の1859年(安政6年)、日本が開国し(1854年)、日本とオランダの友好通商条約が結ばれて追放令が解除された後、オランダ貿易会社の顧問として再び日本へやって来た。1861年には幕府の外交顧問にもなったが、各国の大使やオランダ領事館から反感を買ったため、数ヶ月で解任され、1863年に帰国した。彼は1866年10月18日、ドイツのミュンヘンで70歳で亡くなった。シーボルト事件は、彼が日本を去る原因となったものの、その後の彼の学術活動をさらに活発にするきっかけとなり、結果として西洋における日本研究が大きく進展するのに貢献したのだ。
シーボルトミミズ:生物学と命名のロマン
フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトの名前は、彼が行った膨大な日本研究の中でも、特に生物学の分野で「シーボルトミミズ」という形で今も残っている。これは、彼がどれほど自然科学に深い情熱を注いでいたか、そしてその情熱が後の学術界にどれほど大きな影響を与え続けたかを象徴するものだ。
シーボルトミミズの発見と名前の由来
「シーボルトミミズ」(Pheretima sieboldi (Horst)) は、日本に生息する大きなミミズで、その和名と学名は、江戸時代に日本に来てこのミミズを採集した医者であり博物学者であるフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトにちなんで名付けられた。シーボルトが採集した標本をオランダのライデン博物館に持ち帰り、それを研究したHorst(ホルスト)という学者が彼に敬意を表して献名したものだ。
このミミズは、日本に生息するミミズの中で初めて学名が与えられた種類という点で、日本の生物学の歴史においてとても重要な意味を持つ。これは、シーボルトが日本における生物の多様性を研究する上で、先駆者的な役割を果たしたことを示している。どこで正確に採集されたかは書かれていないものの、彼の収集活動がどれほど広範囲にわたっていたかを示す一例だ。シーボルトは、当時のヨーロッパの学術界にとって「未知の国」とも言える日本を、まさに彼が求めていた「これまであまり調査されていない地域」としての「宝庫」と捉え、その生物の多様性を明らかにすることに並々ならぬ情熱を注いでいたことが、このミミズの命名からもわかる。
シーボルトミミズの生物学的特徴と生態
シーボルトミミズは、日本に生息する大きなミミズで、「日本最大のミミズの一つ」と言われている。大人になったシーボルトミミズの体長は、だいたい25センチから28センチにもなり、その大きさはとても目を引く。
一番の特徴は、濃い紺色や青みがかった光沢のある体色で、他のミミズと簡単に見分けがつく点だ。この目立つ見た目のため、昔から人々に知られていて、各地で違う名前で呼ばれるほどだ。
主に西日本の山林に生息していて、特に四国や九州を中心に分布している。地面に出てくることがよくあるので、人目を引く存在だ。その存在は、シーボルトが日本の自然環境の細部にまで目を向け、その多様性を記録しようと努力した証拠である。
シーボルトの博物学研究における位置づけ
シーボルトは、日本に滞在している間に、たくさんの動植物の標本を集めた。植物の押し葉標本は12,000点、哺乳動物の標本は200点にも及び、これらはオランダのライデン博物館やナチュラリス自然史博物館(約6500点の標本を収蔵)に保管されている。シーボルトミミズも、この広い範囲にわたるコレクションの一部として採集されたものであり、彼の博物学研究の網羅性を示している。彼は同じ種類の動物でも、成長に伴う形の違い、地域による変化、オスとメスの違いを意識して、複数の個体の標本を細かく集めていて、後の分類研究にとても役立った。
シーボルトは、日本で集めた動植物に関する情報をもとに、ヨーゼフ・ゲアハルト・ツッカリーニと共著で**『日本植物誌』を出版し、また『日本動物誌』を著した。『日本動物誌』**では、スズキ、マダイ、イセエビなど、日本でよく見かける生き物の学名が初めて確定された。シーボルトミミズの学名が確定したのも、この広範囲な動物学研究の一環として位置づけられる。
シーボルトに敬意を表して、学名に”sieboldi”や”sieboldii”と名付けられている生き物はたくさん存在する。例えば、サクラソウ (Primula sieboldii) などが挙げられる。これは、彼が日本の生物多様性を明らかにし、世界に紹介する上で果たした多大な貢献を物語っている。彼の植物学への情熱は、日本の自然の美しさを世界に広めることにもつながった。シーボルトの博物学研究は、日本の生物多様性が世界に知られるきっかけとなり、後の生物学研究の基礎が築かれたと言える。彼にちなんで名付けられた数多くの生物の学名は、その永続的な影響力を示しており、一人の研究者の情熱が、国際的な科学知識の発展にどれほど貢献しうるかを示す良い例である。
シーボルトに関するよくある質問
Q1: シーボルトはなぜ日本に来たのか?
A1: シーボルトは、オランダ商館付きの医者として日本に来たが、同時に日本の動植物や地理、文化などの情報を集めるという学術的な目的も持っていた。また、オランダ政府からの特別な指示で、日本の政治や軍事の情報を収集する秘密の任務も帯びていたと考えられている。
Q2: シーボルト事件とは具体的に何が原因で起こったのか?
A2: シーボルト事件は、シーボルトが日本を離れる際に、日本から国外持ち出しが禁じられていた日本地図や江戸城の見取図などの機密情報が、船の座礁事故で偶然見つかったことから発覚した。幕府の役人から禁制品を受け取っていた高橋景保が逮捕され、多くの日本人も処罰された。
Q3: シーボルトミミズはなぜシーボルトの名前がつけられたのか?
A3: シーボルトミミズは、シーボルトが日本で採集し、ヨーロッパに持ち帰った標本をもとに、Horstという学者がシーボルトに敬意を表して学名を献名したためだ。これは、シーボルトが日本の生物多様性の研究に大きく貢献した証だ。
Q4: シーボルトは日本にどんな影響を与えたのか?
A4: シーボルトは西洋医学を日本に伝え、多くの日本人医者や学者を育てた。また、日本の動植物、地理、文化に関する膨大な資料をヨーロッパに紹介し、「日本学」の基礎を築いた。彼の活動は、西洋に日本への理解を深めさせるきっかけとなった。
Q5: シーボルトは事件後、日本に再来日したのか?
A5: はい、シーボルトは国外追放から30年後、日本が開国して追放令が解除された後の1859年に、オランダ貿易会社の顧問として再び日本を訪れた。一時的に幕府の外交顧問にも就任したが、数ヶ月で解任され、1863年に帰国した。
結論:シーボルトが遺した知の遺産と日本への貢献
フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトは、その大胆な性格と飽くなき知的好奇心、そして時に国の情報戦略に巻き込まれながらも、鎖国中の日本において計り知れない足跡を残した。彼の生涯は、単なる一人の医者や博物学者の枠を超え、日本と西洋の学問や文化交流の歴史において、極めて重要な役割を果たしたことを示している。
彼の功績は多岐にわたる。彼は西洋医学を日本に伝え、1824年に開いた鳴滝塾を通じて、高野長英、二宮敬作、伊東玄朴、小関三英、伊藤圭介といった多くの日本人医者や学者を育て、市民に病気の治療を見せたり、医学の基本的な知識や診断方法、科学全般を教えたりした。同時に、日本の動植物、地理、民族の文化に関する膨大な資料を集め、その成果を**『日本』、『日本植物誌』、『日本動物誌』**といった大著としてヨーロッパに紹介した。これらの活動は、西洋における「日本学」の基礎を築き、日本の自然や文化が世界に知られるきっかけとなった。
シーボルト事件によって一時的に日本を追放されたものの、彼の研究と収集品は、オランダのライデン博物館やナチュラリス自然史博物館に保管され、現在も日本の文化や自然を伝える貴重な資料として活用されている。特にライデンにあるシーボルトハウスは、彼が帰国後に住んだ家であり、世界で初めての日本博物館として日本の文化財を展示し、日本とオランダの文化交流の中心となっている。また、長崎シーボルト記念館など、日本国内にも彼の功績を称える施設がたくさん存在し、その遺産は現代にも受け継がれている。
シーボルトの物語は、学問を深く探求することが、時に政治的・社会的な制限とぶつかる可能性を示唆する一方で、知識を共有し、異なる文化を理解することがいかに大切であるかを教えてくれる。彼が残した学術的な遺産は、現代の植物学や動物学、民族学の研究においても重要な参考資料とされており、彼の名前が献名された数多くの生物の学名や、彼が日本からヨーロッパに紹介した植物が今のヨーロッパの園芸に欠かせない存在となっていることなど、その影響は今日まで続いている。
シーボルトは、日本と世界の相互理解を深める上で欠かせない存在であり続けている。彼の功績は、一つの分野に限られず、学術、文化、外交といった複数の側面で大きな影響を与えており、事件による中断があったにもかかわらず、その影響は彼の死後も現代に至るまで受け継がれているのだ。これは、彼の研究と収集の質が極めて高かったこと、そして彼が築いた日本と西洋の学術交流の基礎が、一時的な政治的な障害を超えて長く続く力を持っていたことを示している。