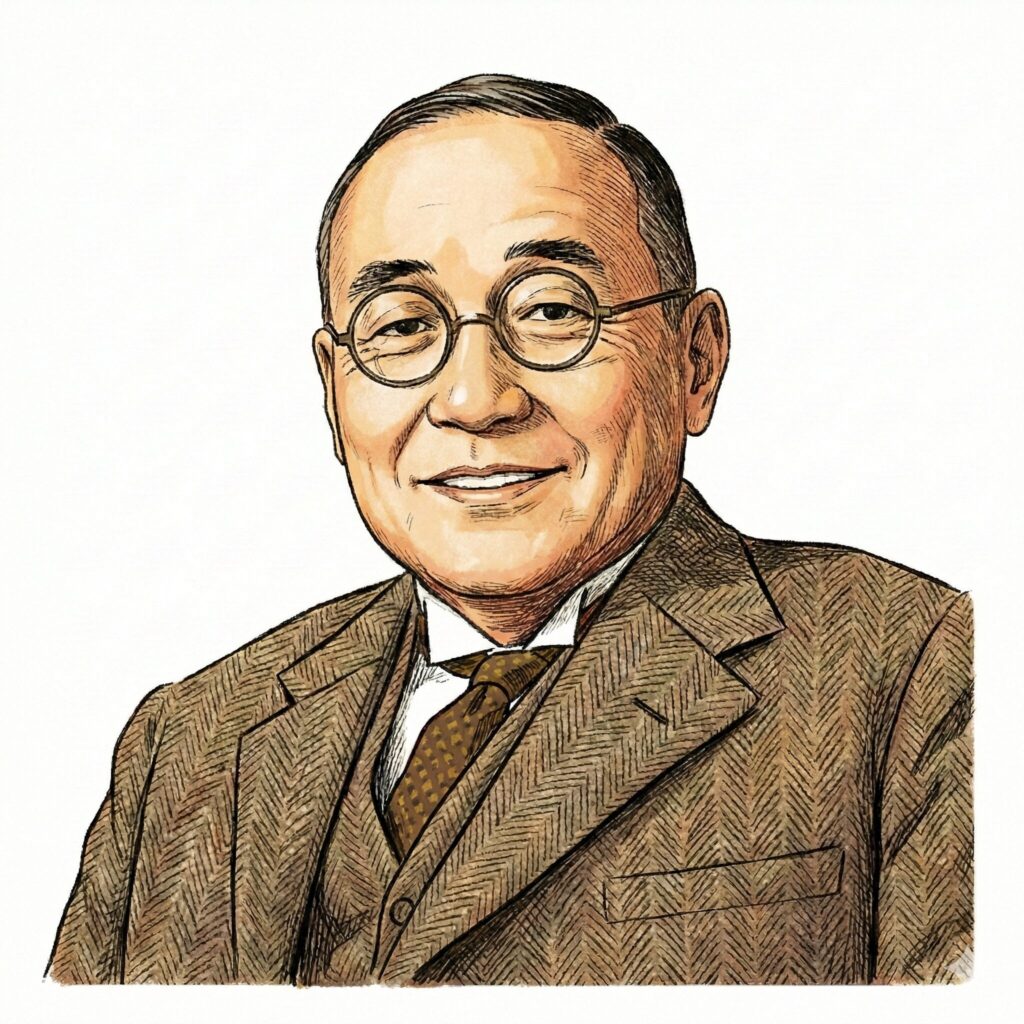太宰治と芥川龍之介は、同じ日本文学の大きな名前なのに、生前に会っていない。けれど、太宰の中では芥川はずっと「憧れ」の中心にいた。
その憧れが表に出たのが、芥川賞をめぐる出来事だ。太宰は候補になり、落選し、選評に激しく反応して“場外戦”を起こした。
「芥川賞騒動」は、陰謀のように語られることもある。だが、残された記録をたどると、意外なほど筋は単純だ。
この記事では、会えなかった理由、憧れの正体、そして芥川賞騒動の真相を、できるだけわかりやすく整理する。
太宰治と芥川龍之介|会えなかった「憧れ」が生まれた理由
生きた時代のズレが「会えなかった」を決めた
芥川龍之介は1892年生まれで、1927年に亡くなっている。太宰治は1909年生まれで、1948年に亡くなっている。まず、二人の活動期がきれいにずれているのが大前提だ。
芥川が亡くなった1927年、太宰はまだ十代で、文壇の中心に出る前だった。後から追いかける形になり、本人がどれほど会いたくても、時間が戻ることはない。
また、ゆかりの地の展示などでも「生前二人が対面することはありませんでした」と明確に扱われる。だから太宰の憧れは、実在の人物というより、作品を通した“像”として育った面が大きい。
太宰が芥川に惹かれた理由は「短編の鋭さ」にある
芥川は短編の名手として知られ、題材や文体を使い分けながら多くの作品を書いた。読者の目線を一気に“核心”へ運ぶ切れ味があるのが強い。
太宰は、そうした芥川文学に青年期から強く引きつけられていたと語られる。単なるファンではなく、「この人の書き方で、どこまで行けるのか」を学ぶような憧れだったはずだ。
一方で太宰は、後に“告白の語り”を武器にしていく作家だ。芥川の冷静な構成力を見つめながら、自分は別の道で勝負する。その「距離感」も、憧れを長く燃やした理由だと思う。
「ぼんやりした不安」という影が、後の世代にも残った
芥川の死はしばしば「ぼんやりした不安」と結びつけて語られる。大きな才能が、強い不安の中で終わった。その事実は、後の作家にとって“恐いほどの現実”になる。
太宰にとっても、憧れの人が「完成」より先に去ったことは重かったはずだ。直接会えないまま、作品だけが残り、死だけが確定する。そこに“神話”のような影が生まれる。
太宰自身も最後は入水自殺で生涯を閉じる。もちろん同一視はできないが、「文学と生の痛み」を真正面から抱えた点で、芥川の影が太宰の中に長く残ったのは不思議ではない。
太宰治と芥川龍之介|芥川賞の誕生と太宰の落選
芥川賞は「亡友を記念し、新人を世に出す」ために作られた
芥川賞と直木賞は、菊池寛が亡き友を記念する形で創設を宣言した、と説明されることが多い。目的は“無名に近い新進作家を世に出す”ことだった。
この「新人を押し上げる仕組み」を、雑誌が主導して作ったのが当時の新しさだ。文学が社会に広がる一方で、賞が作家の運命を左右する時代が始まった。
つまり芥川賞は、芥川龍之介を記念するだけの賞ではない。芥川の名を借りて、“次の世代”を可視化する舞台になった。そこに太宰が巻き込まれていく。
第1回芥川賞の候補と結果はこうだった
第1回の芥川賞受賞作は、石川達三『蒼氓』だと整理されている。最終候補には複数作が並び、太宰治『逆行』も候補に入ったとされる。
ここで大事なのは、太宰が「候補になれなかった」わけではない点だ。候補になったうえで、結果として受賞に届かなかった。そして問題は“落選後”に起きた。
芥川賞は当初から注目度が高く、受賞・落選は作家の評価や生活にも響く。だからこそ太宰にとっては、落選が単なる出来事で終わりにくかった。
選評の「生活に厭な雲」は、何を意味したのか
騒動の火種は、選評の一文だ。川端康成が太宰について「生活に厭な雲」がある、と評したことが、太宰の怒りに火をつけたと説明される。
ここで大事なのは、この言葉が「受賞取り消しの陰謀」を示すサインではない点だ。川端の“私見”として、当時の太宰の不安定さが作品に影を落とした、という見立てに近い。
ただ、太宰側からすると話は別だ。才能そのものではなく“生活”を理由に語られたように感じた。だから傷が深くなり、反撃が文章として噴き出した。
太宰治と芥川龍之介|芥川賞騒動の真相
太宰「川端康成へ」は、何に怒っていたのか
太宰は「川端康成へ」という一文を発表している。内容は、川端の感覚や生き方を皮肉りつつ、過激な言葉で挑発するものだったとされる。
落選そのものより、選評の言葉が“評価の線”を越えたと太宰が受け取ったのが核心だ。自分の作品がどう見られたか以上に、自分の存在がどう扱われたかが痛かった。
つまり騒動は、芥川賞の結果よりも、「憧れの世界が、自分をどう見たか」という痛みから生まれた。太宰にとって芥川は直接会えない存在で、芥川賞はその“入口”だった。
川端の反論が示した「真相」は、票差が大きかったことだ
川端は翌号で反論し、選考会では受賞作に票が集まり、他の候補は少数票だった、と説明したとされる。これでは大きな議論が起きにくい、という趣旨だ。
さらに川端は、事情を知らないなら「妄想や邪推はせぬがよい」とたしなめた、と語られる。ここに“密室の陰謀”より先に、単純な得票差があったことが見える。
これが「芥川賞騒動の真相」の骨格だ。受賞作は決まっていて、太宰が噛みついたのは、結果そのものより、選評が投げた言葉のほうだった。
騒動のあと太宰は、憧れを作品へ戻していく
太宰は芥川賞を取れなかったが、戦後に『斜陽』『人間失格』などで大きな反響を得た。賞の有無が作家の価値を決め切るわけではない。
一方、芥川の名は、芥川賞を通して社会に残り続ける。太宰はその舞台で痛い目を見たが、だからこそ“憧れを神棚に置いたまま”にはできなくなった。
会えなかった憧れは、最後には「自分の文体で決着をつける」しかない。芥川を読んで燃え、芥川賞で傷つき、それでも書き続けた――そこに二人の関係のいちばん人間的なところがある。
太宰治と芥川龍之介 まとめ
- 二人は生前に対面していない
- 芥川は1927年に亡くなり、太宰は後から文壇に入った
- 太宰の憧れは、実像よりも作品を通した“像”として育った
- 芥川は短編の名手で、文体と題材の幅が広い
- 芥川賞は新人を押し上げるために作られた文学賞だ
- 太宰は『逆行』で第1回芥川賞候補になった
- 受賞は石川達三『蒼氓』で、候補の中でも票差があったとされる
- 火種は落選より、選評の「生活に厭な雲」という言葉だった
- 太宰は「川端康成へ」で挑発し、川端は票差を示して反論したとされる
- 太宰は賞を逃しても、後に代表作で強い存在感を残した