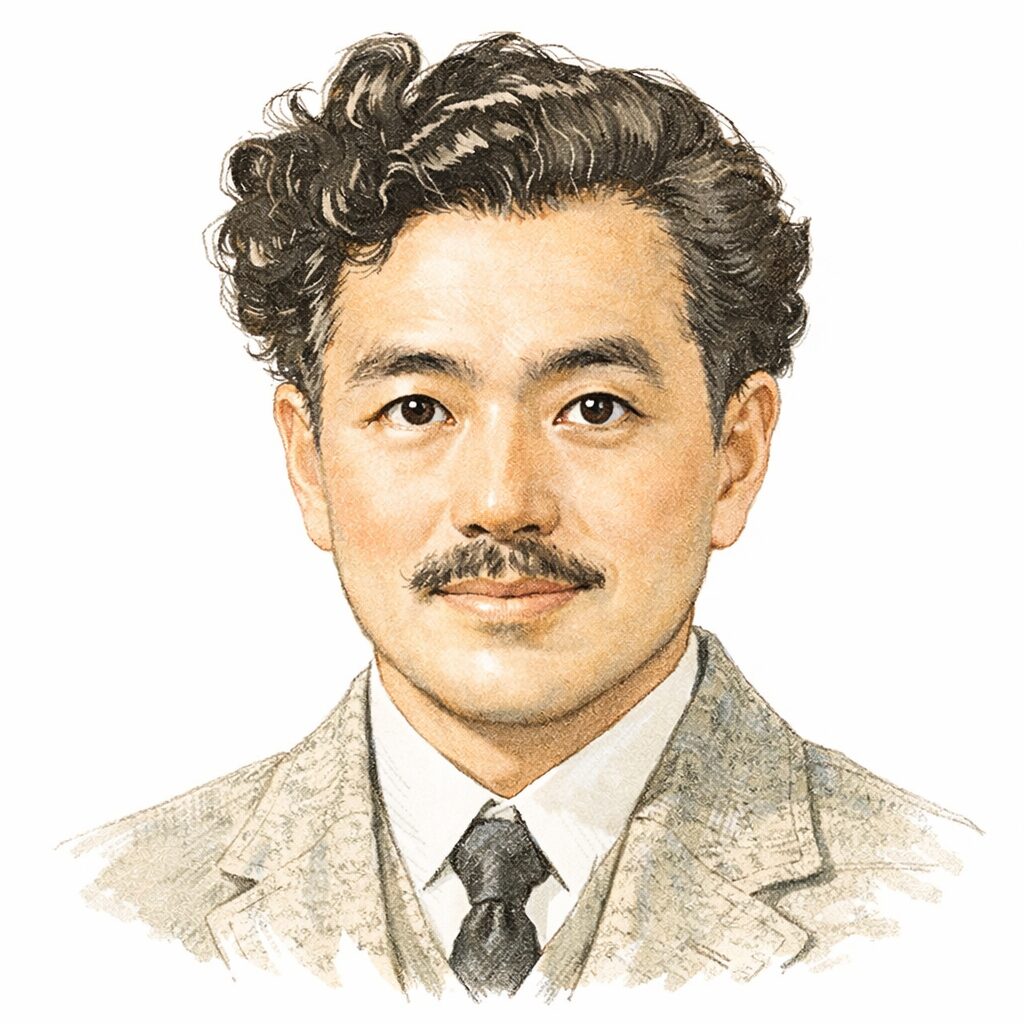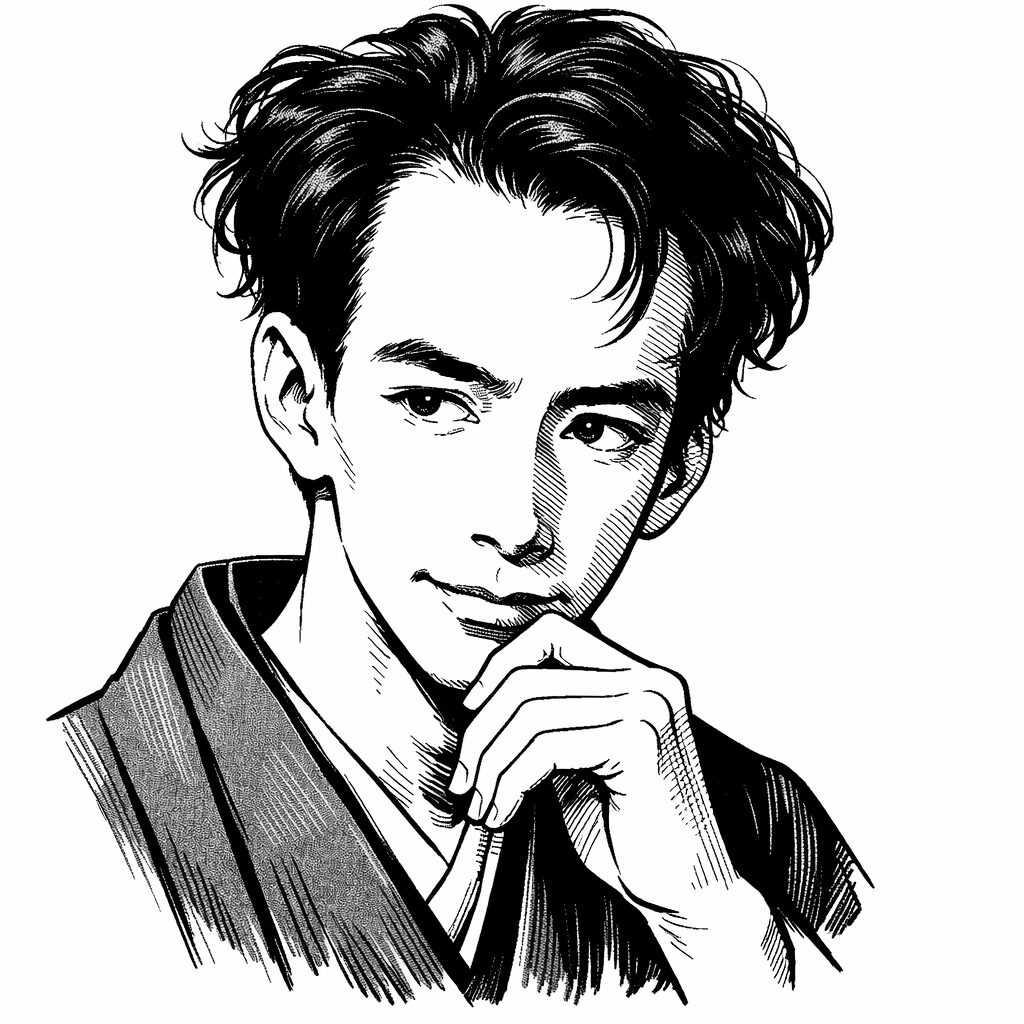「与謝野晶子とロダン」と聞くと、遠い世界の話に思えるかもしれない。だが晶子は1912年、夫・与謝野寛を追って欧州へ渡り、パリで彫刻家オーギュスト・ロダンと実際に会っている。
この面会は、1912年6月18日と日付まで資料で確認できる。ロダンは日本で自分の展覧会を開きたいとして、夫妻に仲立ちを頼んだとされる。
さらに翌1913年3月12日、ロダンが寛あてに書簡を作成し、展覧会へ向けて準備を進めている旨を知らせた。晶子は妊娠が判明したこともあり1912年10月に帰国し、旅の記録はのちに『巴里より』としてまとめられた。
本記事は、こうした資料と作品本文を照合しながら、面会の経緯・場所・その後の動きまでを整理する。年表のように追える形で、誤解されやすい点も補足する。読み終えるころには、二人の名が並ぶ理由がはっきりするはずだ。
与謝野晶子とロダン:面会までの道のり
渡欧と『巴里より』が生まれた背景
晶子は1912年5月、先に渡仏していた寛を追って欧州へ向かった。シベリア鉄道経由でパリに入り、当時としては珍しい単独渡航を成し遂げた点でも注目される。
滞在中はパリを拠点に、ロンドン、ブリュッセル、ミュンヘン、ベルリン、アムステルダムなども訪ねたことが伝わる。旅の途中で妊娠が分かり、晶子は1912年10月に海路で帰国し、寛は翌1913年1月に帰国した。
体験は、帰国後に写真を多く載せた紀行文集『巴里より』へ結実した。寛が事実を淡々と述べるのに対し、晶子は人間観察に徹する視点を強く持つとされる。
この土台があるからこそ、ロダンとの面会が強烈に響いた。作品を読むと、街の熱と巨匠の存在感が一続きの体験として立ち上がる。
1912年6月18日の面会は何が確実か
面会の事実は、公的資料で押さえられる。晶子と寛は1912年6月18日にロダンと会い、日本での展覧会の仲立ちを頼まれたと記録されている。
『巴里より』でも、ロダン訪問は一つの山場として語られる。夫妻にとって忘れられない出来事だったことがうかがえる。
面会場所の細部は資料によって語り方が分かれる。ムードンの住まいを訪ねた流れで語られることが多い一方、パリのビロン館で面会したと整理される記録もある。
確実に言えるのは、夫妻がロダンに会い、言葉を交わし、その体験を文章として残したことだ。場所の細部は断定を急がず、複数の記録を突き合わせて読むのが安全である。
展覧会の仲立ち依頼と1913年の書簡
資料が興味深いのは、面会が会えたで終わらない点まで示すところだ。ロダンは夫妻に、日本で自分の展覧会を開きたいので仲立ちをお願いしたいと伝えたという。
そして1913年3月12日、ロダンは与謝野寛あての書簡を作成した。本文はタイプで打たれ、最後の署名だけが自筆と説明される。内容は、日本でのロダン展開催に向けて準備を進めていることを知らせるものだ。
この書簡が残るという事実は、与謝野夫妻が一時の来訪者ではなく、展覧会計画の相談相手として見られていた可能性を高める。
ただし、実際に日本で展覧会がどこまで進んだかは別問題だ。面会日と書簡の存在を確実に押さえたうえで、推測は推測として区別して書くのが信頼性を守るコツになる。
1912年10月帰国と四男アウギュスト
旅の終盤、晶子は妊娠の診断を受け、単身での帰国を決めた。東京に残した子どもたちへの思いが募ったことも背景として語られる。
晶子は1912年10月に海路で帰国し、寛は翌1913年1月に帰国したとされる。面会が6月18日なので、その後ほどなく帰国準備に入った計算になる。
そして1913年4月、四男が生まれ、名はアウギュストとされる。名前の由来はロダンとの出会いにちなむとも言われるが、ここは断言せず「ちなむとされる」程度に留めるのが安全だ。
与謝野晶子とロダン:言葉と作品に残る余韻
『巴里より』の「ロダン翁」を読む視点
『巴里より』には、ロダン訪問を扱う章があり、「ロダン翁」という題が付けられている。ここで重要なのは、夫妻が作品だけではなく人としてのロダンを見に行った点だ。
同じ出来事でも、寛は事実を淡々と述べ、晶子は人間観察に徹する。読者は二つの目を通して、巨匠の存在感と場の緊張感を立体的に感じられる。
晶子の文章は、対面の場の空気や、自分の緊張、相手のしぐさといったその場の温度を大事にする。描写で補うことで、敬意や驚きを伝えている。
短歌だけでなく『巴里より』の章も合わせて読むと、面会が単なる名所巡りではなかったことが伝わってくる。
『火の鳥』の追悼歌が示すロダン像
晶子はロダンの死(1917年)を受け、追悼の歌を詠んだと整理されている。その歌は歌集『火の鳥』(1919年)に収録されたとされ、「ああロダン君は不思議のカテドラル…」の一首はロダンの偉大さを表す歌として知られる。
ここでのカテドラル(大聖堂)は、巨大で、長い時間を耐え、そこに立つだけで人の心を動かす存在の比喩だ。晶子はロダンを説明する代わりに、建築のイメージへ置き換えて一気に伝えている。
この一首を読むコツは、ロダンを人物として見るより、時代を越えて残る仕事として見ることだ。そうすると面会の記憶が後年まで燃え続けた理由が見えてくる。
ロダン作品を知ると面会が見えやすい
晶子の衝撃を想像しやすくするために、ロダン作品の性格も押さえておきたい。《地獄の門》はダンテ『神曲』に取材した大作で、ロダンが長年取り組んだ中心的プロジェクトとして知られる。
《考える人》も《地獄の門》と深く結びつき、もともとはその一部として構想された像だと説明されることが多い。
ロダンの彫刻は、人間の感情や葛藤を石や青銅に刻みつけるような強さを持つ。晶子がロダンを「カテドラル」と呼んだのは、こうした量と時間の感覚を肌で受けたからだろう。
作品を少し知ってから『巴里より』を読むと、面会の場が一段くっきりしてくる。
事実確認のために当たるべき資料
事実関係を確かめたいなら、入口は三つある。
第一に、面会日と書簡を示す公的資料。ここで1912年6月18日の面会、展覧会の仲立ち依頼、1913年3月12日の書簡という骨格が読める。
第二に、紀行文『巴里より』本文とその解説。帰国時期や旅の経緯が整理されている。
第三に、歌集『火の鳥』と研究論文。追悼歌の位置づけが確認できる。
一次に近い情報を中心に組み立てることが、「与謝野晶子とロダン」を誤解なく理解するための最も堅い手順になる。
まとめ
- 晶子は1912年5月に渡欧し、パリを拠点に各地を回った
- 面会日は1912年6月18日と確認できる
- ロダンは日本での展覧会の仲立ちを夫妻に頼んだとされる
- 1913年3月12日付でロダンの寛あて書簡が作成された
- 晶子は妊娠が分かり1912年10月に帰国、寛は翌1913年1月に帰国
- 四男アウギュスト(1913年4月出生)は事実として示せる
- 名の由来は「ロダンにちなむとされる」程度に留めるのが安全
- 『巴里より』には「ロダン翁」の章があり、面会が重要な出来事として扱われる
- 追悼歌「ああロダン君は不思議のカテドラル…」は『火の鳥』(1919年)所収とされ
- ロダン代表作を知ると晶子の驚きが理解しやすい