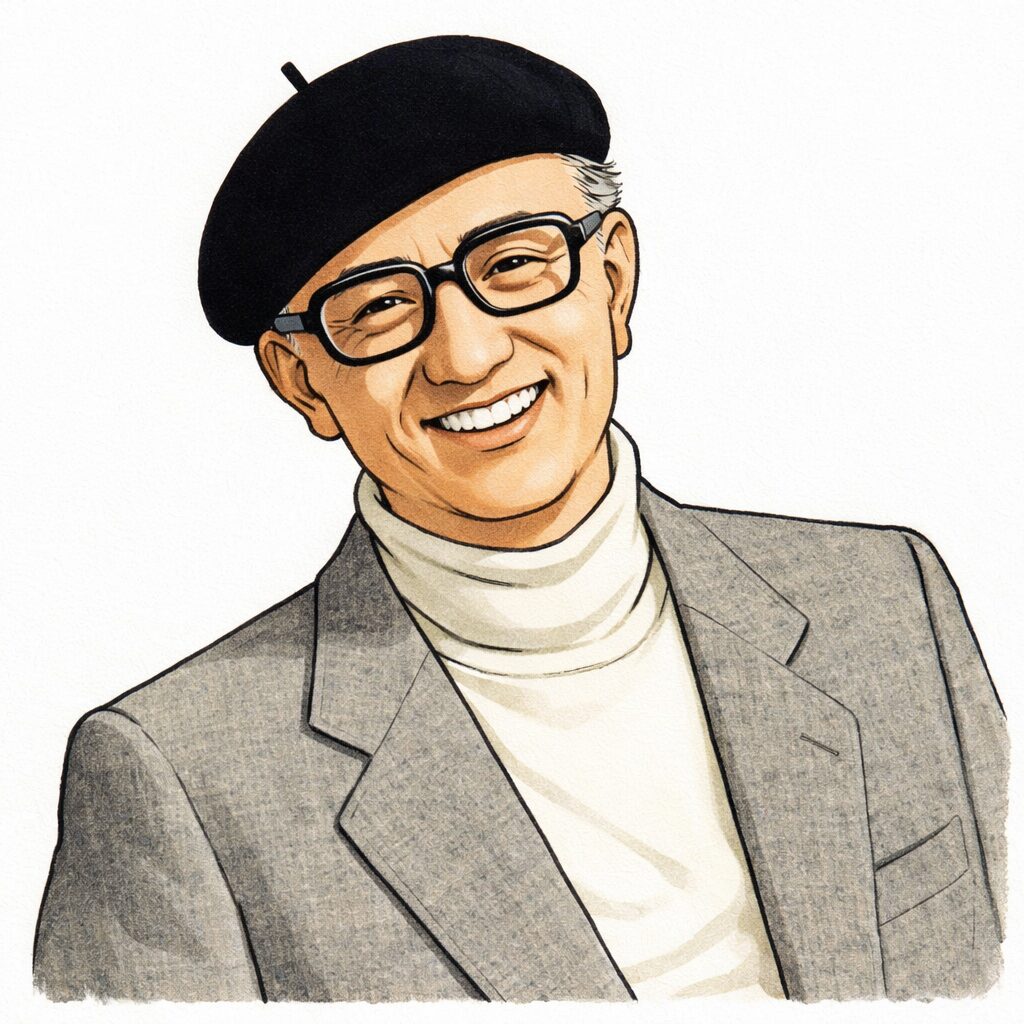「三島由紀夫と美輪明宏がキスした」という話は、刺激が強いぶん、事実と想像が混ざりやすい。
先に結論を言うと、この“キス”が語られる中心は、映画『黒蜥蜴』(1968)にある「生人形(剥製のように展示された人間)」の場面だ。作品データ上でも、三島由紀夫は「日本青年の生人形」として特別出演している。
ただし、ここで大事なのは二段階で整理することだ。一つ目は「作品の中で、どう描かれているか」。二つ目は「現実の二人の関係を、どう語れるか」。
作品内の演出を、そのまま現実の恋愛話に直結させると、かえって本筋を見失う。『黒蜥蜴』は、二人の“関係”をゴシップで消費するより、二人の美意識が交差した瞬間として見るほうが、ずっと面白い。
三島由紀夫と美輪明宏のキスが語られるのは『黒蜥蜴』
まず押さえる作品データ
映画『黒蜥蜴』は、1968年に公開された作品で、監督は深作欣二、原作は江戸川乱歩、戯曲は三島由紀夫という形で並ぶ。主演は美輪明宏(当時名義:丸山明宏)で、明智小五郎は木村功が演じている。そして重要なのが、三島由紀夫のクレジットだ。作品データでは、三島は「(特別出演)日本青年の生人形」と明記されている。つまり、「生人形」という設定の場面に、三島本人が“無言の存在”として登場するのが公式情報として確認できる。
「生人形(剥製)」と口づけの“語られ方”
『黒蜥蜴』の物語には、黒蜥蜴のアジトに「人間剥製の美術館」がある、という発想がはっきりある。この「恐怖美術館」「剥製」「生人形」という装置の中で、三島が“剥製にされた生人形”として現れる。そして「キス」については、記事や紹介文の中で、「このシーンで、黒蜥蜴役の美輪は人形役の三島と口づけを交わす」と説明されることが多い。ここでポイントは、「どこで?」の答えが、現実の場所の話ではなく、作品世界の中の場面指定として語られていることだ。つまり「黒蜥蜴のアジトにある“恐怖美術館(人間剥製の美術館)”で、生人形として展示された青年に対する演出」として説明されるのが、この話の芯になる。
ここで注意
「作品内の演出」と「現実の関係」は、同じ線で結ばないほうがいい。なぜなら、『黒蜥蜴』自体が、誘惑・変装・倒錯・美の蒐集といった要素を、わざと濃く、舞台的に配置した作品だからだ。作品は作品として確認できる。一方で、現実の二人がどういう関係だったのかは、本人の言葉や信頼できる記録で慎重に見る必要がある。
三島由紀夫と美輪明宏|『黒蜥蜴』とは
原作と戯曲化
『黒蜥蜴』は江戸川乱歩の小説が出発点にある。その小説をもとに、三島由紀夫が戯曲として形にした。乱歩の筋立てを借りながら、言葉の美しさ、倒錯の香り、舞台的な決めの強さを前に押し出すのが戯曲版の特徴になる。ここに美輪明宏の舞台感覚が重なることで、『黒蜥蜴』は「物語」以上の存在になっていく。
映画版の基本情報
映画版『黒蜥蜴』は松竹配給で、監督は深作欣二、脚本にも深作が関わる。キャストは、黒蜥蜴(緑川夫人)=丸山明宏(美輪明宏)、明智小五郎=木村功などが軸になる。三島由紀夫は、前述の通り「生人形」として特別出演だ。
三島由紀夫と美輪明宏は恋愛関係だったのか
美輪さんが“恋愛関係ではない”と述べる文脈
この話題で一番ねじれやすいのが、「キスがあるなら恋人だったのでは」という短絡だ。しかし、美輪明宏本人の語りとして、「お互いに恋愛感情はなかった」「恋愛関係ではない」という趣旨が伝えられている。ここを押さえると、見え方が変わる。『黒蜥蜴』は、恋人同士の逸話として読むより、「美と演劇と文学が接触した現場」として読むほうが、作品とも二人とも裏切らない。
「95%と5%」「俺に惚れないことだ」
美輪明宏が三島由紀夫との関係を語る中で、「95%と5%」という比率で気持ちを説明する文脈が紹介されることがある。また、印象的な言い回しとして「俺に惚れないことだ」という短い言葉が、二人の距離感を象徴するものとして語られることが多い。こうした言葉は、恋愛の告白というより、距離感を含んだ“美意識の会話”に近い。相手を自分の物にしたい、という単純な支配ではなく、相手の才能や魅力を認めながら、踏み込みすぎない線を引く。その線引きが、逆に強い磁力になる。
この章の結論
恋愛かどうか、で片づけると薄くなる。二人の間にあったのは、敬意、警戒、感心、演劇への執着、言葉への執着、そして“美”への共犯関係のようなものだ。その交点が、『黒蜥蜴』という作品で一度、目に見える形になった。“キス”は、その象徴として語られている。
なぜ三島由紀夫は美輪明宏に『黒蜥蜴』を頼んだのか
「毛皮のマリー」を観た三島が懇願→実現、という流れ
舞台版『黒蜥蜴』が生まれた背景としてよく語られるのが、三島が美輪の舞台『毛皮のマリー』を観て、強く出演を頼み込み、断られてもなお懇願し、実現したという流れだ。ここは、ただの思いつきではない。三島は「この人でなければ成立しない」と見たから、二度断られても引かない。その執着自体が、三島らしい。
三島が評価した“セリフ術/レトリック”の話
三島の台詞は、計算され尽くした美しい日本語として語られることが多い。『黒蜥蜴』は筋だけでも楽しめる。しかし舞台版、とくに美輪版の強さは「台詞が音楽のように作用する」点にある。三島の言葉は、意味だけでなく、響きやリズムで観客を縛る。美輪は、その言葉を“演じる”というより、“纏う”ことで成立させる。ここに、文学と舞台の結婚がある。
三島由紀夫と美輪明宏の“キス”が象徴するもの
生人形=保存された美(剥製)という装置
『黒蜥蜴』の核心には「人間剥製の美術館」という装置がある。美しいものは、壊れる。若さは、必ず消える。だから黒蜥蜴は、盗むだけでなく、“保存”しようとする。宝石よりも、人間の美しさを永遠にするほうが、よほど危険で、よほど魅力的だ。「生人形」は、その極端な結論だ。生きた人間を、動かない美として固定する。これほど残酷で、これほど耽美的な発想はない。
『黒蜥蜴』が描く「完成の瞬間を固定する」発想
『黒蜥蜴』では、黒蜥蜴と明智の関係が、ただの追う者と追われる者に収まらない。そこには、憎しみと惹かれ合いが混ざる。近づけば壊れる。だから、理想の形のまま止めたくなる。そのために、死や固定化のイメージが必要になる。「剥製の美術館」も、同じ思想の延長にある。美は、変化と引き換えに永遠になる。永遠は、命と引き換えに手に入る。その交換が、作品全体に漂っている。
三島美学と美輪の舞台美学が交差する点
三島由紀夫は、肉体、鍛錬、死、様式、そして完成への執念を作品にも生き方にも刻んだ人物だ。美輪明宏は、舞台の上で、声、衣裳、照明、香りさえも含めて、世界を作る。二人とも「生のままの現実」をそのまま出すことに満足しない。現実を、様式へ変える。人生を、演劇へ変える。だから『黒蜥蜴』は、ただのミステリーでは終わらない。“キス”が語られるのも、そこだ。もしそれが作品内に置かれているなら、それは恋愛の証拠というより、「美を固定する装置が、ついに肉体に触れる瞬間」として配置されている。しかも相手は、台詞のない「生人形」だ。言葉の人である三島が、言葉を奪われ、ただ“美の対象”として置かれる。この残酷さと、甘美さ。だからこの場面は、長く語られる。
三島由紀夫と美輪明宏に関するよくある質問
Q. キスは本当に“した”の?
「映画の『生人形』場面で、美輪と三島が口づけを交わす」と説明する文章は見つかる。ただし、ここで重要なのは、まず作品内の演出として受け止めることだ。現実の関係を断定する材料にはしないほうがいい。この作品は、倒錯や耽美を“舞台的に”強く見せる作りになっている。
Q. 二人は恋人だった?
美輪明宏の語りとして「恋愛感情はなかった」「恋愛関係ではない」という趣旨が伝えられている。“キス”の有無で恋愛を決めるより、二人の関係は「敬愛と緊張の混ざった距離」として見るほうが説明力がある。
Q. 映画と舞台は別物?どっちを観ればいい?
別物と考えたほうがいい。映画は映像の派手さやテンポが強く、豪華さが前面に出る。舞台は、三島の台詞の密度と、美輪の演出が“言葉と身体”で観客を支配する。最初の一本なら、話題の場面を含む「映画」を押さえ、そのあとで舞台の台詞の強さを味わう流れが理解しやすい。
Q. 今どこで観られる?
まとまった動きとして確認しやすいのは、円盤と放送だ。円盤や放送は時期で変わるため、今の状況は作品名で調べて最新の案内を見るのが確実だ。
まとめ
- 「三島由紀夫と美輪明宏のキス」として語られる中心は、映画『黒蜥蜴』(1968)の「生人形」場面だ
- 三島由紀夫は映画内で「日本青年の生人形」として特別出演し、展示物のように扱われる設定が核になる
- 黒蜥蜴のアジトには「人間剥製の美術館」という装置があり、作品全体の耽美性と残酷さを支える
- “キス”は現実の恋愛エピソードというより、作品内の演出・象徴として語られやすい
- 作品内の表現と、現実の二人の関係は混同しないほうが理解が正確になる
- 『黒蜥蜴』は江戸川乱歩の原作を、三島由紀夫が戯曲化し、深作欣二が映画化した流れで成立している
- 美輪明宏(当時名義:丸山明宏)の主演が、作品の妖しさや華やかさを決定づけている
- 二人の関係は「恋人だったか」で片づけるより、敬意と緊張を含む距離感として捉えるほうが筋が通る
- 舞台版誕生には、三島が美輪の舞台『毛皮のマリー』を観て強く出演を求めた、という経緯が語られることが多い
- “生人形”は「美を保存し、完成の瞬間を固定したい」というテーマを体現し、三島の美学と美輪の舞台美学の交点になる