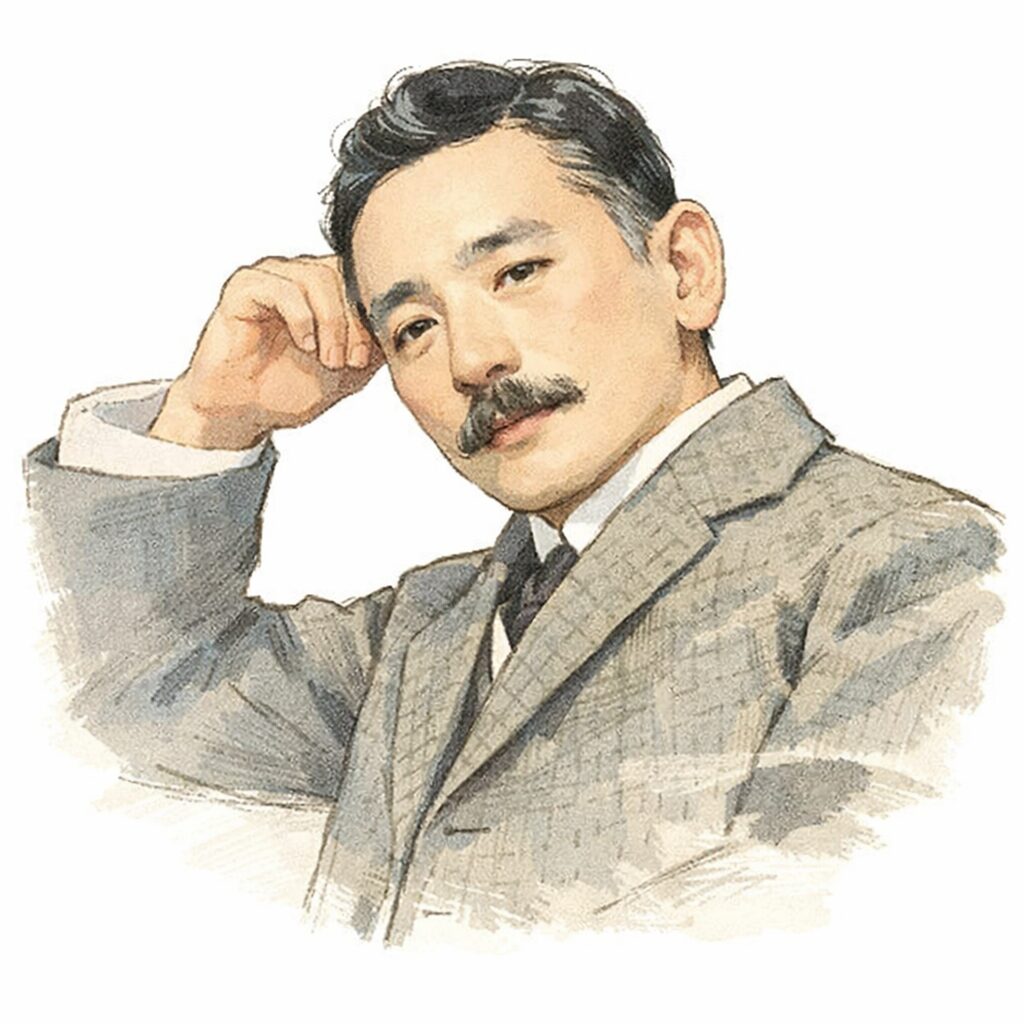『怪談』や『知られぬ日本の面影』などの名著で知られる小泉八雲ことラフカディオ・ハーン。彼の肖像写真を見ると、ある奇妙な共通点に気づくひとも多いはずだ。現存する八雲のポートレートは、そのほとんどが顔の右側をカメラに向けた横顔か、あるいは伏し目がちにうつむいた姿で写されている。彼が頑なに正面からの撮影を避けた背景には、若き日に負った左目の深い傷と、生涯消えることのなかったコンプレックスがあった。
八雲の左目は、彼がまだ16歳という多感な少年時代に、不慮の事故によって失明している。その瞳は視力を失っただけでなく、外見上も白く濁ってしまい、彼はそれをひどく恥じていたといわれている。この身体的な特徴は、彼の内向的な性格を形成する大きな要因となっただけでなく、後に日本で紡ぎ出される文学作品の独特な世界観にも、少なからぬ影響を与えたと考えられている。
本記事では、小泉八雲の左目にまつわる事故の真相から、彼が抱え続けた容姿への葛藤、そして隻眼というハンディキャップがいかにして彼の作家としての才能を開花させたのかについて詳しく掘り下げていく。世間でまことしやかに語られる「オッドアイ説」の真偽や、残された右目の視力についても、確かな記録をもとに紐解いていきたい。
見えない左目と、極度の近視だった右目。限られた視覚の中で八雲が見つめていたのは、現実の風景だけではなかった。彼が心の目を通して捉えた「目に見えない世界」の正体に迫ることは、小泉八雲という稀代の作家の魂に触れることでもある。彼の瞳の奥に隠された真実を知れば、怪談物語の行間から、これまでとは違ったメッセージが読み取れるようになるだろう。
小泉八雲の左目が失明した原因と当時の状況
16歳の学生時代に起きた悲劇的な事故の詳細
小泉八雲が左目の視力を失ったのは、彼が16歳だった1866年のことだ。当時の彼は、イギリス北部のダラム州にあるセント・カスバーツ校、別名ユショー・カレッジというカトリック系の神学校に在籍していた。アイルランド育ちの八雲にとって、厳格な規律と信仰を重んじるこの寄宿学校での生活は、決して心安らぐものではなかったといわれている。
ある日、校庭での休憩時間に悲劇は起こった。多くの生徒たちが興奮しながら遊具で遊んでいる最中、八雲の左目に固い物体が激しく衝突したのだ。それは一瞬の出来事であり、あまりの激痛に彼はその場にうずくまったに違いない。すぐに医師の手当てを受けたものの、眼球へのダメージは深刻で、当時の医療技術では視力を回復させることは不可能だった。
この事故は、単に片目の視力を奪っただけでなく、思春期の少年であった八雲の心に深い影を落とした。異国での生活、親族との複雑な関係に加え、自身の身体の一部が損なわれるという体験は、彼の孤独感をより一層深める結果となったのである。この時期に味わった喪失感や絶望が、後の彼の作品に見られる「はかなさ」や「哀愁」の原点になったとも考えられるだろう。
原因となったロープ遊び「ジャイアント・ストライド」
八雲の左目を奪った事故の原因については、当時の学校で流行していたジャイアント・ストライドという遊具によるものだと特定されている。これは、グラウンドに立てられた高い支柱の頂点から何本もの長いロープがぶら下がっているという、当時のイギリスの学校では一般的な遊具だった。
遊び方はシンプルで、子供たちがそれぞれのロープの端にある取っ手や結び目を掴み、支柱の周りを勢いよく走って回るというものだ。スピードに乗ると体が宙に浮き、まるで巨人が大股で歩いているかのような浮遊感を味わえることから、この名がついたといわれている。しかし、遠心力がかかるため、ロープの制御を失うと危険な凶器にもなり得た。
事故の際、八雲が自らロープを握って回っていたのか、あるいは近くで見学していたところに誰かのロープが飛んできたのかについては、詳細な記録によってニュアンスが異なることもある。しかし、ロープの先端にある結び目、あるいは持ち手の金具部分が、不運にも彼の左目を直撃したことは事実である。楽しく遊ぶはずの場所が一転して悲劇の舞台となり、八雲の人生を大きく変えてしまったのだ。
治療の経過と視力を失ったあとの目の変化
事故直後、八雲は激しい痛みと恐怖に襲われたはずだが、その後の経過はさらに過酷なものだった。眼球の組織が傷ついたことで炎症が起き、左目は徐々にその機能を失っていった。当時の眼科医療では、感染症を防ぐことや痛みを和らげることはできても、損傷した網膜や水晶体を修復する術はなかったからだ。
やがて炎症が治まると、彼の左目は光を失っただけでなく、外見上も明らかな変化をきたした。黒目の一部が白く濁り、全体が変色してしまったのである。これを外傷性白内障や角膜白斑と推測する専門家もいるが、いずれにせよ、かつての澄んだ瞳は失われ、他人から見てもひと目でわかる異変が残ってしまった。
八雲自身、この目の変化を鏡で見るたびに大きなショックを受けたことだろう。視覚的な情報量が半分になるという機能的な不便さに加え、「人と違う目」になってしまったという事実は、彼の自尊心を深く傷つけた。この白濁した左目は、彼にとって隠すべき傷跡となり、その後の人生において他者と対面する際の大きな心理的障壁となっていくのである。
家族との関係悪化や孤独感への影響について
左目を失明した16歳という年齢は、八雲にとって家庭環境が崩壊しつつある時期とも重なっていた。幼い頃に両親が離婚し、実の母とは生き別れ、父もまた再婚して彼のもとを去っていた。大叔母に引き取られて育てられていたものの、彼女との関係も信仰上の理由などでぎくしゃくし始めていた頃である。
そんな中で起きた失明事故は、八雲の孤独を決定的なものにした。頼れる親がおらず、学校という閉鎖的な社会の中で大きな怪我を負った彼は、「自分は誰からも愛されていないのではないか」という疑念を強めたかもしれない。また、神学校で起きた事故であるにもかかわらず、神が自分を守ってくれなかったという事実は、彼の宗教観にも影響を与え、後のカトリック信仰からの離反につながったという見方もある。
身体的なハンディキャップと、家族という後ろ盾の喪失。この二重の苦しみは、彼をより内面世界へと向かわせた。現実の世界に居場所がないと感じた少年は、本の世界や物語の世界へと逃げ込み、そこで安らぎを見出すようになる。この時期に培われた孤独な魂と想像力こそが、後の文豪ラフカディオ・ハーンを形作る重要な土壌となったことは間違いない。
小泉八雲の左目を隠す写真アングルと容姿への葛藤
現存するポートレート写真が右顔ばかりである理由
書店や図書館で小泉八雲の写真を目にする機会があれば、ぜひその顔の向きに注目してみてほしい。驚くべきことに、現在残されている彼の写真のほぼすべてが、顔の右側を向けた横顔か、やや斜め右からのアングルで撮影されている。正面を向いて堂々と写っている写真は、極めて稀か、あるいは存在しないと言っても過言ではない。
これは偶然ではなく、八雲自身の強い意志によるものだった。彼は写真技師に対して、自分の左側を撮らないよう厳しく注文をつけていたといわれる。白濁した左目が写真に写り込むことを極端に恐れ、最も自分が美しく、あるいは普通に見える角度を熟知していたのだ。集合写真においてさえ、周囲の人々が正面を向いている中で、彼一人だけが横を向いたり、うつむいたりしている姿が確認できる。
この徹底した「右顔」へのこだわりは、彼がいかに自分のイメージをコントロールしようとしていたかを物語っている。写真という記録媒体が普及し始めた時代にあって、彼は自分の「理想の姿」だけを後世に残そうとしたのかもしれない。その結果、私たちは彼の右側の顔立ちはよく知っているが、左側から見た彼がどのような表情をしていたのかを知る術をほとんど持たないのである。
白濁した瞳に対する強いコンプレックスの正体
八雲がこれほどまでに左目を隠そうとした背景には、単なる羞恥心を超えた深いコンプレックスがあった。彼は自分の白濁した左目を「醜いもの」や「他人に不快感を与えるもの」と思い込んでいた節がある。特に、感受性が強く美意識の高かった彼にとって、顔の一部が損なわれていることは耐え難い苦痛だったのだろう。
当時の西洋社会や日本において、身体的な差異に対する視線が今よりもずっと容赦なかったことも想像に難くない。彼は会話をする際にも、相手に左目を見られないよう、手で顔を覆ったり、やや顔を背けたりする癖があったとも伝えられている。この動作は、彼が常に他者の視線を意識し、緊張状態にあったことを示唆している。
また、彼のコンプレックスは、異性との関係においても影を落とした。若い頃の彼は、自分の容姿が原因で女性に愛されないのではないかと悩み、積極的な恋愛に踏み出せない時期もあったようだ。この「自分は異形である」という自己認識は、後に彼が日本の妖怪や幽霊といった「異界の存在」に深い愛着と共感を寄せる心理的なベースになったとも言われている。
拡大鏡を使って執筆する姿と残された右目の視力
左目を失明した八雲にとって、頼みの綱は残された右目だけだった。しかし、その右目もまた、強度の近視に侵されていた。もともと近視の傾向があったところに、片目での生活による負担がかかったのか、彼の視力は晩年になるにつれてさらに低下していったといわれている。
彼が執筆や読書をする際の姿は、鬼気迫るものがあった。特注で作らせた高さのある机に向かい、紙に鼻がくっつくほどの至近距離まで顔を近づけて文字を書いていたのだ。さらに、細かい文字を読むためには、常に持ち歩いていた片眼鏡や強力な拡大鏡が欠かせなかった。
周囲の人々から見れば、その姿は異様に映ったかもしれない。しかし、八雲にとってそれは、愛する文学の世界と繋がるための唯一の手段であり、必死の営みだった。彼はわずかに残された視力を極限まで使い、膨大な書物を読み漁り、緻密な文章を書き続けた。あの美しい英語の散文は、ほとんど見えない目から絞り出すようにして生み出された、執筆への執念の結晶だったのである。
妻のセツが語った八雲の目に対する気遣い
日本で八雲と結ばれ、その生涯を支え続けた妻・小泉セツ。彼女は夫の目に対するコンプレックスを誰よりも深く理解し、優しく寄り添った女性だった。セツの回想録などを読むと、彼女が八雲の目のことには決して触れず、また彼が気に病まないよう細心の注意を払っていたことがわかる。
セツは、夫が執筆に疲れた様子を見せると、代わりに日本の民話や怪談を語って聞かせた。八雲はその話を熱心に聞き入り、独自の解釈を加えて英語の物語へと再構成していった。この「妻が語り、夫が書く」という共同作業は、目を酷使する八雲の負担を減らすという意味でも、非常に理にかなった創作スタイルだったといえる。
また、セツは日常生活でも、視力の悪い夫が怪我をしないよう、家具の配置に気を配ったり、外出時にさりげなくサポートしたりしていた。八雲が日本での生活に安らぎを見出し、数々の名作を残すことができたのは、彼の「見えない苦しみ」を黙って受け止め、支え続けたセツの献身的な愛があったからこそである。彼女の前でだけは、八雲も目のコンプレックスから解放され、心安らかにいられたのかもしれない。
小泉八雲の左目にまつわる噂と作家活動への影響
碧眼やオッドアイという誤解が生まれた背景
現代において、アニメやゲームなどの創作作品で小泉八雲、あるいは彼をモデルにしたキャラクターが描かれる際、左右の目の色が違う「オッドアイ」として表現されることがある。これにより、「小泉八雲は生まれつき神秘的なオッドアイだった」と誤解している人も少なくない。しかし、史実における彼の目の色は、先天的なものではなく、事故による後天的な変化である。
八雲の左目が青や灰色、あるいは白っぽく見えたのは、失明に伴う眼球の白濁や虹彩の変色が原因だ。右目が本来の色、おそらくは茶色や暗めの色であったのに対し、左目が病的に変色してしまったため、結果として左右の色が異なって見えたのである。これを神秘的な「碧眼」と捉えるのは、後世のロマンチックな解釈に過ぎない。
ただ、この誤解が広まった背景には、彼が持つ「西洋と東洋の架け橋」というイメージや、怪談という超自然的なテーマを扱った作家性が関係しているのかもしれない。左右で異なる目を持つという特徴は、二つの異なる文化や、現世と来世を見つめる彼の特異な存在感を象徴する記号として、フィクションの中で魅力的に映るのだろう。事実は痛ましい事故の結果であっても、それが伝説化していく過程そのものが、八雲的であるともいえる。
隻眼の視界が研ぎ澄ませた聴覚と怪談への傾倒
視覚からの情報が制限されていたことは、八雲の他の感覚、特に「聴覚」を研ぎ澄ませる結果となった。彼の作品を読むと、音に対する描写が驚くほど繊細で豊かであることに気づかされる。下駄が石畳を叩く音、虫の音、風が木々を揺らす音など、彼は耳から入る情報で日本の情緒を感じ取っていたのだ。
代表作『怪談』に収められた「耳なし芳一」の話などは、その最たる例だろう。盲目の琵琶法師が平家の亡霊に琵琶を弾じ、その音色が聴く者の魂を揺さぶるという物語は、視覚を閉ざされた者の世界がいかに深淵で、かつ恐ろしくも美しいかを如実に描いている。八雲自身もまた、視力に頼れない分、音の響きの中に物語の真髄を見出していたのではないだろうか。
彼が怪談というジャンルに強く惹かれたのも、それが「目に見えないもの」の気配や音、雰囲気を重視する文学だからかもしれない。幽霊や妖怪は、はっきりとは見えないからこそ恐ろしく、また魅力的である。八雲の隻眼は、明るい光の下では見過ごされてしまうような、闇の中に潜む微かな音や気配を捉えるための、特別なアンテナの役割を果たしていたといえる。
視覚的なハンディキャップが生んだ独特な観察眼
八雲の文学の魅力は、単なる風景描写にとどまらず、その奥にある「心」や「精神」を描き出している点にある。これには、彼の視覚的なハンディキャップが逆説的にプラスに働いた側面がある。彼は対象物を物理的にはっきりと見ることが難しかったため、そのものの形よりも、それが放つ雰囲気や、背後にある歴史、人々の想いといった「目に見えない本質」を感じ取ろうとしたのだ。
一般の旅行者が素通りしてしまうような古びた地蔵や、名もなき小さな神社に対して、彼が深い愛着を示したのもそのためだろう。彼は表面的な美醜や新旧にとらわれず、そこに宿る日本人の信仰心や優しさを、心の目で見抜いていた。視力が弱いからこそ、想像力で補い、対象をより理想化して、あるいはより深く解釈して捉えることができたのである。
この独特な観察眼は、『知られぬ日本の面影』などの紀行文において遺憾なく発揮されている。彼の文章を通して見る日本は、当時の日本人自身が気づいていなかったような神秘性と美しさに満ちている。それは、物理的な視界がぼやけていたからこそ見えた、魂の風景だったのかもしれません。ハンディキャップは彼から光を奪ったが、その代わりに深い洞察力を与えたのである。
身体的なコンプレックスが生涯の放浪に与えた影響
小泉八雲の生涯は、ギリシャ、アイルランド、アメリカ、フランス領西インド諸島、そして日本と、地球を半周するような放浪の旅だった。この安住の地を求め続けた人生の根底にも、自身の身体的コンプレックスと、それに起因する「どこにも馴染めない」という疎外感があったと考えられる。
彼は自分の容姿を恥じ、西洋文明の中心地や華やかな社交界に背を向ける傾向があった。その代わりに彼が惹かれたのは、ニューオーリンズのクレオール文化や、マルティニーク島の素朴な暮らし、そして近代化以前の面影を残す日本の地方都市といった、いわゆる「周縁」の場所や人々だった。そこでは、彼のような異邦人や、社会的なマイノリティも、ある種の優しさを持って受け入れられると感じたのだろう。
自身の身体に「傷」を抱えていたからこそ、彼は虐げられた人々や、滅びゆく文化に対して、並々ならぬ共感と同情を寄せることができた。彼の文学に流れる弱者への温かい眼差しは、彼自身が味わった痛みと劣等感から生まれたものだ。日本という国が彼にとって終の棲家となったのは、ここが彼の傷ついた心と体を優しく包み込み、その異質さを才能として認めてくれた場所だったからに違いない。
まとめ
小泉八雲の左目は、16歳の時にイギリスの学校での遊戯中の事故によって失明し、その後白く変色してしまった。この事実は、彼に生涯消えることのない深いコンプレックスを植え付け、写真撮影の際に頑なに右顔しか見せないという特異な行動をとらせる原因となった。しかし、この悲劇的な事故と、残された右目の強度近視というハンディキャップは、彼の作家としての感性を鋭く研ぎ澄ませることにもつながった。
視覚情報が制限されたことで、彼は聴覚や想像力を極限まで発達させ、「耳なし芳一」に代表されるような、目に見えない世界を描く怪談文学の傑作を生み出した。また、自身の容姿への悩みは、社会の周縁に生きる人々や異文化への深い共感を生み、日本人の精神性を内側から理解する助けともなった。小泉八雲にとっての左目の失明は、個人的な悲劇であったと同時に、彼を唯一無二の文豪へと押し上げる運命的な転機でもあったといえるだろう。