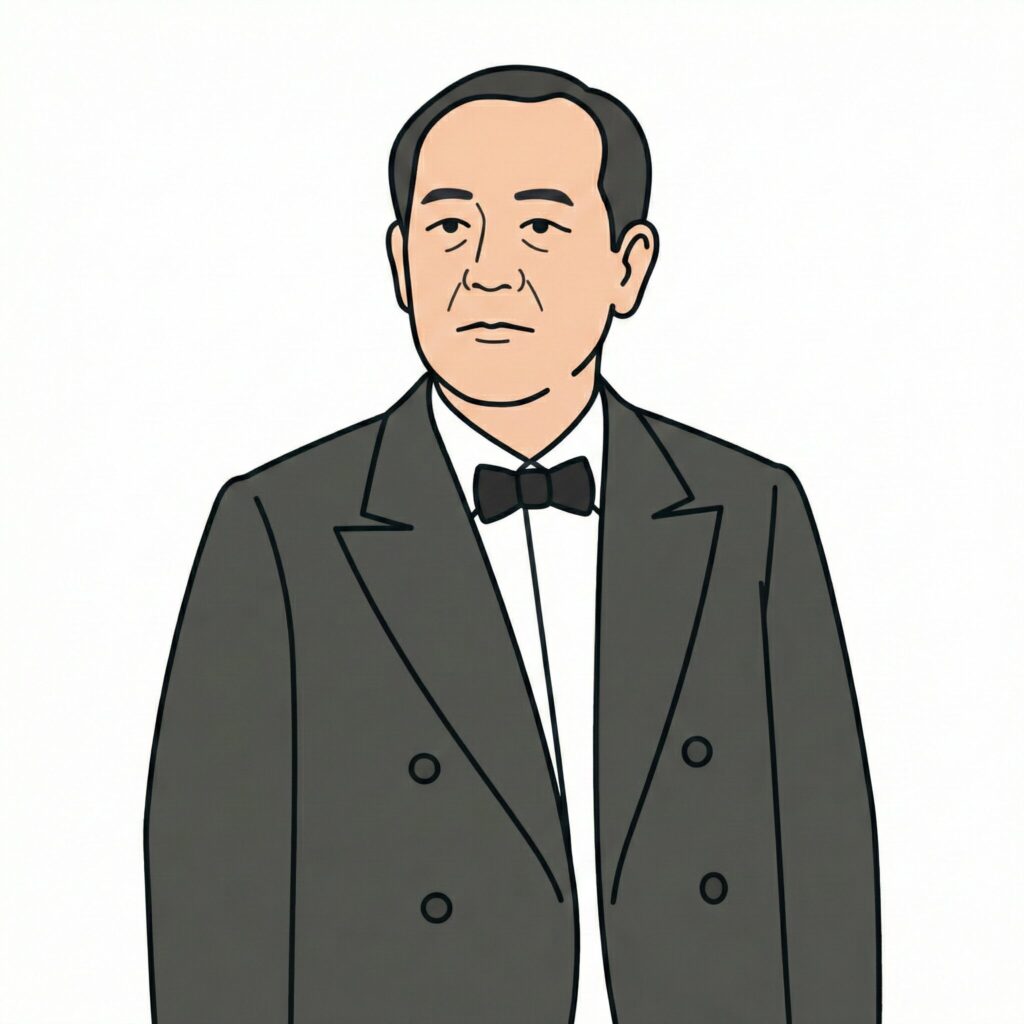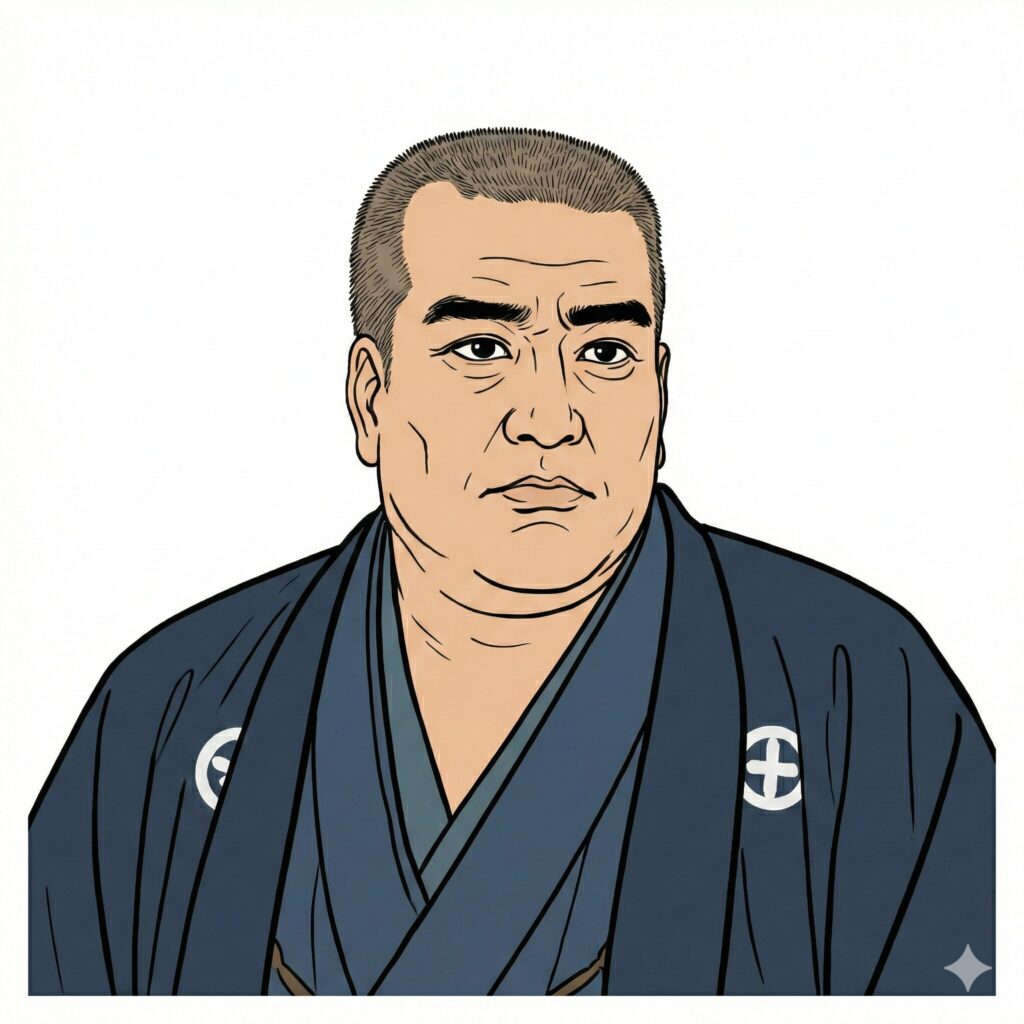小泉八雲ことラフカディオ・ハーンは、日本の怪談や文化を世界に広めた文学者として知られている。隻眼の文豪としても有名な彼は、明治時代の日本で数々の名作を残し、人々の心に深く刻まれる物語を紡ぎ出した。しかし、その生涯は54歳という若さで突然の幕引きを迎えることとなる。
彼がこの世を去ったのは、日露戦争の最中である明治37年(1904年)9月26日のことだった。季節が秋へと移り変わる時期に、自宅で夕食を待つ平穏な時間のなかで悲劇は起きた。偉大な作家の命を奪ったのは、心臓の病である。
直接的な死因は狭心症による心臓発作であったとされている。当時、彼はすでに体調の異変を感じており、死の直前にも胸の痛みを訴えていた。現代医学の観点からも、彼の生活習慣や激務が心臓に大きな負担をかけていたことは想像に難くない。
八雲が最期の瞬間に何を見、何を語ったのかは、妻であるセツの回想録によって今に伝えられている。そこには、死への恐怖よりも、静かに運命を受け入れるような穏やかな姿があった。彼が愛した日本の地で迎えた最期について、その詳細を紐解いていく。
小泉八雲の死因である狭心症と最期の瞬間
1904年9月26日の夜に起きた悲劇の瞬間
明治37年9月26日の夜、東京の西大久保にあった小泉八雲の自宅は、いつもと変わらぬ静けさに包まれていた。夕食の時間になり、八雲は書斎での仕事を終えて居間へと移動しようとしていた。その時、突如として激しい胸の痛みが彼を襲ったのである。これは以前から懸念されていた心臓の発作であり、家族にとっては恐れていた事態が現実となった瞬間でもあった。
八雲はこのとき54歳であり、作家として円熟期を迎えていたが、肉体的な衰えは隠せない状態にあった。発作が起きてから息を引き取るまでの時間は長くはなく、苦しみ抜いたというよりは、糸が切れるように静かに意識が遠のいていったと伝えられている。駆けつけた医師(かかりつけ医の岸清一博士であったと言われる)による懸命な処置も及ばず、偉大な文豪はその日のうちに帰らぬ人となった。
当時の日本は医療技術が発展途上にあったが、彼の症状は典型的な狭心症の発作として記録されている。この夜の出来事は、日本文学界にとっても大きな損失であり、多くの人々がその早すぎる死を悼んだ。彼の死は、日常のふとした瞬間に訪れたあまりにも突然な別れであり、夕食の団欒を目前にした悲劇的なタイミングであったことが、残された家族の悲しみをより深いものにした。
死の数日前にあった最初の発作という明確な予兆
八雲が亡くなるちょうど一週間前の9月19日、すでに死の予兆ともいえる最初の大きな発作が起きていた。彼はその日の夕方、友人への手紙を書いている最中に胸部に鋭い痛みを感じ、そのまま動けなくなってしまったという。このときは一時的に持ち直したものの、八雲自身も自分の命がそう長くはないことをはっきりと悟っていた節がある。
この最初の発作の後、八雲は「私、新しい病気を得ました」と語り、家族に対して自分の身に何かあったときのことを静かに話し始めたといわれている。彼は自分の死を恐れるのではなく、残される家族、特に妻のセツや子供たちが路頭に迷わないようにと、将来のことを具体的に案じていた。この時期の彼は、体調不良をおして執筆や講義の準備を続けており、家長としての責任感の強さがうかがえる。
周囲の人々は彼に絶対安静と休養を勧めたが、八雲は書くことをやめなかった。最初の発作から亡くなるまでの約一週間は、彼にとって人生を振り返り、愛する日本での生活を噛みしめる最後の貴重な時間となったのである。この予兆があったからこそ、家族はある程度の心の準備ができていたとも言えるが、やはり別れの時はあまりにも早すぎた。
最愛の妻セツが見守る中で迎えた安らかな最期
小泉八雲の最期を看取ったのは、彼が誰よりも信頼し愛した妻、小泉セツであった。発作が起きた際、八雲はすぐにセツに助けを求め、彼女は彼を抱きかかえて必死に介抱した。セツの回想によれば、八雲は苦しい息の中で、彼女に対して感謝と別れの言葉を伝えようとしていたという。二人の絆は深く、セツの腕の中こそが彼にとって最も安心できる場所であった。
二人の関係は、単なる夫婦という枠を超え、日本の怪談や伝承を共に発掘するかけがえのないパートナーでもあった。セツが語る日本の不思議な話を八雲が聞き書きすることで、数々の名作が生まれたのである。そのため、最期の瞬間にセツがそばにいたことは、八雲にとって最大の救いであったに違いない。彼女の存在なくして、小泉八雲の文学は成立しなかったと言っても過言ではないからだ。
セツは動揺しながらも、夫が少しでも楽になるように背中をさすり、「パパさん」と声をかけ続けた。八雲は彼女の腕の中で、次第に力が抜けていき、苦痛の表情から解放された安らかな顔へと変わっていったとされる。愛する人のぬくもりを感じながら旅立てたことは、異国の地で骨を埋める覚悟を決めていた彼にとって、本望であっただろう。
亡くなる直前に残した言葉と桜の返り咲きの不思議
八雲が亡くなる直前、胸の痛みを訴えた彼にセツが寄り添うと、彼は「あぁ、病気のため(Ah, because of sickness)」と英語でつぶやいたと伝えられている。また、「ママさん、先日の病気、また参りました」とも語ったとされ、これが彼が残した最後の言葉の一つと言われている。苦痛の中にあっても取り乱すことなく、自分の状態を客観的に認識していた彼の知性が垣間見える瞬間である。
また、彼の死には不思議なエピソードが残されている。亡くなった日の朝、庭の桜の木に季節外れの花(返り咲き)が咲いているのをセツが見つけていた。八雲はこの桜を見て「春のように咲いた、ようこそ」と喜んだという。さらに、彼がかわいがっていた松虫が、その夜に限って物悲しく鳴いていたことなどが、後に『思い出の記』で語られている。セツはこれらの出来事を、夫の死を告げる予兆であったかのように回想している。
八雲自身も日本の自然や霊的な現象に深い関心を寄せていたため、こうした偶然もまた、彼の物語の一部のように感じられる。桜の返り咲きや虫の知らせといったエピソードとともに語られる彼の死は、どこか神秘的な雰囲気を帯びており、まさに彼が生涯をかけて描き続けた「怪談」の世界のような美しい幕切れであった。
小泉八雲の死因に深く関わった晩年の健康状態と生活
片目の視力喪失が執筆活動と身体に与えた負担
小泉八雲の外見的な特徴としてよく知られているのが、左目の視力を失っていたことである。彼は16歳のときに学生時代の事故で左目を失明しており、残された右目だけで生活し、膨大な量の読書と執筆を行っていた。この隻眼の生活は、彼の身体に想像以上の負担を強いていたと考えられる。右目の視力も非常に弱く、高度の近視であった。
文字を読むときや書くときは、紙に顔が触れるほど近づけなければならなかった。キセルを吸いながら、机にかじりつくようにして執筆する彼の姿は、家族にも心配されていた。このような姿勢での長時間の作業は、首や肩への激しい凝りを引き起こし、全身の血流にも悪影響を及ぼしていたはずである。眼精疲労は慢性的な頭痛やストレスの原因となり、心臓への負担を間接的に高める要因となった。
また、彼は自分の外見、特に白濁した左目を非常に気にしていたため、写真を撮られる際は必ず右側の顔を向けるか、うつむき加減で写っていた。こうした精神的な緊張感も、日々の生活において微細ながらも積み重なるストレスとなっていた可能性がある。視力のハンディキャップを乗り越えて執筆を続けた彼の精神力は凄まじいが、肉体はその代償を払い続けていたのである。
ヘビースモーカーとしての生活習慣と心臓へのリスク
小泉八雲は大変な愛煙家であり、パイプや葉巻を片時も手放さない生活を送っていた。当時の写真や肖像画でも、パイプをくわえている姿が多く残されている。執筆の合間や思索にふけるとき、紫煙をくゆらせることは彼にとって欠かせないリラックスの時間であり、精神統一の儀式のようなものであった。
しかし、現代医学の常識に照らし合わせれば、重度の喫煙習慣が狭心症や心臓病の重大なリスクファクターであることは明らかである。ニコチンは血管を収縮させ、血圧を上昇させる作用があるため、長年にわたる喫煙は彼の心臓の血管(冠動脈)を徐々に蝕んでいたと考えられる。当時の医学では喫煙の害はそれほど強調されていなかったため、彼自身にその自覚はなく、むしろ健康の源とさえ思っていたかもしれない。
彼が好んだ強いタバコの煙は、彼の精神を安定させる鎮静剤の役割を果たしていた一方で、肉体的には寿命を縮める一因となってしまった。もし彼が喫煙者でなければ、もう少し長く生きられたかもしれないという見方もできるが、タバコのない生活は彼にとって創作のインスピレーションを欠くものになっていた可能性もあり、その評価は難しいところである。
東京帝国大学を追われたことによる精神的なストレス
晩年の八雲を苦しめた大きな要因の一つに、職をめぐるトラブルとそれに伴う精神的ストレスがある。彼は長らく東京帝国大学(現在の東京大学)で英文学の講師を務め、学生たちから絶大な人気を誇っていた。しかし、明治36年(1903年)、大学側の方針や給与の問題により、事実上の解雇通告を受けることとなる。
この解雇劇は、彼の後任として夏目漱石が英国留学から帰国するタイミングと重なっていたこともあり、文学史的にも有名な出来事である。学生たちは八雲の留任を求めて運動を起こしたが、決定が覆ることはなかった。八雲にとって、愛する学生たちとの別れや、経済的な基盤を脅かされる事態は、大きな心労となった。彼は家族を養う責任を強く感じていたため、この時期の不安は計り知れないものがあっただろう。
その後、早稲田大学に迎えられることにはなったが、環境の変化や将来への不安が完全に払拭されたわけではなかった。繊細な感受性を持つ彼にとって、組織の論理で排除されたという経験は、プライドを傷つけられる出来事であり、心臓への負担を加速させる精神的なダメージとなっていた可能性は否定できない。
命を削るような執筆活動による過労と心臓への影響
八雲の晩年は、まさに命を削って執筆に取り組んでいた時期でもあった。彼は大学での講義の準備に加え、アメリカの出版社からの依頼や自身の著作の執筆に追われていた。特に『怪談(Kwaidan)』などの代表作が生まれたのはこの時期であり、創作意欲は衰えるどころか、ますます盛んになっていた。
しかし、その代償としての過労は深刻であった。前述した視力の問題に加え、完璧主義な性格もあって、納得がいくまで推敲を重ねる作業は深夜に及ぶことも珍しくなかった。運動不足になりがちな執筆生活と、不規則な睡眠時間は、心臓疾患を持つ人間にとっては最悪の環境といえる。彼はまさに、生命の灯火を燃やして作品を生み出していたのである。
彼は「書くこと」に生きがいを感じていたが、それは同時に肉体を酷使する行為でもあった。死の直前までペンを握り続けていたその姿勢は、作家としての業を感じさせるが、休息を取らずに走り続けたことが、心臓発作の引き金を引く遠因となったことは間違いない。彼の作品が持つ高い完成度は、彼の寿命と引き換えに生み出されたものとも言えるのである。
小泉八雲の死因と死後に残された家族との深い絆
葬儀の様子と雑司ヶ谷霊園にある静かな墓所
小泉八雲の葬儀は、彼の死から数日後に東京の寺院で仏式によって執り行われた。彼は生前、自分が死んだら簡素な瓶に入れて埋めてくれればよいと語っていたが、実際には多くの教え子や文壇関係者が参列する厳かな式となった。キリスト教圏で生まれ育った彼が、日本式の葬儀で送られたことは、彼がいかに日本に同化していたかを示している。
彼の遺骨は、東京都豊島区にある雑司ヶ谷霊園に埋葬された。この場所は、後に夏目漱石などの多くの文化人も眠ることになる静かな聖地である。八雲の墓は、彼が愛した木々に囲まれた場所にあり、今でも多くのファンや文学愛好家が訪れ、花や線香を手向けている。墓石には彼の名が刻まれ、静寂の中に佇んでいる。
墓石のデザインや配置にも、日本文化を尊重した彼の精神が反映されている。雑司ヶ谷の森の静寂は、賑やかな都会の喧騒を嫌い、古い日本の風情を愛した八雲にとって、永遠の眠りにつくのにふさわしい場所であるといえるだろう。彼の墓所は、彼と日本との永遠の結びつきを象徴する場所となっている。
戒名「正覚院殿浄華八雲居士」に込められた思想
八雲には「正覚院殿浄華八雲居士」という立派な戒名が授けられている。この戒名には、彼の生涯や思想が見事に表現されている。特に「八雲」という文字が入っていることは、彼が出雲(島根県)の地で小泉八雲として日本に帰化したことへの敬意が込められている。出雲での生活は彼の日本理解の原点であり、その名を死後も背負うことは彼にとって本望だったはずだ。
「浄華」という言葉は、彼が美しいもの、純粋なものを愛した精神性を表しているようにも感じられる。彼は西洋の合理主義よりも、日本の精神世界や仏教的な無常観に共鳴していた。そのため、死後にこのような仏教風の名前で呼ばれることは、彼自身にとっても違和感のない、むしろ望ましいことであったかもしれない。
戒名は単なる死後の名前ではなく、その人がどのように生きたかを示す証でもある。異国の地からやってきて、日本人以上に日本の心を理解しようとした彼の魂は、この戒名を通じて日本の土に深く根を下ろしたのである。この戒名を見るたびに、彼がどれほど日本を愛していたかが偲ばれる。
死後に出版された作品群と世界的な評価の高まり
八雲が亡くなった時点で、彼の作品のすべてが出版されていたわけではなかった。彼の死後、遺稿となっていた原稿が整理され、いくつかの重要な作品が世に出ることとなった。特に晩年の集大成ともいえる『日本:一つの解明』などは、彼の死後に評価を不動のものにする重要な役割を果たした。
彼の死因となった心臓発作と闘いながら書かれた文章には、鬼気迫る美しさと、消えゆく「古き良き日本」への愛惜が込められている。読者は彼の死を知った上で作品を読むことで、そこに込められたメッセージをより深く受け取ることとなった。死してなお、彼の言葉は生き続け、世界中の人々に日本の文化を伝え続けたのである。
また、彼の死後、欧米でも彼の評価は高まり、日本文化の紹介者としての地位は決定的なものとなった。生前の苦労や大学でのトラブルは、時とともに風化し、純粋な文学的功績だけが輝きを増していった。彼の命を縮めた執筆活動は、結果として永遠の命を持つ作品群を残すことにつながったのである。
残された家族の生活と八雲の意思を継ぐ人々
八雲が最も心配していた残された家族たちは、彼の死後も互いに支え合いながら強く生きていった。妻のセツは、夫の遺品や原稿を大切に守り、彼の功績を後世に伝えるための役割を果たした。彼女の献身的な姿は、八雲の研究者たちの間でも高く評価されており、彼女がいなければ多くの資料が散逸していたかもしれない。
長男の小泉一雄をはじめとする子供たちも、父の記憶を大切にし、それぞれの道で父の教えを胸に生きた。特に一雄は、父に関する回想録を残しており、家庭人としての八雲の素顔を知るための貴重な資料となっている。家族の絆は、八雲が亡くなった後も決して途切れることはなく、むしろ強まっていったと言える。
現在でも、小泉八雲のひ孫にあたる小泉凡氏などが、彼の精神を受け継ぎ、文化活動や講演を行っている。八雲の死因は突然の病であったが、彼が蒔いた種は家族や研究者たちによって大切に育てられ、100年以上経った今でも大輪の花を咲かせ続けているのである。彼の血脈と精神は、今もなお日本の中で生き続けている。
まとめ
小泉八雲の死因は狭心症による心臓発作であり、54歳という若さでその生涯を閉じた。隻眼による身体的負担、ヘビースモーカーとしての習慣、そして大学解雇や執筆活動による過労とストレスが、心臓への大きな負担となっていたことは明らかである。
彼が亡くなる直前、妻のセツは桜の返り咲きを死の予兆と感じたと回想しており、八雲自身も「あぁ、病気のため」と言葉を残し、静かにこの世を去った。彼の肉体は滅びたが、その作品と精神は家族や後世の人々に受け継がれ、今なお多くの人々の心を捉えて離さない。